朝起きたらなんとなく喉がイガイガする、いつもより身体が重い気がする、「あれ、もしかしてかぜのはじまりかな?」
そんな小さな違和感を覚えたこと、誰にでもありますよね。
かぜのひきはじめは、いわば身体からの小さなSOS。
「ちょっと頑張りすぎたよ」「休むタイミングだよ」と教えてくれているのかもしれません。
でも、多くの人がそのサインを見逃してしまいがちです。
仕事や家事で無理をして、「大丈夫、まだ平気」と動き続けてしまううちに、気がついたら本格的にダウンしていた。
そんな経験はありませんか?
今回は、そんな「かぜのひきはじめ」に焦点を当てて、おうちですぐできるセルフケアをお伝えします。
そもそも「かぜのひきはじめ」ってどんな状態?


かぜの初期とは、ウイルスや寒さ、疲労、ストレスなどで身体のバランスが一時的に崩れた状態を指します。
西洋医学では、かぜはウイルス感染が原因とされていますが、東洋医学では、もっと広い意味で「身体の中と外の調和が乱れた状態」としてとらえます。
例えば
- 外からの冷えや乾燥(外邪)が入り込む
- 体内のエネルギー(気)や血のめぐりが滞る
- 休む時間が少なく、身体が回復しきれていない
といったことが重なると、身体の防御力が一時的に弱まると考えます。
その結果、寒気・のどの違和感・だるさなどの“予告サイン”が出るのです。
この段階でうまくケアできれば、身体が自分の力で整っていきやすいとも言われています。
あなたはどんなタイプ?かぜのひきはじめセルフチェック


かぜのひきはじめにも、人によって出やすいサインが違います。
ここで、自分がどのタイプかを簡単にチェックしてみましょう。
Aタイプ 寒気・ゾクゾクタイプ
- 首や背中がゾクッとする
- 手足が冷える
- 鼻水がさらさらしている
- 熱はないけど寒い
→冷え(陰)が強まっているサイン。
身体をしっかり温めて、“めぐり”をよくするケアを意識しましょう。
Bタイプ のど・発熱タイプ
- のどがイガイガ、痛みを感じる
- 顔がほてる
- 微熱がある
- 汗をかいてもスッキリしない
→身体の中に熱(陽)がこもっている状態。
冷たい飲み物ではなく、常温の水やハーブティーなどで穏やかにクールダウンを。
Cタイプ だるさ・気力不足タイプ
- 身体が重くて動くのがつらい
- 食欲がない
- 胃が重い
- 眠気が強い
→「気(エネルギー)」が足りないサイン。
無理せず休んで、あたたかくて消化のよいものを少しずつ摂りましょう。
かぜのひきはじめは「冷え」「熱」「気の不足」のいずれか、もしくはその複合タイプであることが多いです。
まずは「今の自分はどんな状態かな?」と観察することから始めましょう。
かぜのひきはじめに試したい5つのこと

温めて休む、まずは“陽”を守る

寒気やゾクゾクを感じたら、無理に動かずしっかり休むことが一番のケアです。
おすすめの過ごし方は、
- 首や背中を冷やさないようにする
- お風呂ではぬるめのお湯にゆっくりつかる
- 寝る前に白湯を一杯
特に、首・手首・足首の「三首」を温めると、身体全体の巡りが整いやすくなります。
体温を上げることよりも、“冷やさない”ことを意識しましょう。
食べ過ぎない、でも何も食べないわけでもない
風邪をひくと「食欲がない」という人も多いですよね。
そんなときは無理に食べず、胃腸の負担を減らすことを意識しましょう。
おすすめは、
- 野菜スープ
- おかゆ
- 味噌汁
など、温かくて消化のよいもの。
反対に、脂っこいものや冷たいものは控えるのがおすすめです。
陰陽五行の「脾(土)」は食べたものをエネルギーに変える大事な存在。
この脾をやさしく休ませてあげることが、回復の土台になります。
水分を少しずつとる
かぜの初期には汗をかくこともあり、知らないうちに水分が不足しがちです。
冷たい飲み物ではなく、常温の水や白湯を少しずつとるのがポイント。
特にのどがイガイガする場合は、
・はちみつ湯
・しょうが湯
などをゆっくり口に含むと、のどをやさしく潤します。
呼吸を整える
のどや鼻に違和感があるときこそ、呼吸をゆっくり深くしてみましょう。
- 肩の力を抜いて、鼻から息を吸う(4秒)
- 口をすぼめて、ゆっくり吐く(6秒)
これを数回繰り返すだけでも、気持ちが落ち着きます。
五行でいう「金(肺)」のエネルギーが整いやすくなるタイミングです。
頑張らない日をつくる
かぜのひきはじめは、「少し休みなさい」という身体の声。
無理をして家事や仕事を詰め込みすぎると、回復のタイミングを逃してしまいます。
ときには「今日はできる範囲でいい」と、自分をゆるめる勇気も必要です
食で整えるかぜ予防と回復の養生


陰陽五行の考えでは、秋冬は「陰」が強まり、「肺」と「腎」に負担がかかる季節。
冷えや乾燥に負けない身体をつくるには、日々の食事でバランスを整えることが養生の第一歩です。
体を温める「温養スープ」
冷えを感じたときにおすすめなのが、根菜と生姜を使ったスープ。
〈鶏と根菜のしょうがスープ〉
- 材料:鶏もも肉、大根、にんじん、ごぼう、生姜
- 作り方:材料を一口大に切り、だしや水で煮込む。仕上げにすりおろし生姜を加え、ごま油を少したらす。
→ 根菜は「土」の要素をもち、胃腸を整えてエネルギー(気)を補う。
〈豆腐と白菜のとろみ味噌スープ〉
- 材料:豆腐、白菜、長ねぎ、味噌、片栗粉
- 作り方:野菜を煮て味噌で味付けし、水溶き片栗粉で軽くとろみをつける。
→ 体を優しく温め、乾燥で荒れた喉を守る。
乾燥から守る「潤いデザート」
喉の痛みや乾いた咳には、肺を潤す食材を。
〈梨のはちみつ煮〉
- 材料:梨、はちみつ、水(少量)
- 作り方:皮をむいた梨をひと口大に切り、はちみつと水で軽く煮る。温かいうちにいただく。
- アレンジ:白きくらげを加えると、さらに潤い効果アップ。
→ 肺を潤し、喉の炎症をやわらげる。
〈りんごとくこの実のコンポート〉
- 材料:りんご、くこの実、レモン汁、はちみつ
- 作り方:すべてを小鍋に入れ、弱火で煮る。くこの実がふっくらしたら出来上がり。
→ ビタミンと潤いを補い、目と喉をいたわるデザート。
疲れを癒やす「お粥養生」
食欲がないとき、無理をせず体を休ませたいときに。
〈生姜塩粥〉
- 材料:米、水、生姜、塩少々
- 作り方:米を柔らかく煮て、生姜のしぼり汁と塩を加える。
- トッピング:黒ごまやくるみをのせると「腎」を補い、回復を助ける。
→ 胃腸にやさしく、体の芯から温めてくれる。
〈中華風とろとろ卵粥〉
- 材料:ご飯、鶏ガラスープ、卵、ねぎ、ごま油
- 作り方:ご飯をスープで煮て、最後に溶き卵を流し入れる。
→ 胃を温め、消化を助け、疲労回復にも効果的。
食は日々の薬。
冷えたら温め、乾いたら潤す。
季節と体調に合わせた食の工夫が、自然に体を整える最良の養生です。
食事について一緒に読まれている記事はこちら。
季節ごとのかぜの“はじまり方”と整え方


実は、かぜのひきはじめには季節ごとの特徴があります。
それぞれのシーズンに合ったケアを意識してみましょう。
春:寒暖差と自律神経のゆらぎ
- まだ朝晩が冷えるのに昼は暖かい時期。
- 薄着や冷たい飲み物に注意。
- 肩を回すストレッチで“気”の巡りを整えて。
夏:冷房と冷たい飲み物の影響
- 「内側の冷え」が起こりやすい。
- 冷たいドリンクを控えて、常温の水をこまめに。
- 汗をかいたらそのままにせず、タオルで拭くのがポイント。
秋:乾燥に注意
- 肺(金)の季節。乾燥でのどや鼻が敏感に。
- 加湿器やマスクで潤いを意識。
- 白い食材(大根、梨、れんこん)を取り入れるのもおすすめ。
冬:冷えと乾燥のダブルパンチ
- 外は寒く、室内は乾燥しがち。
- 三首を温める+加湿を意識。
- ストールや腹巻きなど“重ねる温もり”を。
かぜのひきはじめにしないほうがいいこと


つい無意識にやってしまう行動が、実は身体の回復を遅らせてしまうこともあります。
ここでは、かぜのひきはじめに避けたいことを、少し具体的に見ていきましょう。
無理に動く
「まだ大丈夫」「ちょっと寒気がするけど仕事は休めないし」と、ついそのまま動き続けてしまう、これがいちばん多いパターンです。
かぜのひきはじめは、身体のエネルギーが「回復」に使われている時間。
そのときに無理をすると、限られたエネルギーが「活動」の方に取られてしまい、結果的に回復が追いつかなくなってしまうことがあります。
特に、
- 朝から寒気やだるさを感じているのに運動をする
- 「気合い」で仕事を詰め込む
- 家事を完璧にこなそうとする
こうした“いつもの頑張り”が、かえって身体を疲れさせてしまうことも。
もし少しでも「おかしいな」と思ったら、“今日は6割で動こう”と決めてみてください。
たとえ家事が少し残っても、それは「休む時間をつくるための余白」です。
冷たいものを食べる・飲む
喉が乾いたとき、つい冷たい飲み物をゴクゴク飲んでしまう。
これも、かぜのひきはじめにありがちな落とし穴です。
身体が冷えているときに冷たいものを入れると、内側の「陽(温める力)」がさらに弱まり、結果として回復しにくくなります。
たとえば、
- 冷たいジュースや炭酸飲料
- アイスクリーム
- 氷の入ったドリンク
これらは一時的にスッキリしても、身体の中では「冷え」が広がってしまいます。
おすすめは、
- 白湯
- 常温の水
- はちみつ湯やしょうが湯
など、やさしい温度の飲み物。
特に、しょうがやはちみつは「陰陽のバランスを整える」食材としても知られています。
身体をゆっくり温めながら、のどの違和感をやわらげてくれます。
眠らずに作業を続ける
「ちょっと喉が痛いけど、明日の準備だけは終わらせたい」そんな気持ちで夜更かしをしてしまうこともありますよね。
でも、かぜのひきはじめに必要なのは「睡眠」よりも「休息の質」です。
夜ふかしをすると、自律神経のバランスが乱れ、身体の回復リズムが崩れやすくなります。
陰陽五行の考えでは、夜は“陰”の時間。
身体を静かに整えるための、大切な再生タイムなのです。
特に22時〜2時の間は、身体の回復に関わるホルモンが分泌されやすい時間帯。
その時間をできるだけ眠りに充てることで、翌朝のだるさが違ってきます。
「全部終わらせてから寝よう」ではなく、「今日は途中でもいいから横になろう」と思うくらいでちょうどいいのです。
不安になって検索ばかりする
少し熱っぽかったり、喉が痛かったりすると、ついスマホで「かぜ 早く治す方法」「喉 痛い 治し方」と検索してしまう。
この行動も、意外と身体に負担をかけています。
画面を見ることで目や脳が緊張し、交感神経(“頑張る神経”)が優位になります。
すると、回復に必要な副交感神経(“休む神経”)の働きが抑えられてしまうのです。
また、情報を見すぎると不安が大きくなり、そのストレスがさらに免疫バランスに影響を与えることもあります。
かぜのひきはじめは、情報を集めるよりも、「今、自分の身体がどう感じているか」に意識を向ける時間に。
たとえば、
- 手足は冷えていないか
- 喉の乾き具合はどうか
- 呼吸は浅くなっていないか
そんな小さな観察が、いちばんのケアにつながります。
「今日は身体の声を聞く日」と思って


かぜのひきはじめは、身体が「少し立ち止まって」と語りかけている時間。
それは、あなたの中で“整い直そう”とする自然な動きでもあります。
決して悪いことではありません。
たとえば、スマホのバッテリーが残り10%になった時、「充電しよう」と思うのは当然のことですよね。
それと同じように、身体も今、“充電タイム”に入っているのです。
こんなふうに、自分にやさしく声をかけてみましょう
- 「最近ちょっと頑張りすぎたね。今日はゆっくりしよう」
- 「無理しなくてもいいよ。ちゃんと休むことも大事」
- 「身体をここまで動かしてくれてありがとう」
そう言葉にしてみると、少しだけ心の緊張がほどけていくのを感じるはずです。
自分をいたわる言葉は、それだけで心の中の“陽”のエネルギーを優しく温めてくれます。
小さな「整いタイム」をつくる
かぜのひきはじめは、大げさなことをするよりも、小さな心地よさを積み重ねることがいちばんのケアになります。
たとえば
- 朝起きて、あたたかい白湯をゆっくり一杯飲む
- 毛布やブランケットにくるまり、深く息を吐く
- 目を閉じて、身体の“重さ”や“温かさ”を感じてみる
- 部屋の照明を少し落として、静かな音楽を流す
それだけで、身体の中の緊張がふっとゆるんでいきます。
身体の声に耳を澄ます、ちいさなワーク
もし余裕があれば、こんなセルフチェックをしてみてください。
- 目を閉じて、呼吸をゆっくり3回。
- 「今、どのあたりが一番疲れてる?」と自分に問いかける。
- 漠然とでも“首”“胃のあたり”“足”など、浮かんできたところを手でそっと触れる。
- 「ここを休ませてあげよう」と心の中でつぶやく。
これだけで、身体は「気づいてくれた」と安心してくれます。
その安心感が、“自分で整う力”をやわらかく後押ししてくれるのです。
おわりに


かぜのひきはじめは、「身体が整うチャンス」でもあります。
バランスを崩すことで、自分の弱点や無理のサインに気づけるからです。
陰陽五行では、自然も人も常に“揺れながら”調和していると考えます。
完全な静でも、完全な動でもなく、陰と陽がゆるやかに入れ替わりながら存在しているのです。
だからこそ、体調が悪い日も「自然の一部」として受け入れてみてください。
そして、少しずつ整えていく。
それが、本当の意味での「自分を大切にする」ということかもしれません。

風邪を悪化させたくない!という方はまずは無料でお試しを!


セルフケアについてもっと知りたいという方に、
上図の5大登録プレゼント「体質改善&美肌作り完全攻略 有料講座教材5点」と
✅美肌&体質改善攻略合計「175枚」スライド
✅24年のノウハウ公開!限定動画3本60分
の計7点をメルマガより無料でプレゼントしています。
20秒で完了の簡単な登録ですので、ぜひ受け取ってみてくださいね!
\ メルマガ登録 /




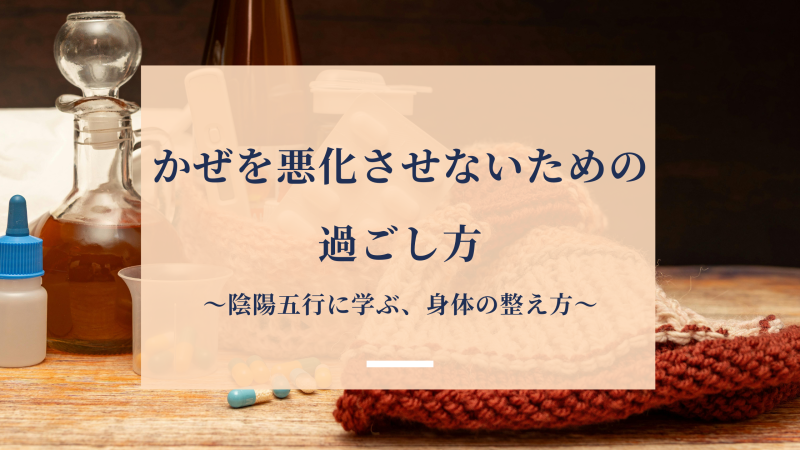


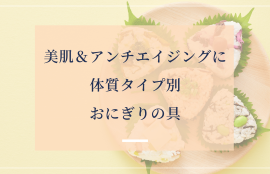
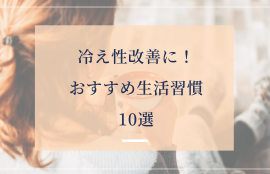
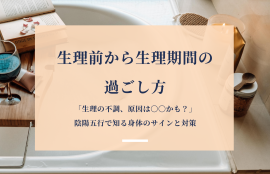
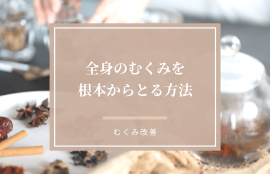
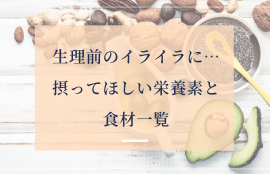
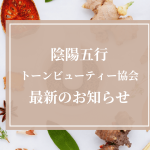

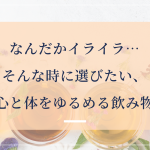

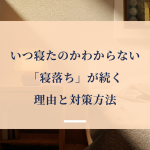
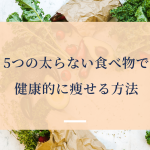
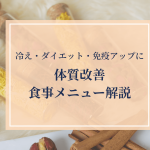
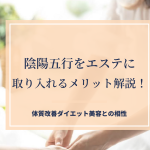
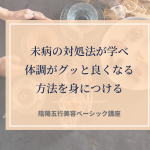
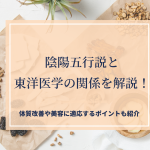
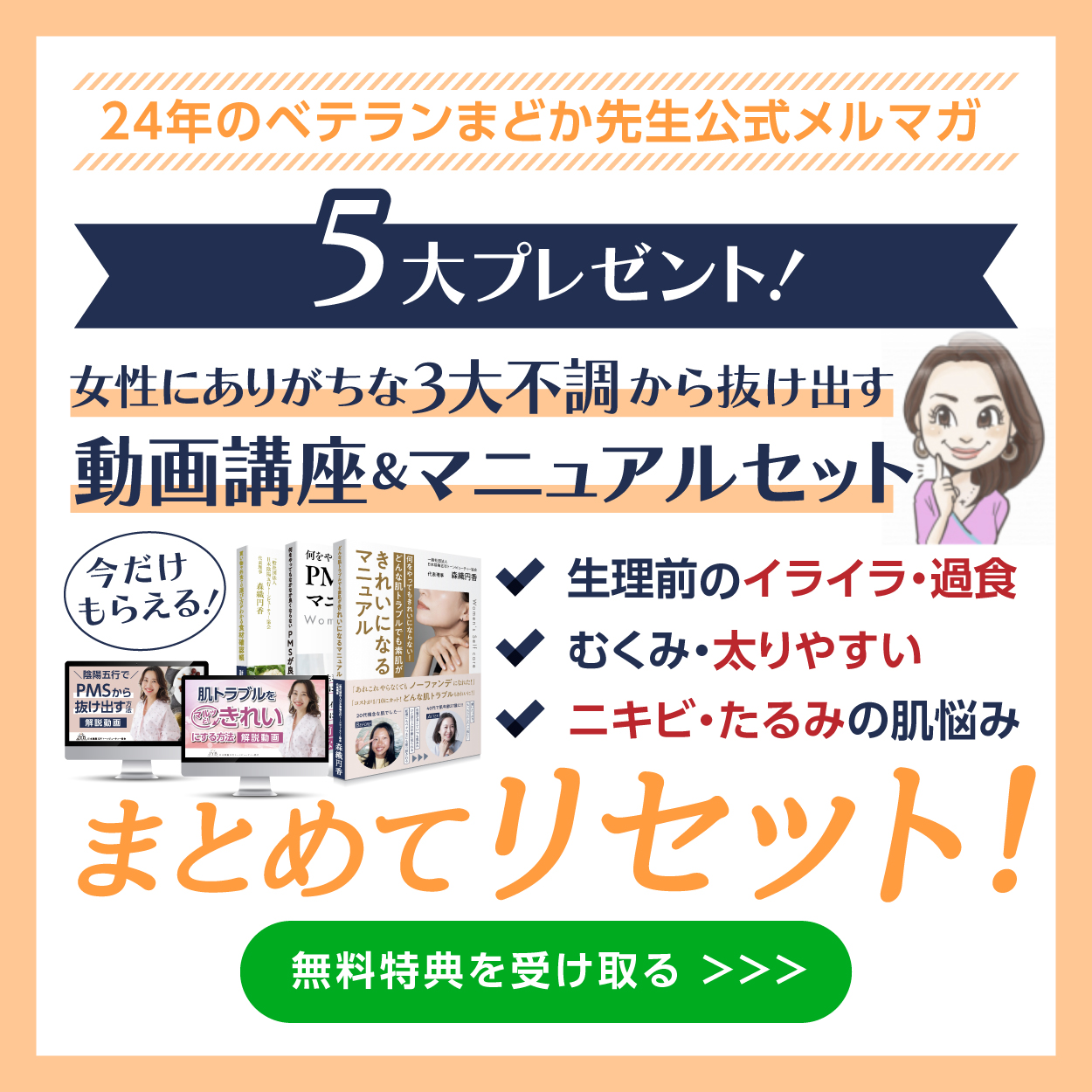
この記事へのコメントはありません。