こんにちは! JYB協会代表理事 森織円香です。
秋の風が肌をひんやりと撫で始めるこの季節。
鏡の前で「なんだか肌がカサついてる…」「いつものケアじゃ物足りないかも」と感じたことはありませんか?
夏の紫外線や湿度の変化が蓄積され、気づかぬうちに肌の潤いバランスが崩れ始めています。
そんな時こそ、内側から整える「食べるスキンケア」の出番です。
今回の記事では、体質に合わせた食材選びや生活習慣の見直しまで、乾燥肌に悩む皆さまへ丁寧にお伝えします。
「何を食べたらいいのかわからない」「このままだと冬がもっと不安…」と感じる方も大丈夫。
あなたの「うるおい肌づくり」をサポートいたします。
秋だからこそ起こる“乾燥肌”の仕組み

なぜ“秋”は肌が乾燥しやすい?乾燥メカニズム

秋になると、気温や湿度が下がります。
空気が乾燥すると、肌表面から内部にある水分が蒸発しやすくなり、肌が「カラッ」とした状態になりがちです。
すると、皮膚の一番上の“壁”のような層(角質層)が水分を保てなくなってきます。
その結果、肌の“水分蒸散”が増えて、水分が保持できずに乾燥が進むのです。
こうして“壁の隙間”ができると、刺激を受けやすくなり、肌がカサついたり、粉をふいたり、ひび割れのような症状が出ることも。
これが、秋に肌が乾燥しやすい理由です。
陰陽五行で読み解く、秋と肌のつながり
陰陽五行では、季節や臓器・味・色・肌などが5つに分類され、それらが相互につながっていると考えます。
陰陽五行で読み解くと、季節ごとに弱りやすい臓器や体表面に出てくる不調、身体を整えるための食材などもわかるのです。
この考え方によると、秋は「潤いが減りやすく」「乾きが入りやすい」季節とされています。
秋に対応する臓器は「肺(はい)」で、乾燥によって働きが弱くなる臓器です。
また、「肺」は「皮膚」とも深くつながっているとされます。
つまり、「外気が乾く」+「肺の働きが十分でなくなる」+「体の中も潤いが減る」=肌が乾燥しやすくなる、という仕組みです。
この視点を持つことで、「ただ保湿をする」だけではなく「内側から」「体質・季節を知って」整える必要性を感じていただけると思います。
“この秋、私の肌は大丈夫?”セルフチェック&危険シグナル
まずは、ご自身の肌・体・生活に秋の乾燥サインが出ていないか、チェックしてみましょう。
以下の項目に「はい」が多いほど、乾燥肌リスクが高めです。
〈チェックリスト〉
- 朝起きたとき、唇やのどが「カサッ」としている。
- 肌がひんやり感じる。
- 手や足、顔の肌表面が、粉をふいたり、ざらつきがある。
- 夜寝る前に手足の末端(指先・かかと)が冷たくなっている。
- 最近、食事のバランスが乱れていたり、急に体重を落とそうとしたりしている。
- 暖房・エアコンを使っている。
もしこの中で 3つ以上当てはまるなら、今こそ「内側の潤い対策」が必要なタイミングです。
この段階で「塗るだけ」ではなく「食べる」「体質から整える」視点を加えることで、より確実に肌の乾燥と向き合えます。
なぜ“秋に整える”ことが、冬の肌を守る鍵なのか
秋は、夏の高湿度・高温から、冬の低温・低湿度へと移行する「過渡期」です。
ここで肌のバリアが弱ったまま放置すると、冬にかけてさらにダメージを受けやすくなります。
角質層のバリアが弱まると、冬には「乾燥+冷え」への反応が出やすくなり、さらなる肌トラブルを日引き起こす危険が。
陰陽五行の視点では、「秋を整える」ことが、次の「冬」にスムーズにつながる準備になります。
つまり、今この「秋のうち」に動くことが、冬の肌トラブルを未然に防ぐ“先手”となるのです。
内側から始める「食べるスキンケア」の基本

潤いをつくる!スキンケアに効く栄養素とは?

肌が自らうるおいを保つためには、体内からの栄養が欠かせません。
以下の栄養素を意識することで、肌の潤い力がぐっと上がる可能性があります。
注目の栄養素と働き
- ビタミンA:肌や粘膜の健康維持に関わる栄養素。不足すると肌の乾燥やかさつきが出やすくなります。
- ビタミンC・E:抗酸化の力を持ち、肌のハリ・ツヤを支えるコラーゲンの生成を助けるとされています。
- オメガ3脂肪酸・必須脂肪酸:肌の“脂質膜”を補い、水分が蒸発するのを減らす働きがあります。
- ミネラル(亜鉛・セレンなど):肌の新陳代謝やダメージ修復に関わり、角質の状態を整える助けとなります。
体質別に分かる!陰陽五行で見る「乾燥肌タイプ」診断
陰陽五行の視点では、「乾燥肌」と一言で言っても原因は人によってさまざま。
まずは自分がどのタイプに当てはまりそうか見てみましょう。
〈潤い不足タイプ〉
- 肌・粘膜・のど・唇が乾きやすい。
- 冷えを感じやすい。
- ドライアイ
- 肌のざらつき、粉ふきがある。
〈エネルギー不足タイプ〉
- 疲れやすい。
- 髪のパサつき。
- 肌にツヤや血色がない。
- 爪が割れやすい。
〈滞りタイプ〉
- 生理痛がある。
- 肌のくすみ。
- 手足末端が冷えやすい。
- むくみやすい。
〈ほてりタイプ〉
- 皮膚がかさつく。
- 顔がほてる。
- 赤みが出やすい。
- 赤ニキビや湿疹がある。
この診断により「自分はどのタイプかな?」という意識を持ちましょう。
そうすることで“おすすめ潤い食材”をより具体的に、自分に合わせて選べるようになります。
毎日の“食べ方習慣”で乾燥肌を回避:朝・昼・夜のポイント
食材を選ぶだけでなく「いつ・どのように・どのくらい」食べるかが、乾燥肌ケアにおいて大きな鍵です。朝昼夜それぞれのポイントを整理します。
〈朝のポイント〉
- 起きてすぐに、ぬるま湯や白湯で身体を温める。
- 朝食にたんぱく質を取り入れる。
- 寝ている間に失われた水分や栄養の回復に意識を。
〈昼のポイント〉
- 魚・ナッツ・緑黄色野菜などを組み合わせて、潤いを支える栄養を補給。
- 空気の乾燥・冷房・室内環境の影響を考えて、「水分+油分」が不足しないように。
〈夜のポイント〉
- 冷えやすい時間帯だからこそ、温かい料理・旬食材を使ったメニューを。
- 食事中は“よく噛む”“ゆっくり味わう”“腹八分目”を意識して消化・めぐりアップ。
- 「焼く・揚げる」より「蒸す・煮る・温かく食べる」を選ぶ。
秋の旬食材&レシピで“潤いチャージ”

陰陽五行理論で選ぶ秋にぴったりの食材

秋に合う食材を選ぶポイントには、以下のようなものがあります。
- 色:白
- 味:辛味・甘味
このポイントを意識することで、秋にぴったりな身体の内側から潤してくれる食材を選びやすくなります。
〈具体的な食材例〉
- 白いもの・・・白キクラゲ、レンコン、梨、山芋 など
- 辛味・・・生姜、ネギ、大根 など
- 甘味・・・さつまいも、栗、かぼちゃ、はちみつ など
体質別おすすめ食材リスト
先ほど、この記事でご自身の体質タイプを確認されましたか。
ここではそれぞれのタイプに合わせたおすすめ食材をご紹介します。
〈潤い不足タイプ〉
- おすすめ食材:白キクラゲ、山芋、梨、蜂蜜、豆乳、鮭、アボカド
- 理由:潤いを補う脂質・保水力・たんぱく質が豊富です。
- 避けたいこと:唐辛子・こしょうなど強い辛味・冷たい飲食、過度なダイエット。
〈エネルギー不足タイプ〉
- おすすめ食材:きのこ、肉、魚、にんじん、小松菜、さつまいも
- 理由:血やエネルギーを補います。
- 避けたいこと:冷たいもの・過剰な甘いもの、汗のかきすぎ・夜更かし・食事を抜く。
〈滞りタイプ〉
- おすすめ食材:くるみ、青魚、ひじき、玉ねぎ、生姜、豆
- 理由:血・水のめぐりを助ける脂質・鉄分・マグネシウム・食物繊維が豊富。
- 避けたい食材:冷たい飲食・甘いスイーツ過多・加工食品・塩分や味付けの濃いもの。
〈ほてりタイプ〉
- おすすめ食材:青野菜(ケール・ほうれん草)、トマト、柑橘類、緑茶
- 理由:体の“熱”を落ち着けつつ、潤いも入れてバランスを取るため。
- 避けたい食材:揚げ物・辛味多用・アルコール・甘味の過剰。
このように体質に応じた「旬の食材選び+避ける食材」を意識することで、食べることが「肌質の整え」に直結するのを実感しやすくなります。
肌の潤いに効く旬の食材ベスト3
ここでは、「肌の潤いやバリア機能」に良いとされる旬の食材を3つご紹介します。
- 鮭・青魚:オメガ3脂肪酸が豊富で、角質層の脂質膜を補い、水分の蒸発を抑える働きが期待されます。
- くるみ・アーモンドなどナッツ類:ビタミンE・良質な脂質が多く、抗酸化作用を通じて肌のダメージをケアします。
- 緑黄色野菜(ほうれん草・ブロッコリー・にんじん・かぼちゃ):ビタミンC・カロテノイド・ポリフェノールが豊富で、肌のハリ・潤いの土台を作ります。
これらの食材を日々の食事に取り入れることで、「肌がなんとなく乾燥してきたな」「粉をふいた」「肌がカサつく」と感じる前に、内側からのケアが始められます。
また、こちらの記事では季節問わずおすすめの「乾燥肌改善食べ物」を紹介しています。
今日からできる!簡単&美味しい“潤いレシピ”3選
ここでは、忙しい毎日でも取り入れやすい「潤いチャージ」レシピを3つご紹介します。
どれも調理にかける時間は短めで、旬を意識しながら“体が喜ぶ”一皿として取り入れやすいです。
ぜひ「今日の一皿」に加えてみてください。
白キクラゲと山芋のスープ
白キクラゲは“肺を潤す”とされ、山芋は保水力・たんぱく補給にも。
〈作り方〉
- 1)白キクラゲ(乾燥タイプ)を戻し、水を切る。
- 2)山芋を薄切りまたは短冊にして、鶏ひき肉少量・生姜を添えて鍋で煮る。
- 3)塩・ごま油を少量加えて味を整える。
鮭とくるみのホットサラダ/さつまいも入り
鮭のオメガ3脂肪酸、くるみのビタミンE、さつまいものβ-カロテンなどが豊富です。
〈作り方〉
- 1)鮭を軽く塩焼きにし、骨を除く。
- 2)さつまいもを蒸すかレンチンで柔らかくし、くるみを刻む。
- 3)ほうれん草(または好みの葉野菜)を加え、オリーブオイル少量+レモン汁で和える。
ネギ・生姜・白ネギ味噌和え&根菜蒸しプレート
白ネギ・生姜が巡りを促し、レンコン・大根・人参など根菜が冬に向けた潤い+温め役を担ってくれます。
〈作り方〉
- 1)白ネギ・生姜を細かく刻み、味噌・蜂蜜少量で和えておく。」
- 2)レンコン・大根・人参を蒸すか軽く茹で、皿に盛る。
- 3)上に味噌和えをのせていただく。
食べるだけじゃない!潤い肌を守る生活習慣

「外的乾燥トリガー」とその対策

肌の乾燥は、内側からだけでなく、外からの影響も大きく受けています。
まずは以下のような“乾燥を招く要因”に気付くことが第一歩です。
主な外的トリガー
- 暖房・エアコンなどによる室内の低湿度。
- 熱めのお風呂
- 強洗浄力のボディソープ
- 頻繁な手洗いによる皮脂膜・角質のダメージ。
- 紫外線・冷風・乾燥風などの気候ストレス。
要因に気づいたら、以下のような対策をしていきましょう。
- 室内湿度を50〜60%程度に保つよう加湿器使用。
- お風呂やシャワーは「ぬるめ&短時間」
- 洗浄料は低刺激タイプを選ぶ。
- 保湿ケアを“外側+内側”で行い、「食べて整える」習慣を併用するとより効果的。
陰陽五行で整える「気血水」のめぐりと冷えケア
陰陽五行では、肌の潤いは「気(エネルギー)」「血(めぐり)」「水(体内の水分・潤い)」のバランスによって支えられています。
秋は特に“乾き”の季節なので、めぐりが悪いと肌にすぐ表れます。
めぐりを整えるためのポイント:
- 5分間のストレッチや軽いウォーキングで「気・血」の巡りを促す。
- 意識してゆっくり深呼吸をし、肺の働きを補う。
- 体を冷やさない食べ方・服装(温かい飲み物・三首を温める・重ね着)を意識する。
1週間実践!“秋の潤い習慣チェックリスト”で自分の肌を育てる
以下は、読者の皆さまが日々実践しやすい「1週間潤い習慣チェックリスト」です。
毎日○×でチェックし、変化を感じながら習慣化していきましょう。
記録しながら意識的に実践することで、1週間後の変化に気づきやすくなります。
体質改善は一度だけでなく、コツコツ継続することで肌が変わってきます。
〈チェック項目〉
- 朝:ぬるま湯・白湯を飲んで身体を温めた。
- 昼:魚・緑黄色野菜などを含むバランスの良い食事をした。
- 夜:温かい料理・根菜・旬の素材を取り入れた。
- 室内湿度を保つために加湿・暖房調整を行った。
- 手足末端(指先・かかと)が冷えないように重ね着をした。
- ぬるめの温度で10分程度の入浴をした。
- 寝る前にスマホ控え・深呼吸・軽ストレッチを実践した。
まとめ:乾燥に“負けない肌”へ


秋の乾燥肌を「食べるスキンケア」で整えるために、大切なのは次の3本柱です。
- 食材を選ぶ:潤いを支えるビタミンA・C・E、オメガ3、ミネラルを含む旬の素材を意識的に。
- 習慣を整える:食べ方・時間・調理法・部屋の環境・巡り(体のめぐり)を整える。
- 体質を知って整える:陰陽五行の視点で自分のタイプを知り、旬の食材・調理法・生活習慣を体質別に合わせる。
この3つを組み合わせることで、「内側からのケア」だけでなく、「外側・生活習慣」もいっしょに整い、乾燥に負けない肌を育てられます。
角質層のバリアが整っていれば、暖房・冷風・空気の乾燥にさらされても強い状態を保ちやすくなります。
また、肌の潤いが整ってくると、見た目だけでなく「触り心地」「温もり」「安心感」「自信」にもつながるでしょう。
体質改善を通じて「肌に優しく、体に心地よい生活」を送ることは、日々の暮らしの質を高めることでもあるのです。
この秋、外からだけでなく、食べる・整える・巡らせる内側ケアを始めて、冬の乾燥に負けない肌を一緒に育てていきましょう。

乾燥肌の悩みを解消したい!という方はまずは無料でお試しを!


食べ物で美肌になりたい!秋の乾燥に負けない肌をつくりたい!という方に、
上図の5大登録プレゼント「体質改善&美肌作り完全攻略 有料講座教材5点」と
✅美肌&体質改善攻略合計「175枚」スライド
✅24年のノウハウ公開!限定動画3本60分
の計7点をメルマガより無料でプレゼントしています。
20秒で完了の簡単な登録ですので、ぜひ受け取ってみてくださいね!
\ メルマガ登録 /




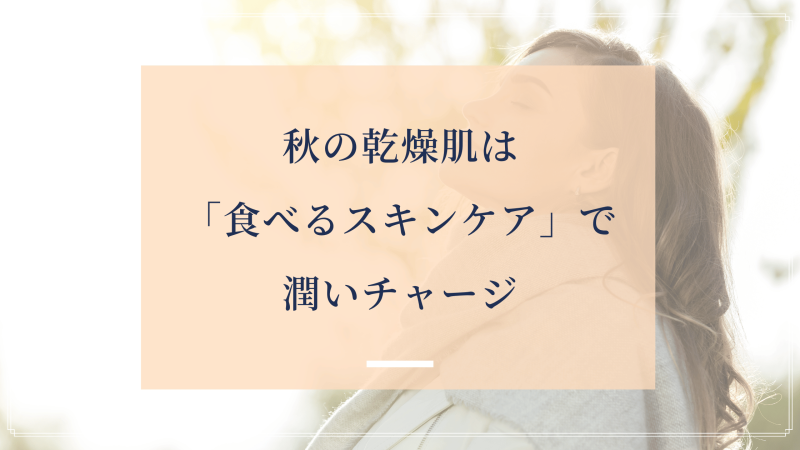

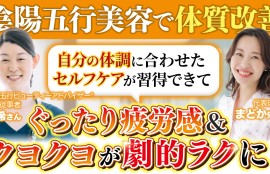
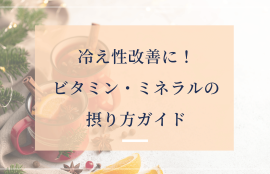
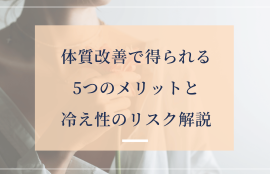
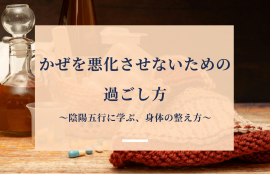
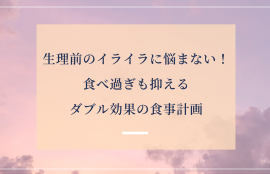
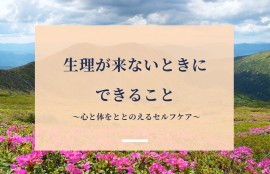
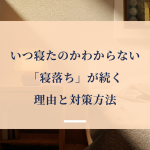
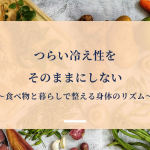
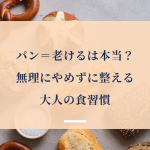
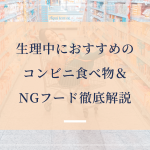
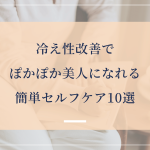
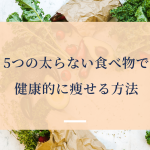
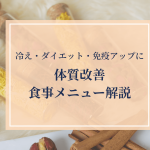
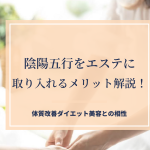
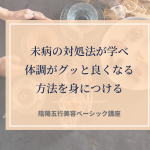
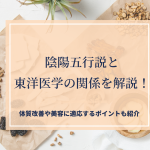

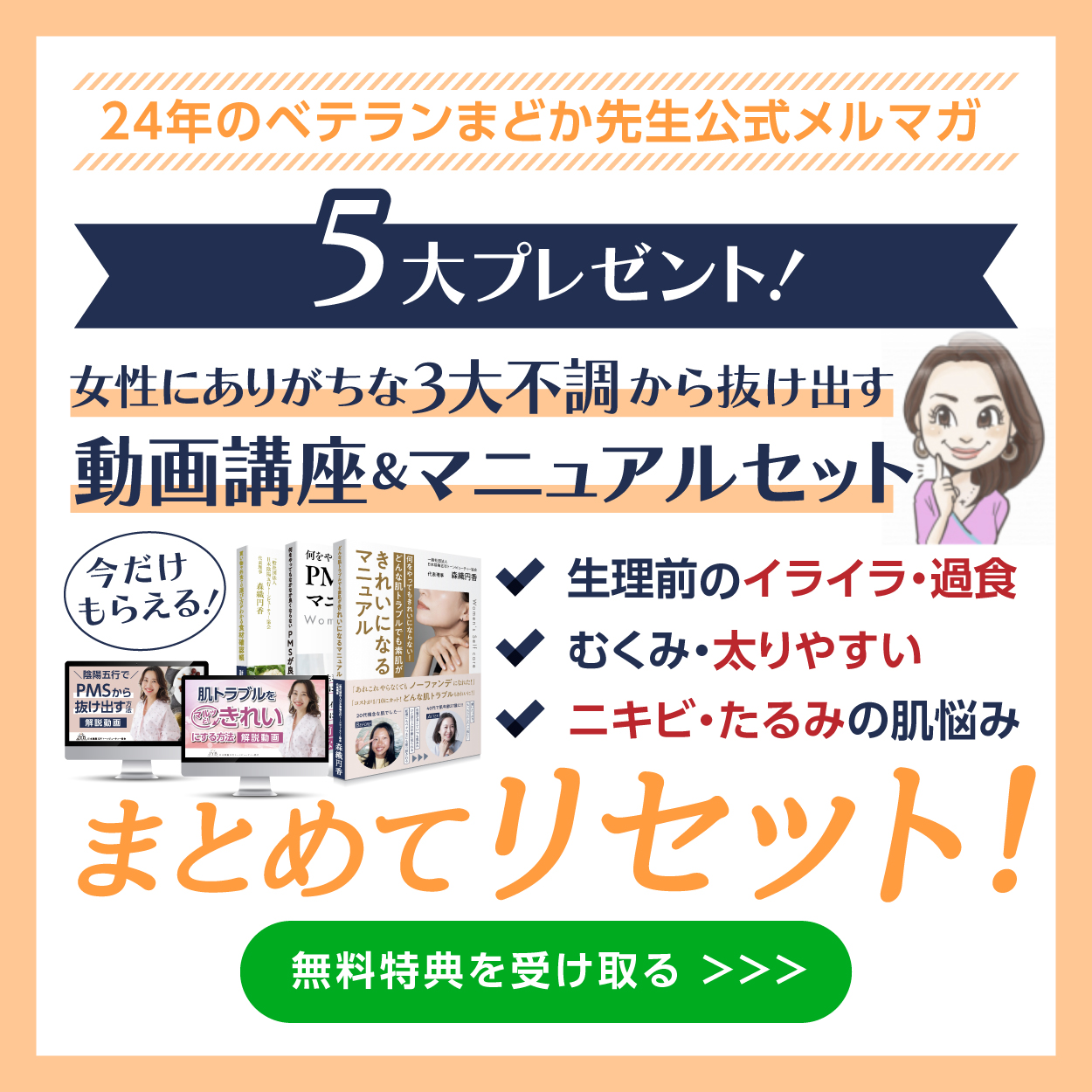
この記事へのコメントはありません。