季節を問わず、なんとなく身体が冷えているように感じる日がありませんか。
「手足がいつも冷たい」「お腹のあたりだけひんやりする」「温かい飲み物を飲んでもすぐ元通り」、そんな小さな違和感を抱えながら、なんとなく過ごしてしまうことは多いものです。
実は、冷えは冬だけの悩みではなく、生活リズムや食事、ストレスなど、さまざまな要因が重なって一年中あらわれることがあります。
気づかないうちに疲れが取れにくくなったり、眠りが浅く感じたりするのも、そのサインのひとつかもしれません。
けれど、身体が温まると、動きやすくなったり、気持ちが軽くなったりと、思いがけない変化を感じることもあります。
だからこそ、日々の食べ物や飲み物の選び方を少し変えるだけで、身体は驚くほどやさしく応えてくれます。
この記事では、忙しい毎日でもすぐに取り入れられる「身体を温める食べ物・飲み物」と「暮らしの工夫」をまとめました。
今日から試せることばかりなので、気になるものから気軽に取り入れてみてください。
冷えやすい人に見られやすいサイン


まずは、あなた自身の「冷えタイプ」を知ることから始めてみましょう。
冷えといっても、人によって感じ方も原因も様々です。
「足先だけが冷える人」「お腹だけが冷える人」「全身が冷たい日がある人」など、
同じ“冷え”でもその出方は大きく違います。
ここでは、冷えやすい人に見られやすいサインをまとめました。
「当てはまるものはあるかな?」と、気軽な気持ちでチェックしてみてください。
- 手足が冷たい
- お腹や腰だけが冷えている
- 風呂上がりでもすぐに身体が冷える
- 疲れが取れにくい
- 朝起きたとき体が固い
- むくみやすい
- 温かい飲み物がすぐ冷えてしまう
- 生理前・生理中に身体が特に冷える
3つ以上当てはまったら、身体が冷えやすくなっている可能性があります。
まずは、冷えを「悪いもの」と捉えず、身体からのメッセージとしてやさしく受け止めましょう。
自分の冷えはどのタイプ?


冷えといっても原因は人によって異なります。
ここではわかりやすく3タイプに分け、それぞれの傾向をお伝えします。
タイプ1|巡りが滞りやすい「巡り不足タイプ」
- 肩こりや頭痛が出やすい
血の巡りがスムーズでないと、首や肩まわりに疲れが溜まりやすく、結果として冷えにつながります。 - 気分が落ち込みやすい
巡りが滞ると、身体だけでなく気分にも影響が出やすく、ため息が増えたり、イライラやモヤモヤが溜まりやすくなるのが特徴です。 - ストレスが溜まると冷える
緊張やストレスが続くと呼吸が浅くなり、身体の巡りがさらに滞って冷えにつながりやすくなります。
ストレスや考えすぎ、忙しさで呼吸が浅い人に多く見られます。
ポイントは「止まっている巡りを動かす」こと。
無理なく少しずつ、動くことを意識してみましょう。
タイプ2|お腹が冷えやすい「内臓冷えタイプ」
- お腹だけが冷たい
手足はそれほど冷たくないのに、お腹だけがひんやりしているタイプ。
内臓が冷えると、エネルギーをうまく巡らせにくくなります。 - 生理中に冷えやすい
ホルモンの変化に敏感で、下腹部の冷えを感じやすい傾向があります。 - 食事が軽くなりがち
食べる量が少なかったり、消化の負担になる冷たい飲み物・サラダが多いと、お腹の冷えにつながりやすくなります。
このタイプは「内側を温める力が弱くなっている冷え」。
食のリズムや、胃腸の働きが影響しやすいのが特徴です。
ポイントは「内側からじんわり温める」こと。
急に温めるよりも、続けられる小さな習慣が大切です。
タイプ3|エネルギー不足の「虚弱タイプ」
- 疲れやすい
体力が不足しやすく、すぐ疲れてしまうことで冷えにつながりやすいタイプです。 - 朝がつらい
朝に身体が温まりにくいと、起きるのがつらかったり、動き始めるまで時間がかかります。 - 食べる量が少ない
食事量が少ないことで、身体の熱をつくるためのエネルギーが不足しがちになります。 - 動くとすぐ息切れする
筋肉量やエネルギーが不足しているため、少しの動きでも疲れやすいのが特徴です。
このタイプは「熱をつくる材料や力が不足している冷え」。
無理なダイエットや食事制限の経験がある人にも見られやすい傾向があります。
ポイントは「身体の土台=エネルギーを満たす」こと。
無理に運動するより、まずは食事と休息で基礎を整えましょう。
身体を温める仕組みを知ろう


身体が温まる方法は、大きく分けて次の3つです。
それぞれを少し詳しく見てみましょう。
熱をつくる(筋肉・食べ物のエネルギー)
身体の中で熱を生み出す主役は筋肉です。
そのため、たんぱく質が不足していると熱が作りにくくなり、冷えやすくなります。
また、食べ物を消化するときにも熱が生まれるため、温かいスープや炊き立てのごはんなど、消化に負担がかからない“温かい食事”は、身体の内側からじんわり熱を生み出しやすくなります。
熱を届ける(血の巡り)
生み出された熱は、血の巡りによって全身に届けられます。
巡りが滞ると、せっかく熱が生まれても手足まで届かず「末端冷え」を感じやすくなります。
そのため、しょうが・ねぎ・シナモンなど“巡りをサポートする食材”を取り入れたり、
ゆっくり湯船に浸かって血の巡りを整えることも大切です。
熱を逃がさない(冷やさない工夫)
冷たい飲み物・薄着・冷えやすい床や椅子で長時間過ごすことは、身体の熱を奪いやすくします。
また、体内の水分バランスが乱れると、体温が一定に保ちにくくなることも。
温かい飲み物を選ぶ、腹巻を使う、首・足首・お腹を冷やさないといった生活の工夫が、
「せっかく温めた熱を逃さない」ための大きなポイントになります。
つまり、“温め食”とは単に「あったかいものを食べる」ではなく、身体本来の温める力をサポートする食べ方のこと。
身体に合った食材を選ぶことで、自然とポカポカしやすい身体づくりにつながっていきます。
食事から冷え知らずになろう


ここからは、身体をやさしく温める食べ物をご紹介します。
どれも普段の食事に取り入れやすいものばかりです。
身体を温める食べ物
土の中で育つ「根菜類」
根菜には大地のエネルギーを蓄える力があり、身体をじんわりと温めるサポートをします。
おすすめの根菜
- にんじん
- ごぼう
- さつまいも
- かぼちゃ
- しょうが
- れんこん
- 大根
煮物・スープ・炒め物など、調理をすることでさらに身体に入りやすくなります。
特に冬は、根菜の甘味が心までほぐしてくれるような優しい味わいになります。
香りの強い「薬味」
薬味には、身体の巡りを整え、温めるサポートをするものが多くあります。
おすすめ薬味
- しょうが
- ねぎ
- にんにく
- 七味唐辛子
- シナモン
- 山椒
味に変化が出るだけでなく、香りが気分転換にもなり、気持ちがすっと軽くなることもあります。
使い方の例
- 味噌汁にしょうがを少し入れる
- 納豆や豆腐にねぎを加える
- ホットミルクにシナモンをひと振り
小さな工夫で身体の温かさが変わっていきます。
色の濃い食材(黒・赤)は身体を内側から温めやすい
陰陽五行の考え方では、「黒」や「赤」の食材は身体の巡りを助け、冷えやすい人をサポートすると言われています。
黒い食材
- 黒ごま
- 黒豆
- ひじき
- のり
- きくらげ
赤い食材
- にんじん
- りんご
- いちご
- 赤パプリカ
これらを食卓に少し加えるだけで、身体を温めるバランスが整いやすくなります。
たんぱく質をしっかりと
筋肉は熱を生み出す大切な器官。
たんぱく質が不足すると、どんなに温かいものを飲んでも冷えやすくなります。
おすすめ食材
- 鶏肉
- 卵
- 魚
- 豆腐
- 納豆
- レンズ豆
特に朝食でたんぱく質を取り入れると、身体の“エンジン”が動きやすくなります。
この記事と一緒に読まれている記事はこちら
これで1日冷え知らず!身体を温める1日のモデルメニュー


「何を食べたらいいか分からない」という方のために、身体を無理なく温めるメニューの一例をご紹介します。
どれも特別な食材は必要なく、普段の食事に取り入れやすい内容です。
朝|一日の“エンジンをかける”温めメニュー
朝は身体の熱が低く、内臓もまだ眠っています。
ここで温かい食事をとることで、巡りが整いはじめます。
例)
- 具だくさん味噌汁(ねぎ・豆腐・わかめ・しょうが)
- 目玉焼きまたはゆで卵(たんぱく質で熱をつくりやすく)
- 温かいごはん
- 白湯またはカモミールティー
ゆっくり噛むことで身体がじんわり温まっていくのを感じられます。
昼|エネルギーを補い、巡りを保つメニュー
昼は、身体のエネルギーが最も必要な時間帯。
冷たい麺類やスイーツに偏ると、夕方の冷えやだるさにつながることがあります。
例)
- 鶏肉と根菜の煮込み(にんじん・ごぼう・れんこん)
- 雑穀ごはん
- ひじきの煮物
- 緑茶(熱いもの)
外食の場合は、「温かい汁物があるメニュー」を選ぶだけでも身体の温まり方が違います。
夜|身体をゆるめて内側から温めるメニュー
夜は、1日の緊張から身体が固まりやすい時間帯。
温かい食事でほっとひと息つけるようにしましょう。
例)
- 野菜と豆腐の鍋(味噌またはしょうがベース)
- かぼちゃの煮物
- 温かいお茶(ルイボス・ほうじ茶・生姜ブレンド)
油や刺激が強いものより「やさしい味」を選ぶと、眠りの質も変わりやすくなります。
身体を温める飲み物


食事で温めるのも大切ですが、じつは“飲み物”はもっと気軽で続けやすい温めケアです。
外出先でも職場でも、カップ一つあればすぐに取り入れられ、忙しい人にとって心強い味方になります。
冷えやすい身体は、水分補給の仕方ひとつでも感じ方が大きく変わることがあります。
普段の何気ない一杯を温かい飲み物に変えるだけで、身体の内側がゆっくりほぐれ、ポカポカ感が長続きしやすくなります。
白湯
白湯は、もっともやさしく身体を温める飲み物です。
特に朝起きて1杯の白湯を飲むと、身体がじんわりと目覚めていくのを感じられます。
ポイント
- 熱すぎない40〜50度程度
- ゆっくり時間をかけて飲む
- 朝起きてすぐが最もおすすめ
白湯は胃腸をやさしく温めるので、冷えて縮こまりやすい朝の身体にぴったりです。
しょうが湯
しょうがは身体を温める代表的な食材。
粉末よりも、生のしょうがをすり下ろして使うほうが温かさが持続しやすくなります。
ハーブティー
ハーブティーは、味だけでなく香りが心の緊張もほぐします。
おすすめハーブティー
- カモミール
- ジンジャーブレンド
- ルイボス
- ローズヒップ
- レモングラス
仕事の合間に1杯飲むだけで、気持ちがふっと落ち着くこともあります。
発酵飲料(甘酒・しょうが甘酒)
甘酒は「飲む点滴」と言われることがありますが、ここでは栄養というより“温め”としておすすめ。
発酵のやさしさが、冷えやすい身体に穏やかに寄り添ってくれます。
食べ方の工夫で冷えない身体を作ろう


身体を温めるために大切なのは、食材選びだけではありません。
同じ食材でも「どう食べるか」で、身体の温まり方は大きく変わるものです。
ちょっとした工夫を意識するだけで、日々の食事が“温めケア”へと変わっていきます。
冷たい飲み物を控える
夏でも氷入りの飲み物は、身体の中心部を急激に冷やしてしまいます。
胃腸が冷えると、全身へ熱を届けにくくなり、結果として手足の冷えにもつながりやすくなります。
外食やコンビニではつい冷たい飲み物を選びがちですが、
- 常温の水
- あたたかい麦茶
- ホットレモン
など、温度を少し変えるだけで身体の負担が軽くなります。
朝いちばんに冷たい飲み物を飲むと、まだ目覚めていない胃腸が驚いてしまうことも。
まずは常温の水や白湯からスタートすると、身体のスイッチがやさしく入ります。
「温かい汁物」を毎食1品
汁物は、身体だけでなく心にもやさしく寄り添ってくれる存在です。
温かい汁物を口にした瞬間、ふっと力が抜けるような安心感が生まれます。
これは、温かいものが胃腸に触れることで副交感神経が働き、身体がリラックスモードに切り替わるためです。
こんなときこそ“汁物習慣”
- 冷えて疲れた日
- 食欲がない日
- なんとなく気持ちがざわつく日
- 身体が固まっていると感じる日
おすすめは、
- 野菜たっぷり味噌汁
- 大根とにんじんの和風スープ
- 玉ねぎのスープ
など、身体を内側からじんわり温めるもの。
特に夜は、汁物をゆっくり飲むことで一日の緊張がほどけ、眠りにもつながりやすくなります。
「食べる」のではなく、「あたたかいものを飲む」という行為そのものが、心と身体を包み込んでくれます。
まとめ


身体を温めることは、気持ちまでやわらかくする小さなセルフケアです。
特別なことをしなくても、毎日の食事や飲み物の選び方、ちょっとした習慣を変えるだけで、身体はゆっくり応えてくれます。
- 根菜類や色の濃い食材を意識する
- 香りのある薬味で巡りを整える
- 温かい飲み物を習慣にする
- 朝食で身体を温める
- 無理なく続ける
どれも大きな変化ではなく、今日から気軽に取り入れられることばかりです。
続けるほどに、身体が軽く感じられたり、冷えによる不快感が和らいだり、気分が整いやすくなる人もいます。
温める習慣は、あなたの生活にそっと寄り添い、心と身体のバランスを整えるサポートになります。
あなたの身体が本来もつ“温める力”をやさしく引き出す食べ方で、無理なく、心地よい毎日を育ててみてください。

冷えに悩みたくない!という方はまずは無料でお試しを!


冷え性に悩まず元気に過ごしたい!という方に、
上図の5大登録プレゼント「体質改善&美肌作り完全攻略 有料講座教材5点」と
✅美肌&体質改善攻略合計「175枚」スライド
✅24年のノウハウ公開!限定動画3本60分
の計7点をメルマガより無料でプレゼントしています。
20秒で完了の簡単な登録ですので、ぜひ受け取ってみてくださいね!
\ メルマガ登録 /




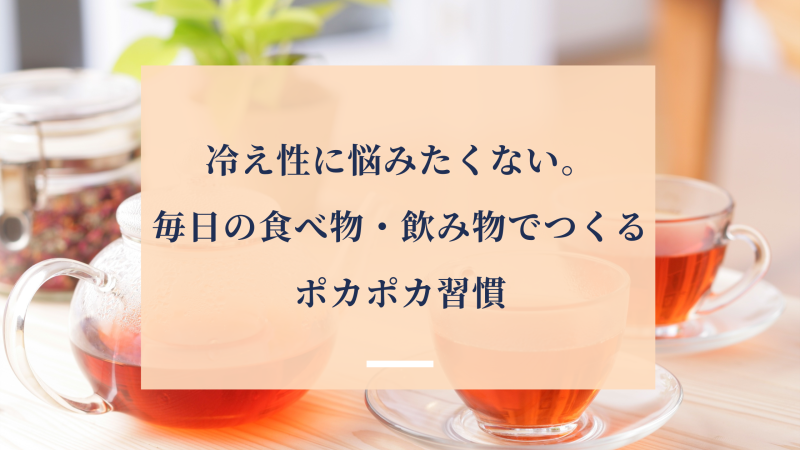

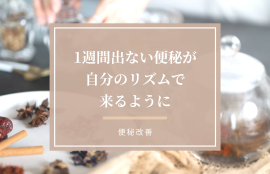
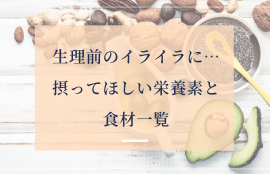
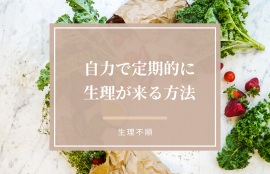
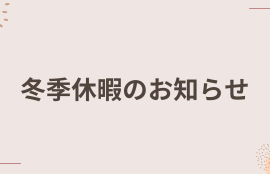
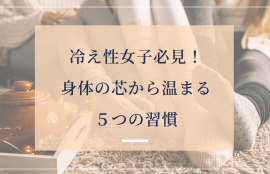
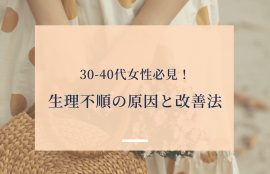
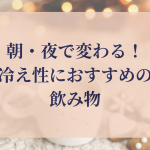
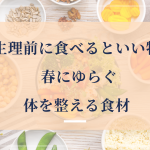

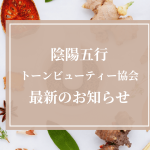

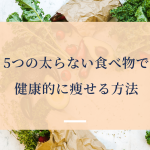
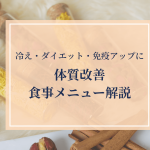
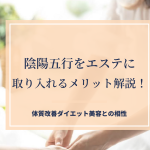
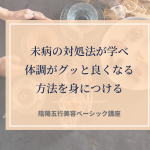
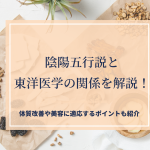

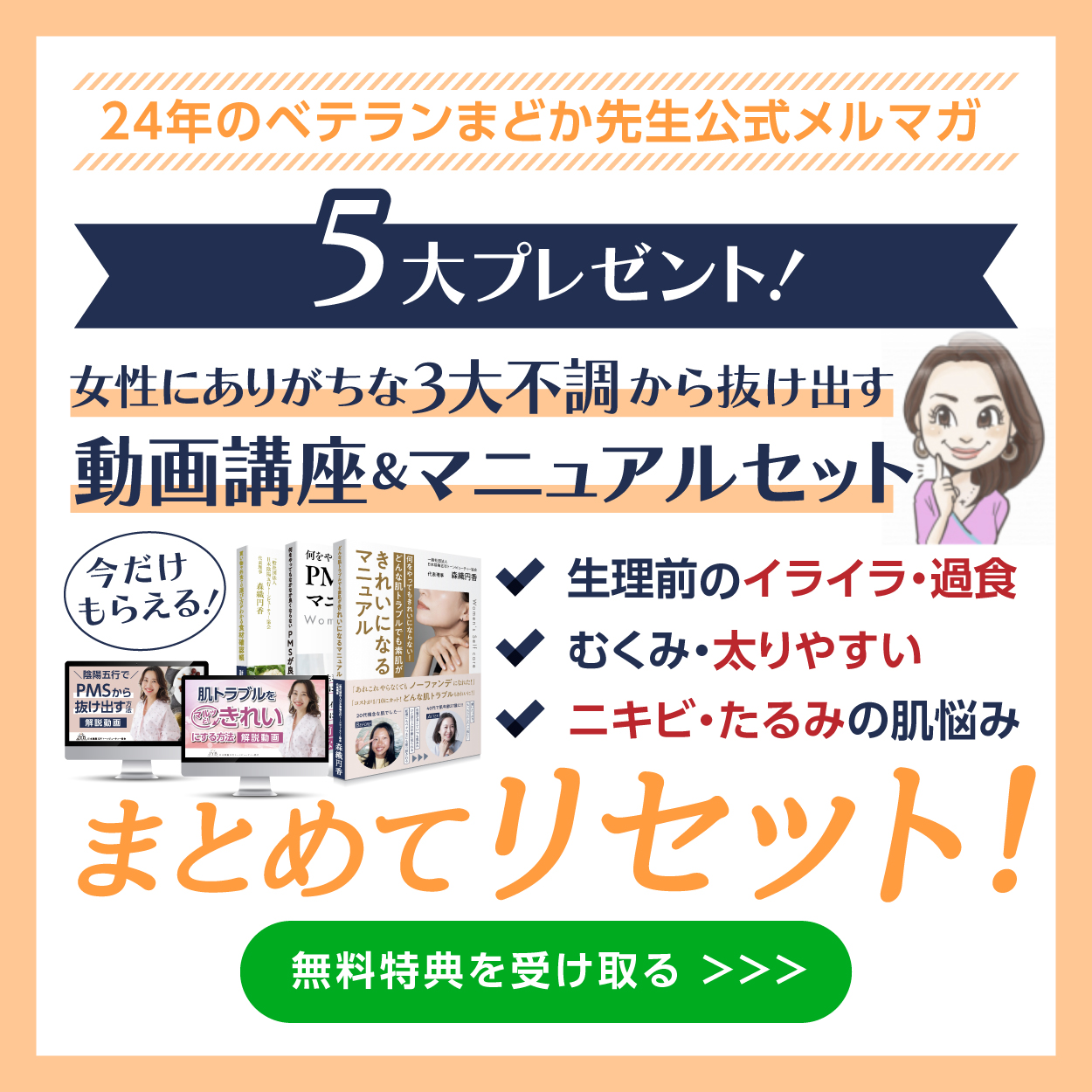
この記事へのコメントはありません。