「気づいたら朝だった」「いつ寝たのか覚えていない」――そんな夜、ありませんか?
ふと目を開けると朝になっていて、昨夜の記憶が途切れている。ちゃんと眠ったのかどうかも分からず、すっきりしない気持ちで一日が始まる。そんな経験をしたことがある人は意外と多いものです。
これは、身体や心が“ちょっとお疲れ”のサイン。
この記事では、「いつ寝たのかわからない」夜に隠れた原因と、今日からできるやさしい整え方をお伝えします。
「いつ寝たのかわからない」って、どんな状態?

限界まで頑張ってしまった体のサイン

夜更かししてスマホを見ながらウトウト……気づけば朝。
そんなとき、脳も身体も“強制的にシャットダウン”している状態かもしれません。
人は極度に疲れていると、睡眠に入る瞬間の記憶がスッと途切れてしまうことがあります。
つまり、「寝た記憶がない=眠る力が尽きるまで頑張っていた」ということ。身体が「もう休んで」とSOSを出していたのです。
浅い眠りのまま朝を迎えている
浅い眠りが続くと、眠っている時間があっても“寝た感覚”が残りません。
夢を多く見る・夜中に何度も目が覚める・朝すっきりしない――これらはすべて浅い睡眠のサイン。
ストレスや不安、生活リズムの乱れで、自律神経がうまく切り替わっていない可能性があります。
「寝た記憶がない」=「休めていない」とは限らない
実は、寝た瞬間を覚えていないのは自然なことでもあります。
深い眠り(ノンレム睡眠)では、脳が記憶の整理を休んでいるため、眠りに入る瞬間を記録していないのです。
問題は、“寝た気がしない”と感じるほど疲労やストレスが積み重なっている場合です。
あなたの眠りをセルフチェックしてみよう


眠りの乱れには、生活習慣や思考の癖が深く関係しています。まずは、今の自分の眠りを客観的に見つめてみましょう。
チェック項目いくつあてはまる?
- 寝る直前までスマホを触っている
- 寝る時間が毎日バラバラ
- 寝る前にコーヒーやお酒を飲む
- 寝ても疲れがとれない
- ストレスで頭の中がぐるぐるする
- 夜の部屋が明るい・音が気になる
3つ以上当てはまったら、眠りのリズムが乱れているサインかもしれません。
次の章で、どんな習慣が眠りを妨げているのか、そしてどう整えていけばよいのかを見ていきましょう。
眠りを乱す習慣と見直しポイント

スマホは“最大の眠りの敵”

ブルーライトは眠りを誘うホルモン「メラトニン」の分泌を抑え、体内時計のリズムを乱します。
寝る30分前にはスマホを手放し、柔らかい照明に切り替えるのが理想です。
どうしても画面を見る必要がある場合は、ナイトモードやブルーライトカット機能を活用して目を守りましょう。
さらに、スマホから流れる情報やSNSの刺激も脳を興奮させる原因に。
ベッドの中でニュースやSNSをチェックすることは、眠りを遠ざける一番の習慣です。
夜は通知をオフにして、アラームをセットしたら“デジタルおやすみ時間”をつくってみてください。
代わりに、紙の本を読む・日記を書く・アロマを焚くなど、心が静まるルーティンを取り入れると自然と眠気が訪れます。
夜の飲み物にも気をつけて
コーヒー・紅茶・緑茶などに含まれるカフェインは覚醒作用があります。
寝る4〜6時間前に摂ると、就寝時まで体内に残ることも。
夜は白湯やハーブティー(カモミール、ルイボスなど)で体を温めてあげましょう。
また、アルコールも一時的に眠気を誘いますが、実は眠りを浅くします。特に就寝前の飲酒は、深い眠りを妨げ、夜中に目が覚めやすくなります。
どうしても飲みたいときは夕食時までに済ませ、就寝の3時間前以降は避けるのがポイントです。
眠りにやさしい飲み物としては、ホットミルク、甘酒(ノンアルコール)、生姜湯などもおすすめです。
温かさが体温を緩やかに上げ、リラックスを促します。
生活リズムを整える
眠る時間と起きる時間が毎日違うと、体内時計が乱れやすくなります。
休日も平日と大きくずれないように意識してみましょう。
朝はカーテンを開けて太陽の光を浴び、夜は少しずつ暗くしていくことで、自然に眠りのスイッチが入ります。
食事のタイミングも“眠りの準備”の一部
眠りやすい体をつくるには、朝と夜の食事リズムも大切です。
朝食で“体内時計リセット”
朝、太陽の光を浴びて、温かいスープや味噌汁をとりましょう。
これが体内時計を整える一番の方法です。朝食を抜くと体が「まだ夜」と勘違いして、夜の寝つきが悪くなることも。
夜は消化のいいメニューで
寝る2〜3時間前には食事を終えるのが理想。
油っこい料理は消化に時間がかかり、睡眠中の内臓の休息を妨げます。野菜たっぷりのスープ、湯豆腐、温野菜などがおすすめです。
「眠りのスイッチ」を入れる3つの工夫

① 寝る1時間前は“ゆるモード”に

照明を少し落とし、静かな時間を過ごしましょう。
温かい飲み物を飲みながら、深呼吸を3回。これだけでも副交感神経が働き始めます。
お風呂は38~40℃のぬるめのお湯で15〜20分。入浴後は自然に体温が下がり、そのタイミングで眠気が訪れます。
② 「寝なきゃ」と焦らない
「早く寝なきゃ」と思うほど、脳が緊張してしまいます。
眠れない夜は“休む練習”のチャンス。ベッドの中で「今、休んでるだけでも大丈夫」とつぶやくだけで、安心感が広がります。
③ 香りや音でリラックス
ラベンダー・ベルガモット・オレンジなどの精油は、心を落ち着ける香りです。
寝室の空気にふんわり香らせるだけでも、リラックスモードに切り替わります。
雨音・波の音・小鳥の声などの自然音もおすすめです。
東洋医学の視点で見る“眠りの乱れ”


東洋医学では、眠りは「気(き)」「血(けつ)」「水(すい)」の巡りが整ってこそスムーズに訪れると考えます。
これらがバランスを崩すと、眠りにもさまざまな影響が現れます。
イライラしたり考えすぎて眠れないタイプ
日中の緊張やストレスが強く、夜になっても頭の中が働き続けている状態です。
東洋医学では、これは「気」が乱れているサイン。呼吸が浅くなり、胸や喉が詰まるような感覚を伴うこともあります。
整え方:
- 深呼吸を意識し、ゆっくり吐く時間を長くとる
- 香り(ラベンダーや柑橘系)でリラックス
- 軽いストレッチや散歩で気を巡らせる
冷えや不安感が強く眠りが浅いタイプ
体が冷えて血の巡りが悪く、疲れているのに眠れない。
顔色が悪い、立ちくらみや貧血気味なども特徴です。これは「血」が不足しているサインとされます。
整え方:
- 栄養を意識した食事(レバー、ほうれん草、黒豆など)
- ぬるめのお風呂や湯たんぽで体を温める
- 就寝前のマッサージで血流を促す
朝だるく、体が重く感じるタイプ
眠っても疲れが抜けない、体が重だるい――これは「水」の巡りが滞っているサイン。
むくみや頭の重さ、天気によって体調が変わる人にも多く見られます。
整え方:
- ぬるめのお風呂で汗をかきやすくする
- 水分をこまめにとり、体内の巡りを促す
- 軽い運動やストレッチで体を動かす
これら3つのタイプはいずれも、「温める」「巡らせる」「休ませる」ことが基本。
自分の体のサインに気づき、日常の中で少しずつ整えることで、無理なく眠りの質が変わっていきます。
今日からできるセルフケア

呼吸で“今”に戻る

ベッドに横になったら、4秒吸って6秒で吐く呼吸を5セット。
呼吸に意識を向けるだけで、思考が静まり、自然と体が重く感じてきます。
夜のノートタイム
頭の中にある“考えごと”を紙に書き出してみましょう。
「今日あったこと」「明日やること」「今の気持ち」など何でもOK。
書くことで思考が整理され、脳が安心して休息モードに入ります。
心地よい寝室づくり
照明はオレンジ系の間接照明を使い、カーテンからの光を抑える。
寝具は季節に合わせて変え、枕の高さを見直すだけでも眠りが深まります。
寝室は“眠るための場所”と体に覚えさせることが大切です。
「眠れない夜」に罪悪感を持たないで


「また寝落ちした」「ちゃんと寝てないかも」と責める必要はありません。
体は必要なタイミングで、ちゃんと休もうとしています。
眠りは努力ではなく、整えるもの。焦らず、自分のペースで整えていけば大丈夫です。
眠れない夜があることも、人間らしさの一部。
そんな夜は、ゆっくりと深呼吸して「今、ここにいる自分」を感じてみましょう。
こちらも記事もぜひ参考にしてみてくださいね。
まとめ:眠りは「整える」ことで深くなる


「いつ寝たのかわからない」夜は、体と心が少し頑張りすぎているサインです。
焦らず、整えることを意識してみましょう。
- 夜のスマホを控える
- ぬるめのお風呂で温まる
- 食事で体をいたわる
- 呼吸でリラックス
小さな習慣を積み重ねるうちに、気づいたら“心地よい眠り”が当たり前になります。
今日も一日、おつかれさまでした。
どうぞ、あたたかい夜をお過ごしください。

睡眠を整えたい!という方はまずは無料でお試しを!


私もよく寝た!睡眠を整えて健康でいたい!という方に、
上図の5大登録プレゼント「体質改善&美肌作り完全攻略 有料講座教材5点」と
✅美肌&体質改善攻略合計「175枚」スライド
✅24年のノウハウ公開!限定動画3本60分
の計7点をメルマガより無料でプレゼントしています。
20秒で完了の簡単な登録ですので、ぜひ受け取ってみてくださいね!
\ メルマガ登録 /




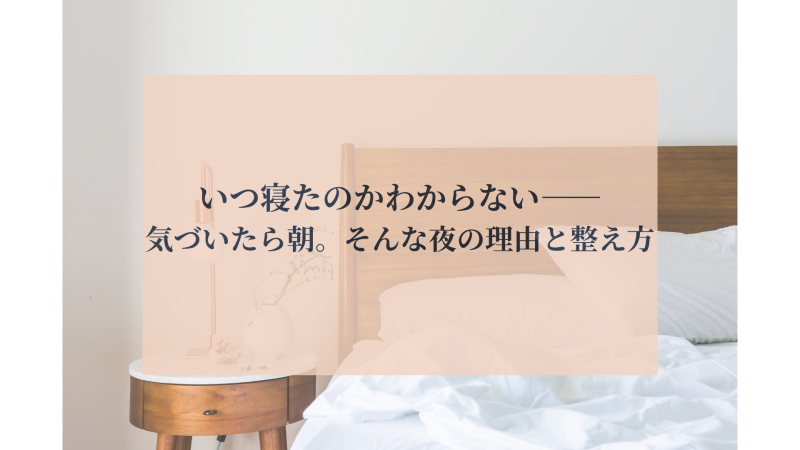

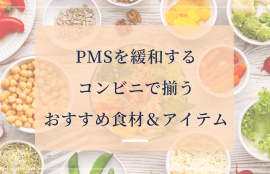
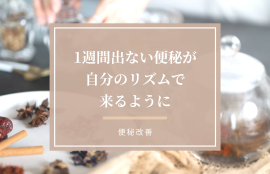


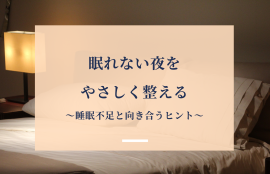
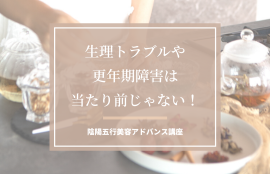
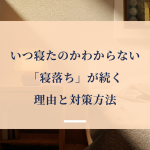
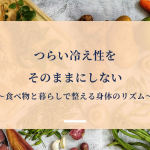
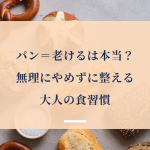
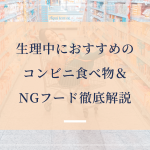
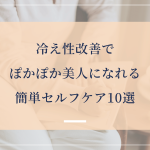
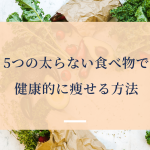
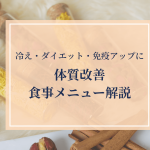
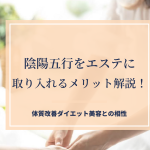
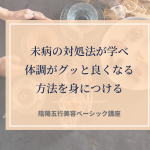
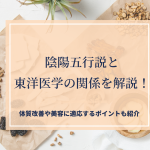
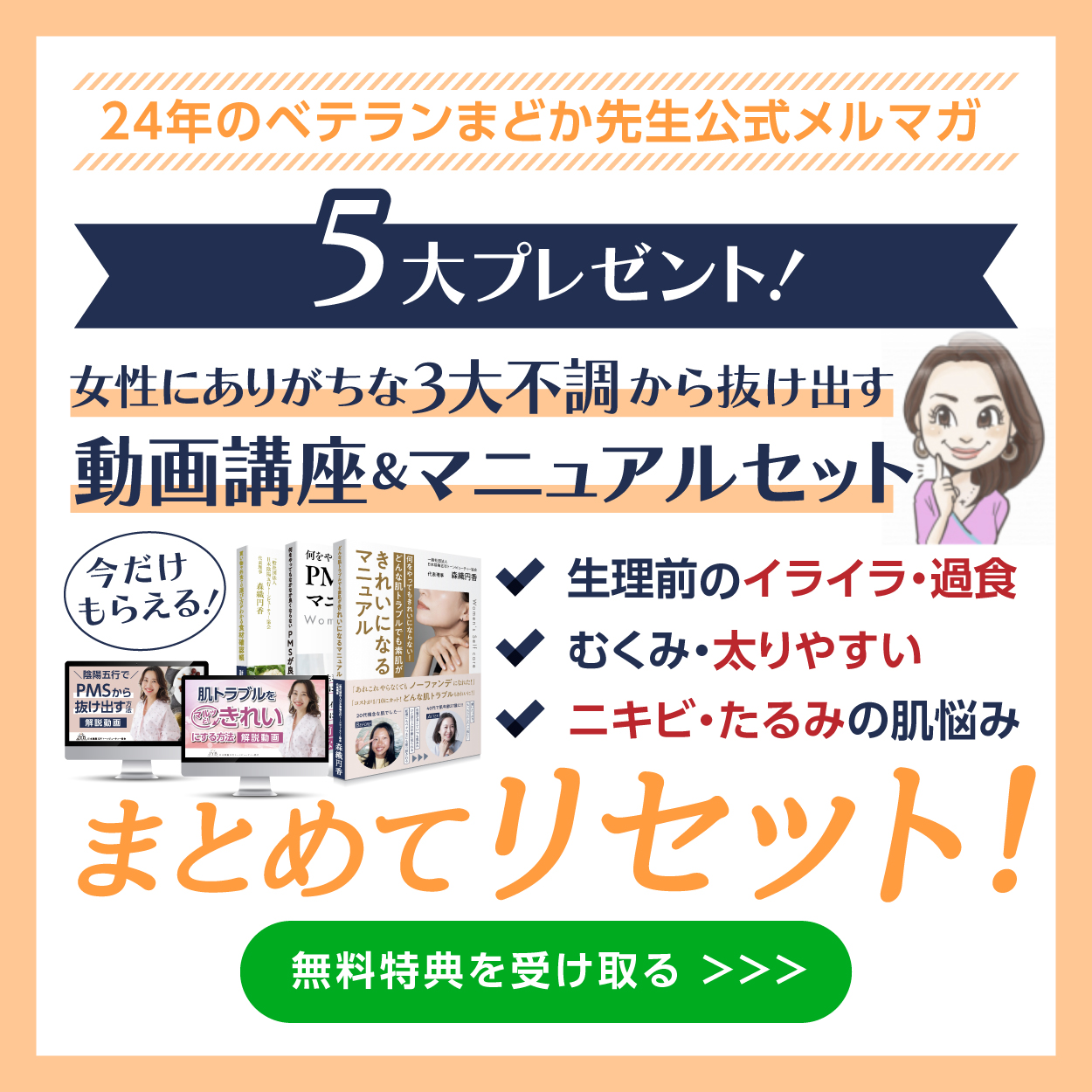
この記事へのコメントはありません。