保湿してもすぐカサつく、粉をふく、季節の変わり目に必ず荒れる――
そんな乾燥肌の悩みは、外から“塗る”ケアだけではなかなか変わらないことがあります。
実は、肌のうるおいは「食べ物」「めぐり」「眠りの質」など、日々の体のバランスが大きく影響しています。
特に東洋医学では、乾燥は“陰”という内側の潤いが不足している状態。表面的な保湿だけでは届かない、体の奥からの乾きに目を向けることが大切です。
本記事では、陰陽五行の視点から、乾燥の背景にある体の偏りをやさしく読み解きながら、「食べ物・飲み物・食べ方」を通じて内側から肌を潤す方法を詳しくご紹介します。
特別な料理や高価な美容食に頼らなくても身近な食材でも大丈夫です。“台所からできるスキンケア”は始められます。
乾燥肌対策はスキンケアだけじゃない。
外から塗り、内から満たす。その両輪で、今日から「うるおい習慣」を育てていきましょう。
なぜ乾燥肌になるのか?

季節や環境による「外的要因」

乾燥肌と聞いてまず思い浮かべるのは、「冬の乾いた空気」ではないでしょうか。
確かに冬は湿度が低く、冷たい風が肌表面の水分を奪いやすいため、乾燥を感じやすい季節です。
しかし、乾燥肌は冬に限った悩みではありません。
夏の冷房による空調の乾燥、春先の花粉、年中降り注ぐ紫外線など、肌にダメージを与える要因は一年中存在します。
肌のバリア機能が乱れることで水分が逃げやすくなり、かさつき・粉ふき・ごわつきなどの不調につながっていきます。
食生活や「巡り」の乱れによる「内的要因」
外側の刺激と同じくらい大切なのが、内側からのバランスです。
乾燥肌は単に空気が乾いているから起こるのではなく、栄養の不足や体内の“めぐり”の悪さが深く関わっています。
たとえば、
- ビタミン(A・B群・C・E)
- 必須脂肪酸(オメガ3など)
- 良質なたんぱく質
これらが不足すると、肌細胞が生まれ変わる力や、水分・油分をとどめる力が落ちてしまいます。
さらに重要なのが「巡り」の状態です。
東洋医学では、体の中を「気・血・水(き・けつ・すい)」がバランスよく流れることが健康の基本とされています。
この巡りが滞ると、栄養や水分がうまく肌まで届かなくなり、肌の潤いを内側から支える力が低下します。
こうした「内側のめぐりの滞り」が、結果的に肌の乾燥・くすみ・ハリ不足として表に現れてくるのです。
陰陽五行から読み解く乾燥肌

- 頬や口元がカサついて粉をふく
- 肌の皮がめくれてファンデがのらない
- 唇や喉が乾き、便秘や空咳も出やすい
- 保湿してもすぐに乾いてしまう…

こんな乾燥トラブルは、スキンケアだけでは根本改善が難しいかもしれません。
陰陽五行では、こうした状態を「陰(=うるおい)不足」ととらえます。肌や粘膜が乾くのは、体の内側で“水”や“油”が足りていないサイン。
特に関わるのが、五行における以下の3つの臓腑です
- 肺(五行:金)… 体表や粘膜にうるおいを届けるバリア機能を担う。弱ると肌・喉・大腸が乾きやすく、秋や空気の乾燥時期にトラブルが増えがち。
- 脾(五行:土)… 飲食物からエネルギーとうるおいをつくり、全身に巡らせる臓腑。消化吸収が弱ると栄養が肌に届かず、乾燥やくすみの原因に。
- 腎(五行:水)… 体の根っことなる臓腑で、深部のうるおいや生命力を司ります。加齢や疲労、睡眠不足が続くと陰(うるおい)が減り、肌が内側から乾き、冷え・だるさ・老化が現れやすくなります。
乾燥肌を根本から整えるには、
「肺にうるおいを補い、脾でつくり、腎でキープする」
という三位一体のアプローチが近道です。
乾燥肌対策におすすめの食材と食べ方


東洋医学の陰陽五行では、乾燥肌を内側から改善するには「肺・脾・腎」のはたらきを整えることが大切です。ここでは、それぞれの臓腑に役立つ食材と、気軽に取り入れられるおすすめの食べ方をご紹介します。
肺(うるおいの通り道)を潤す食材
肺は皮膚・粘膜・大腸とつながっており、乾燥にとても敏感な臓腑。秋〜冬の乾燥対策には「白くてみずみずしい食材」がおすすめです。
おすすめ食材
- 白きくらげ
- れんこん
- かぶ
- 柿
- 梨
- はちみつ
食べ方のヒント
- 白きくらげ×梨のコンポート(デザート感覚で)
- れんこんと人参のきんぴら(唐辛子控えめで)
- はちみつ柿ヨーグルト(朝食や間食に)
肺を潤す食材は、粘膜や肌にうるおいを与え、空咳や乾燥便秘のケアにもつながります。
脾(うるおいを生み出す)を元気にする食材
脾は食べたものを「気・血・水=エネルギーと栄養」に変える土台。冷えすぎ・甘い物の摂りすぎ・早食いなどで弱りやすくなります。
おすすめ食材
- 白米(玄米より消化にやさしい)
- かぼちゃ・さつまいも
- にんじん
- 山芋
- 味噌・納豆などの発酵食品
食べ方のヒント
- にんじん×ツナのしりしり(油と相性◎)
- 山芋と卵のとろろ丼(脾を補って胃腸も軽やかに)
- お味噌汁(根菜+豆腐で腸も潤す)
消化力が落ちていると感じるときは、柔らかく煮る・温かい料理を選ぶのがポイントです。
腎(うるおいを蓄える)をサポートする食材
腎は“生命の貯蔵庫”。加齢・ストレス・睡眠不足などで陰(深部のうるおい)が減ると、肌が乾き、冷え・抜け毛・足腰の弱りなどにもつながります。
おすすめ食材
- 黒ごま・黒豆・黒きくらげ(黒い食材=腎に働きかける)
- 豚肉・うなぎ・牡蠣
- 山芋
- アボカド
- ナッツ類(くるみ・ピーナッツなど)
食べ方のヒント
- 黒ごま坦々風うどん(辛味控えめで)
- 豚肉と白菜のミルフィーユ鍋(潤い・温め効果の組み合わせ)
- ピーナッツ+くるみの手作りエナジーボール(間食に)
腎は「冷え」や「疲れ」にも深く関わるため、体を冷やさず滋養のある食事を心がけましょう。
「飲み方」も大事|内側から潤す飲み物の工夫


食事と同じくらい、日々の「飲み方」も肌の乾燥対策には大切です。ただし、水をたくさん飲めばよいわけではありません。陰陽五行では、「水分=潤い」ではなく、どう巡らせ、どこに届けるかも重要な視点とされます。
水分補給の基本ルール
乾燥肌の方によくあるのが、「水は意識して飲んでいるのに、肌が潤わない」というお悩み。一度にがぶ飲みすると体に吸収されず排出されやすくなり、逆効果です。
ポイントは
- 一度に大量ではなく「こまめに」飲むこと
- 1日1.5〜2L程度を目安に、常温または白湯で
- 冷たい飲み物は「脾」を冷やして潤いづくりを妨げるため控えめに
「冷えは乾燥の親」ともいえるほど密接な関係があるため、温かい飲み物で巡りをよくする意識も大切です。
肌を内側からうるおすおすすめの飲み物
- カモミールティー:緊張を緩め、血流を促す。寝る前にもおすすめ
- ルイボスティー:抗酸化作用があり、アンチエイジング効果も◎
- 野菜スープ・薬膳スープ:栄養と水分を一緒にとれる「食べる保湿」
- 生姜湯:冷えやすい人は特に◎。胃腸をあたため「脾」を守る
日々の飲み物も「温めながら潤す」という視点で見直すことで、肌の乾燥ケアはぐっとラクになります。
こちらも読まれています
陰陽五行で見る|季節ごとの乾燥対策


乾燥肌といえば「冬」のイメージがありますが、実は季節によって乾燥の質や背景が異なります。
東洋医学では、自然界の変化と体の反応は連動していると考えられており、それぞれの季節に合った養生(=体をいたわる方法)を取り入れることが大切です。
以下では、四季に合わせた乾燥対策のポイントを「陰陽五行」の観点からご紹介します。
春|肝と肌のゆらぎに注意
春は五行で「木」に属し、肝(かん)の働きが高まる季節。肝は血を貯蔵し、全身を巡らせる役割を担っているため、春の乾燥は「血不足(血虚)」と関係が深いとされます。
この時期に多い肌トラブル
- 肌のカサつきとともにくすみやクマが目立つ
- イライラや不安で肌荒れする
- 花粉によるバリア機能低下
おすすめの食材
- 小松菜、クコの実、黒ごま(血を補う)
- しじみ、レバー、プルーン(肝を養う)
- 春菊、菜の花(気の巡りを良くする)
春は「気のめぐり」を整えることが、美肌の鍵になります。ストレッチや朝散歩で体をのびのびさせるのも◎。
夏|汗のかきすぎで“隠れ乾燥”に
夏は「火」に属し、心(しん)と関係します。汗をかくことで一見うるおっているように感じますが、実は“体内の陰(潤い)”が消耗しやすい季節です。
この時期に多い肌トラブル
- 汗のあとに急に粉をふく
- インナードライ(肌表面はベタつき、中は乾く)
- 紫外線による水分蒸発・炎症
おすすめの食材
- トマト、きゅうり、スイカ(熱を冷まし水分補給)
- 白きくらげ、はちみつ、梨(肺を潤す)
- 緑豆、豆腐、豆乳(陰を養う)
冷房のあたりすぎ、冷たい飲食物の摂りすぎは、陰を消耗させるため注意。冷たいものをとるなら、温かい汁物とセットに。
秋|本格的な乾燥の始まり
秋は「金」に属し、肺が活発になります。同時に、空気の乾燥が進み、外からも中からも潤いを奪われやすい時期。ここでのケアが冬の肌を左右します。
この時期に多い肌トラブル
- 洗顔後にすぐ突っ張る
- 喉の乾燥や空咳
- 粘膜の乾燥による鼻炎や肌のかゆみ
おすすめの食材
- れんこん、梨、大根(肺を潤す)
- ごま、くるみ、松の実(油分で潤いチャージ)
- はちみつ、生姜、白ネギ(気血をめぐらせる)
乾燥対策の本番。加湿器の活用、早めの保湿ケアも忘れずに。皮膚は肺の鏡なので、肺を守る意識が美肌につながります。
冬|“奥から冷える”乾燥肌に
冬は「水」に属し、腎(じん)と深い関係があります。寒さにより血流や代謝が低下し、肌のターンオーバーも停滞。表面だけでなく、体の芯から乾きやすい季節です。
この時期に多い肌トラブル
- 粉ふき、皮むけが慢性化
- 体の冷えとともに肌がパリパリ
- 夕方のくすみや老け見えが強くなる
おすすめの食材
- 黒豆、黒ごま、海藻類(腎を養う)
- しょうが、ねぎ、にんにく(巡りを良くし温める)
- 豚肉、鶏肉、白きくらげ(潤いとエネルギーの両方を補給)
煮物やスープなど、温かい調理法を中心にして“胃腸から温める”ことが乾燥ケアの鍵です。
まとめ|スキンケアだけに頼らない乾燥対策を


肌の乾燥は、表面的な問題ではなく、体の内側にある「うるおいをつくる力」「めぐらせる力」「保持する力」のバランスの乱れによって起こります。
陰陽五行では、
- 「肺」でうるおいを受け取り、
- 「脾」で気血を生み出し、
- 「腎」で深い潤いを支える
という三位一体の働きが、美しい肌を支えていると考えます。
つまり、乾燥肌の根本ケアは「塗るケア」だけでなく、「食べる・飲む・暮らす」のすべてを見直すことが必要なのです。
今日からできる乾燥対策の一歩
- お米をしっかり食べる
- 潤いを補うれんこん・ごま・豆腐を献立に入れる
- 常温の水やスープで温めながらうるおす
- 季節に応じた食材を取り入れる
- 冷えに気づいたらすぐ温める
日々の食事や飲み物、暮らしの中で「陰」を補い、「巡り」を整えることこそが、うるおい肌への近道です。
肌は内側から育つもの。
台所から、あなたの肌を潤す習慣を始めてみませんか?

乾燥対策もっと知りたい!という方はまずは無料でお試しを!


私も肌を綺麗にしたい!美肌になる食べ物や飲み物についてもっと知りたい!という方に、
上図の5大登録プレゼント「体質改善&美肌作り完全攻略 有料講座教材5点」と
✅美肌&体質改善攻略合計「175枚」スライド
✅24年のノウハウ公開!限定動画3本60分
の計7点をメルマガより無料でプレゼントしています。
20秒で完了の簡単な登録ですので、ぜひ受け取ってみてくださいね!
\ メルマガ登録 /




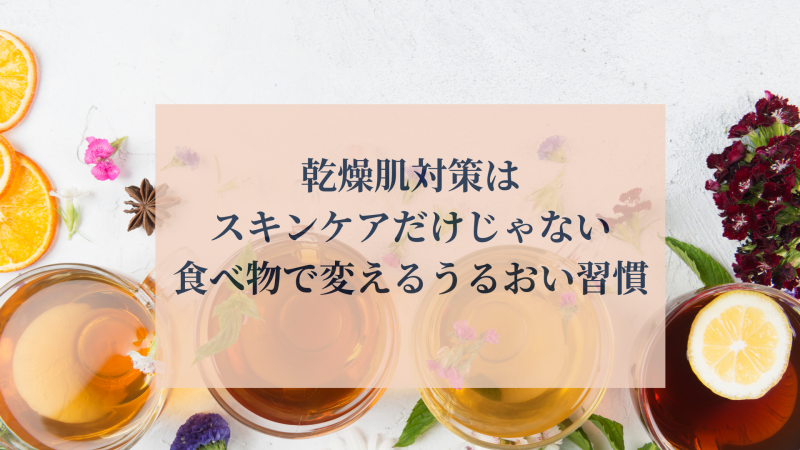

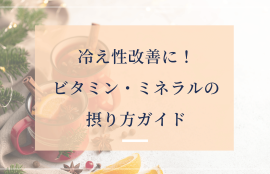
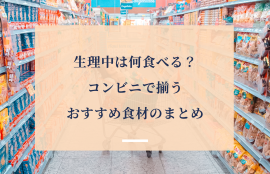
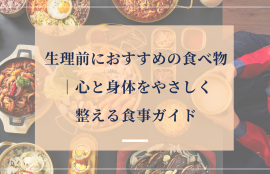
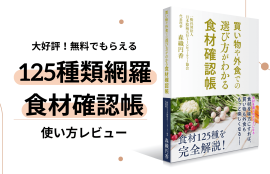
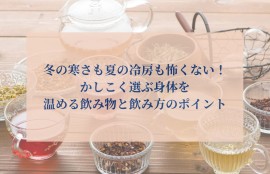
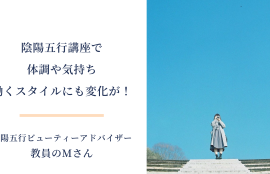
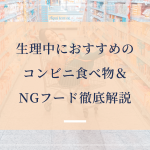
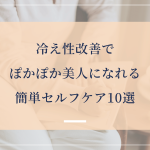
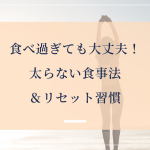
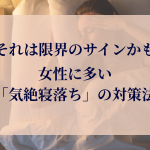
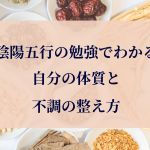
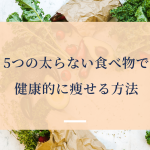
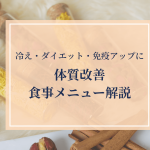
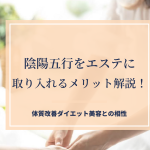
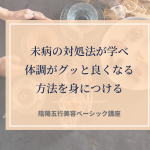
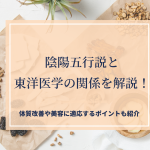
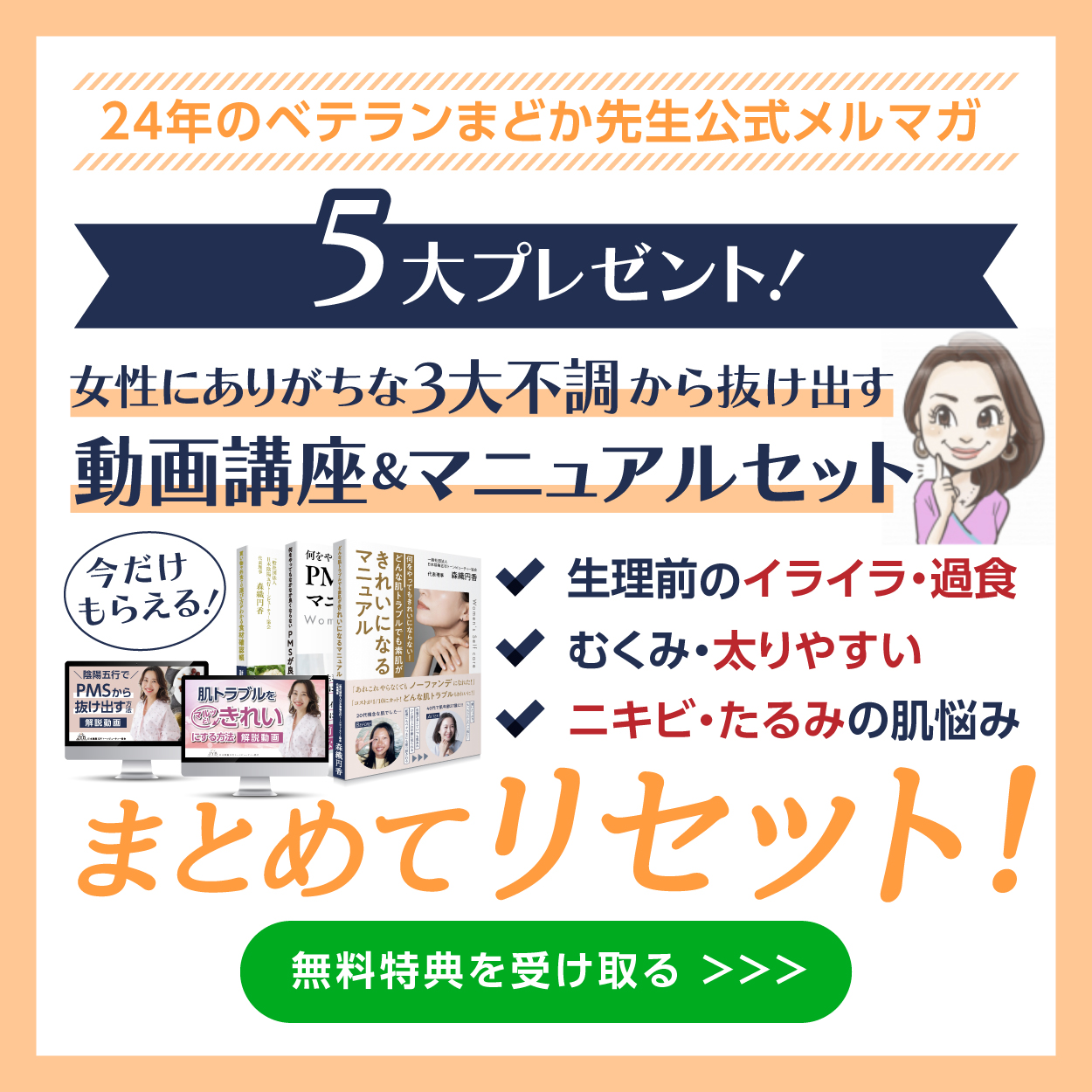
この記事へのコメントはありません。