こんにちは! JYB協会代表理事 森織円香です。
生理前から生理中にかけて、「イライラする」「身体が重い」「頭痛や腰痛がつらい」など、心と身体にさまざまな変化を感じる女性は少なくありません。
西洋医学では女性ホルモン(エストロゲン・プロゲステロン)の変動による影響として説明されますが、東洋医学では「気・血・水(体を巡るエネルギーと栄養)」のバランスが乱れることで症状が出ると考えられています。
食事・ツボ・生活習慣の工夫を知ることで、少しでも快適に過ごせるヒントになれば幸いです。
目次
- 生理前・生理中に起こる身体と心の変化
- ホルモンバランスと症状の関係
- 陰陽五行から見た「気・血・水」の乱れ
- 陰陽五行で読み解く生理周期
- 肝(気の巡り)と生理前のイライラ
- 脾(消化)とむくみ・食欲
- 腎(生命エネルギー)と冷え・腰痛
- 心(心火)と不安・不眠
- 肺(呼吸)と自律神経の安定
- 生理前の過ごし方
- 食事の工夫
- おすすめのツボ押し
- 過ごし方のポイント
- 生理期間中の過ごし方
- 食事で意識したいこと
- やさしいセルフケア
- 睡眠と休養のとり方
- 陰陽五行的おすすめ食材とレシピのヒント
- 季節ごとの生理ケアの違い
- まとめ
生理前・生理中に起こる身体と心の変化

ホルモンバランスと症状の関係
生理前はプロゲステロンの分泌が増え、身体は妊娠に備えて水分をため込みやすくなります。そのため「むくみ」「胸の張り」「体重増加」が起こりやすく、さらに自律神経にも影響を与えるため「イライラ」「気分の落ち込み」「集中力の低下」が出てきます。
生理が始まるとホルモンが急激に減少し、子宮の収縮による「下腹部痛」「腰痛」が強くなることもあります。
陰陽五行から見た「気・血・水」の乱れ
陰陽五行では、体調の変化を以下のように捉えます。
- 気(エネルギーの流れ) 滞るとイライラや便秘に
- 血(血液と栄養)不足すると頭痛・貧血・疲れやすさに
- 水(水分代謝)乱れるとむくみ・頭重感に
つまり、生理前〜生理中は「気が滞り」「血が消耗され」「水が停滞する」という状態になりやすいのです。
陰陽五行で読み解く生理周期


ホルモンバランスと症状の関係
生理前はプロゲステロンの分泌が増え、身体は妊娠に備えて水分をため込みやすくなります。そのため「むくみ」「胸の張り」「体重増加」が起こりやすく、さらに自律神経にも影響を与えるため「イライラ」「気分の落ち込み」「集中力の低下」が出てきます。
生理が始まるとホルモンが急激に減少し、子宮の収縮による「下腹部痛」「腰痛」が強くなることもあります。
陰陽五行から見た「気・血・水」の乱れ
陰陽五行では、体調の変化を以下のように捉えます。
- 気(エネルギーの流れ) 滞るとイライラや便秘に
- 血(血液と栄養)不足すると頭痛・貧血・疲れやすさに
- 水(水分代謝)乱れるとむくみ・頭重感に
つまり、生理前〜生理中は「気が滞り」「血が消耗され」「水が停滞する」という状態になりやすいのです。

生理周期は、単なるホルモンの変化や身体的な現象としてだけでなく、心と体のバランスが映し出される大切なリズムでもあります。
この周期の揺らぎを「陰陽五行」の視点から読み解くことで、自分の体質や不調の原因をより深く理解できると考えます。
肝(気の巡り)と生理前のイライラ
「肝」は身体の中で気の流れをスムーズにする役割を担っています。この流れが滞るとイライラしたり、胸が張って苦しく感じることがあります。
特に生理前はホルモンバランスの影響で気の巡りが乱れやすく、PMSの症状として現れやすい時期です。普段は気にならない小さなことにも敏感になってしまったり、涙もろくなるのも「肝の気」がスムーズに流れていないサインと捉えることができます。
深呼吸やストレッチ、軽い運動などで気の流れを整えてあげると、少しずつ気持ちも落ち着きやすくなります。
脾(消化)とむくみ・食欲
「脾」は食べたものをエネルギーに変え、全身に運ぶ役割を持っています。
ここが弱まると、うまく水分をさばけず、体に余分な水がたまってむくみやだるさを感じやすくなります。また、食べ物を正しく消化できないと、甘いものや脂っこいものが無性に欲しくなったり、ついつい食べすぎてしまうこともあります。
特に生理前は体がエネルギーを欲している時期なので、食欲が普段より増すのは自然なこと。ただし、脾が弱っていると過食や偏食につながりやすくなります。温かいスープや消化の良いものを取り入れると、体も気持ちも落ち着きやすくなります。
腎(生命エネルギー)と冷え・腰痛
「腎」は東洋医学で生命エネルギーの貯蔵庫と考えられています。
生理は血を消耗するため、そのたびに腎のエネルギーも使われやすくなります。腎が弱ると、腰の重だるさや冷えが強まったり、疲れが抜けにくいと感じることがあります。特に下半身の冷えは腎の弱りと関わりが深いため、腰やお腹を温めてあげることが大切です。
腹巻きやカイロで温めたり、温かい飲み物を意識することで、体の芯から安心感を得られます。腎は年齢とともに少しずつ弱まりやすいため、普段から無理をせず、睡眠や休養をしっかりとることも大切です。
心(心火)と不安・不眠
「心」は精神活動を司る臓腑であり、血と深く関係しています。
血が不足すると心が落ち着かなくなり、不安感や緊張感が強まったり、夜眠れなくなるといった不調につながることがあります。生理の前後は血を多く消耗するため、心も不安定になりやすい時期です。眠りが浅く、夢をよく見る、夜中に何度も目が覚めるといった状態も心のサインです。
そんな時は、寝る前にスマホを控えたり、やさしい音楽やアロマを取り入れて心を鎮めてあげるとよいでしょう。血を養う食材(黒豆やナツメなど)を食事に取り入れるのも、心を落ち着けるサポートになります。
肺(呼吸)と自律神経の安定
「肺」は呼吸を通じて新しい気を取り入れ、全身に巡らせる役割を持っています。
呼吸が浅いと、気や血の流れが滞り、身体も心も疲れやすくなります。生理前や生理中は自律神経が乱れやすく、息苦しさや疲労感が出やすいですが、これは肺の働きと深く関係しています。意識的に深くゆっくり呼吸をすることで、自律神経も整いやすくなります。
胸を開くように軽くストレッチをしたり、散歩をしながら空気をたっぷり吸い込むことは、気の流れを助けるだけでなく、気分のリフレッシュにもつながります。
生理前の過ごし方

陰陽五行では、生理前は「気」と「血」の巡りが滞りやすくなる時期とされています。
特に「肝」が関わり、気の流れがスムーズでないとイライラや胸の張り、頭痛などのサインとして現れやすくなります。さらに脾や腎が弱まると、むくみや冷え、疲れやすさも感じやすくなるのが特徴です。
つまり、生理前は自然のエネルギーが内側にこもりやすい「陰」に傾く時期であり、心身のバランスを意識して整えることが大切です。
この時期を穏やかに過ごすためには、「今は巡りがゆらぎやすい時期なんだ」と受け止め、無理をせずやさしく過ごすことが、生理前のセルフケアの大切なポイントです。
食事の工夫
生理前から生理期間にかけては、身体のバランスを意識した食事を心がけると過ごしやすさにつながります。たとえば、イライラや気持ちの張りを和らげたいときには「肝」を整えることが大切。柑橘類のさわやかな香りや、しそや香味野菜を食事に取り入れると、気分もリフレッシュしやすくなります。
また、消化の働きを担う「脾」を守るためには、かぼちゃやさつまいも、もち米など、体を温めてエネルギーを補ってくれる食材がおすすめです。優しい甘みのある根菜類は心も落ち着けてくれるような安心感があります。
さらに、むくみが気になるときには、はと麦や冬瓜、小豆など、余分な水分を調整すると考えられてきた食材を加えるのも良いでしょう。お粥やスープに取り入れると、身体を内側からいたわるような温かさを感じられます。
おすすめのツボ押し
日常に少しだけ取り入れやすいセルフケアとして、ツボ押しも役立ちます。
・太衝(たいしょう) 気の巡りを助けるといわれ、イライラや胸の張りをやわらげたいときに試してみるのも一案です。指で軽く押して、心地よいくらいの刺激を与えるだけで十分です。
・三陰交(さんいんこう) 女性の身体と関わりが深いツボとして知られています。むくみや冷えを感じやすいときにやさしく押すと、じんわりと温かさを感じ、心身ともにほっとすることができるでしょう。お風呂上がりのリラックスタイムに取り入れるとより効果的です。
過ごし方のポイント
日常生活のちょっとした工夫でも身体と心の調子は変わってきます。
例えば、カフェインや甘いものを摂りすぎると体に負担がかかりやすくなることがあるので、控えめに意識してみましょう。代わりにハーブティーや温かい飲み物を楽しむとリラックスにもつながります。
また、気の巡りを整えるには深呼吸や軽いストレッチがとてもおすすめです。難しい運動ではなく、肩を回したり、背伸びをする程度でも十分。呼吸と一緒に身体の中の滞りがほどけていくようなイメージで行うと、心も少しずつ軽くなっていきます。
生理期間中の過ごし方

生理中は「血」が体の外に出ることで、心身のエネルギーが一時的に不足しやすくなる時期です。
陰陽五行では、この時期は「腎」と「心」の働きが深く関わり、血の不足が冷えや腰の重さ、だるさ、さらには気持ちの不安定さへとつながると考えられます。
自然界の流れに例えると、エネルギーが静かに内側に集まる「冬」のような状態であり、無理に活動するよりも静養して整えることが望ましいとされます。
生理期間は「休むこと」に意味があるととらえ、自然に寄り添うように自分を大切に扱うことが、健やかに過ごすための第一歩となります。
食事で意識したいこと
出血で失われる「血」を補う → レバー、ほうれん草、黒ごま
生理中は出血によって体内の「血」が不足しがちなので、レバーやほうれん草、黒ごまなど血を養う食材を意識して摂ると、からだの回復をゆるやかにサポートしてくれます。
温めてめぐりを良くする → 生姜、にら、シナモン
冷えが強いと血流が滞りやすくなるため、生姜やにら、シナモンなど身体を温める食材を取り入れると、体内のめぐりが良くなり、心地よく過ごしやすくなります。
やさしいセルフケア
お腹や腰をカイロで温める
下腹部や腰をやさしく温めることで、冷えからくる不快感を和らげることができます。外出時でも使いやすいカイロを活用して、じんわりとした温かさを味方にしましょう。
アロマ(ラベンダー、クラリセージ)でリラックス
心が落ち着かない時や気分が揺れやすい時は、ラベンダーやクラリセージの香りを取り入れてみましょう。深呼吸と合わせると、気分が少し軽くなるサポートになります。
睡眠と休養のとり方
早寝を心がける
生理前後は体が普段よりも疲れやすいため、できるだけ早めに休む習慣をつけると回復がスムーズになります。夜はスマホを早めに手放すことも眠りやすさにつながります。
昼寝は20分以内でスッキリ
日中どうしても眠気が強いときは、20分以内の短い昼寝を心がけると効果的です。長く眠りすぎないことで、頭も身体もリフレッシュでき、夜の睡眠にも影響しにくくなります。
陰陽五行的おすすめ食材とレシピのヒント

私たちの身体は自然と深くつながっており、季節や環境の変化に影響を受けています。
陰陽五行の考え方では、「木・火・土・金・水」という五つの要素が体や心のバランスを整える鍵になるとされています。
それぞれの要素には対応する臓器や感情、そして体を養うための食材があります。
ここでは陰陽五行をもとにしたおすすめの食材と、日常に取り入れやすいレシピのヒントをご紹介します。食卓から自然のリズムを感じ、体と心を健やかに保ちましょう。
黒豆ごはん(腎を補う)
黒豆は「腎」を補うとされ、生命エネルギーをサポートする食材。ほんのり甘みと香ばしさが加わり、普段のごはんも特別感のある一品になります。
はと麦と小豆のスープ(むくみ対策)
はと麦や小豆は水分代謝を助けるといわれ、むくみや重だるさが気になる時におすすめ。やさしい甘みのあるスープは、体を内側からほっと温めてくれます。
生姜入り味噌汁(冷え改善)
生姜は身体を温める代表的な食材。味噌の発酵の力と組み合わせることで、冷えやすい季節の朝にもぴったりの心強い一杯になります。
梨と白きくらげのデザート(潤い補給)
梨や白きくらげは乾燥に弱い「肺」をサポートするとされる食材。やさしい甘さで食後のデザートにもなり、秋から冬にかけての乾燥対策にぴったりです。
かぼちゃの黒ごま煮(血を養う)
かぼちゃは気力を養い、黒ごまは血を補うと考えられる組み合わせ。ほんのり甘いかぼちゃに黒ごまの香ばしさが加わり、栄養も満足感も得られるおかずになります。
季節ごとの生理ケアの違い

陰陽五行の考え方では、季節ごとに自然界のエネルギーが変化し、それが私たちの体や心にも影響するとされています。
春は「木」、夏は「火」、秋は「金」、冬は「水」と結びつき、それぞれの季節に特有の不調やケアのポイントが表れるのです。特に女性の体は季節の移ろいに敏感で、生理周期の揺らぎもこの自然のリズムと深く関係しています。
つまり季節に応じて生理ケアの工夫をすることは、自然の流れに寄り添い、自分の心身をやさしく整えることにつながるのです。
春 → 肝が乱れやすい、酸味を取り入れる
春は気温や環境の変化で「肝」の働きが乱れやすく、気持ちのアップダウンが強く出る時期です。酸味のある食材(梅干し、いちご、柑橘類)を食事に少し加えると、気の巡りを整えるサポートになります。
夏 → 汗で気血を消耗、梅干しやきゅうりで補う
暑さでたくさん汗をかく夏は、体のエネルギーである「気」と「血」が不足しやすくなります。梅干しやきゅうりなど、水分とミネラルを補える食材を取り入れると、体の内側からしっかり潤いを保ちやすくなります。
秋 → 肺を潤す、梨や白きくらげを食べる
乾燥しやすい秋は「肺」に影響が出やすく、喉や肌の乾燥、生理周期の乱れが気になる人もいます。梨や白きくらげ、はちみつなど潤いを与える食材を日々の食事に取り入れることで、からだをやさしくいたわることができます。
冬 → 腎を守る、黒ごま・黒豆を意識
寒さの厳しい冬は「腎」に負担がかかりやすく、冷えや腰のだるさ、生理痛を感じやすい時期です。黒ごまや黒豆、ひじきなど黒い食材を意識して取り入れると、腎の働きを支え、冷えにくい体づくりに役立ちます。
まとめ

生理前から生理期間の過ごし方は、女性の身体と心の調子を大きく左右します。
つい「生理だから仕方ない」と我慢してしまいがちですが、実はちょっとした工夫や意識の切り替えで、驚くほど快適に過ごすことができるのです。
西洋医学的にはホルモンの変動によって起こる不調も、東洋医学や陰陽五行の視点で見れば「気・血・水の巡りの滞り」「陰と陽のバランスの崩れ」として捉えることができます。つまり、自分の体のリズムに合った過ごし方を選ぶことで自然と整いやすくなるのです。
また、生理前や生理中は「休むこと」も大切なケアの一部です。
現代社会では、どうしても頑張り続けることが美徳とされがちですが、陰陽の流れで言えば「陰」を補う時期にはしっかり休むことが必要不可欠です。無理をしてしまうと、気血の巡りが滞り、次の周期にも影響してしまいます。
そして何より、「自分の体を知り、受け入れること」が最大の養生です。
「こうあるべき」と思い込むのではなく、自分自身の体の声に耳を傾けてあげましょう。
今日は疲れているから早く寝よう、今日は温かいスープを飲もう、今日は深呼吸をして気持ちを落ち着けよう。そんな小さな自己ケアが、長い目で見て女性の健康を守り、人生をより豊かにしてくれます。
つまり、生理前から生理期間の過ごし方は「毎月訪れる体からのリセットタイム」と捉えることもできます。
体調の波を受け入れながら、自分に合ったケアを積み重ねていくことで、PMSの症状が和らぎ、生理そのものが「つらい時間」から「自分を労わる時間」へと変化していくのです。
ぜひ、今回ご紹介した陰陽五行の視点や日々の工夫をヒントに、あなた自身の心と体に合った“心地よい生理ライフ”を見つけてみてください。
 まどか先生日々のちょっとした工夫で不調なく元気に過ごすことができます。さらに詳しい情報を無料公開していますので、良かったら下記から受け取ってくださいね。
まどか先生日々のちょっとした工夫で不調なく元気に過ごすことができます。さらに詳しい情報を無料公開していますので、良かったら下記から受け取ってくださいね。
生理の不調に悩みたくない!という方はまずは無料でお試しを!


生理中は「血」が体の外に出ることで、心身のエネルギーが一時的に不足しやすくなる時期です。
陰陽五行では、この時期は「腎」と「心」の働きが深く関わり、血の不足が冷えや腰の重さ、だるさ、さらには気持ちの不安定さへとつながると考えられます。
自然界の流れに例えると、エネルギーが静かに内側に集まる「冬」のような状態であり、無理に活動するよりも静養して整えることが望ましいとされます。
生理期間は「休むこと」に意味があるととらえ、自然に寄り添うように自分を大切に扱うことが、健やかに過ごすための第一歩となります。
食事で意識したいこと
出血で失われる「血」を補う → レバー、ほうれん草、黒ごま
生理中は出血によって体内の「血」が不足しがちなので、レバーやほうれん草、黒ごまなど血を養う食材を意識して摂ると、からだの回復をゆるやかにサポートしてくれます。
温めてめぐりを良くする → 生姜、にら、シナモン
冷えが強いと血流が滞りやすくなるため、生姜やにら、シナモンなど身体を温める食材を取り入れると、体内のめぐりが良くなり、心地よく過ごしやすくなります。
やさしいセルフケア
お腹や腰をカイロで温める
下腹部や腰をやさしく温めることで、冷えからくる不快感を和らげることができます。外出時でも使いやすいカイロを活用して、じんわりとした温かさを味方にしましょう。
アロマ(ラベンダー、クラリセージ)でリラックス
心が落ち着かない時や気分が揺れやすい時は、ラベンダーやクラリセージの香りを取り入れてみましょう。深呼吸と合わせると、気分が少し軽くなるサポートになります。
睡眠と休養のとり方
早寝を心がける
生理前後は体が普段よりも疲れやすいため、できるだけ早めに休む習慣をつけると回復がスムーズになります。夜はスマホを早めに手放すことも眠りやすさにつながります。
昼寝は20分以内でスッキリ
日中どうしても眠気が強いときは、20分以内の短い昼寝を心がけると効果的です。長く眠りすぎないことで、頭も身体もリフレッシュでき、夜の睡眠にも影響しにくくなります。
陰陽五行的おすすめ食材とレシピのヒント

私たちの身体は自然と深くつながっており、季節や環境の変化に影響を受けています。
陰陽五行の考え方では、「木・火・土・金・水」という五つの要素が体や心のバランスを整える鍵になるとされています。
それぞれの要素には対応する臓器や感情、そして体を養うための食材があります。
ここでは陰陽五行をもとにしたおすすめの食材と、日常に取り入れやすいレシピのヒントをご紹介します。食卓から自然のリズムを感じ、体と心を健やかに保ちましょう。
黒豆ごはん(腎を補う)
黒豆は「腎」を補うとされ、生命エネルギーをサポートする食材。ほんのり甘みと香ばしさが加わり、普段のごはんも特別感のある一品になります。
はと麦と小豆のスープ(むくみ対策)
はと麦や小豆は水分代謝を助けるといわれ、むくみや重だるさが気になる時におすすめ。やさしい甘みのあるスープは、体を内側からほっと温めてくれます。
生姜入り味噌汁(冷え改善)
生姜は身体を温める代表的な食材。味噌の発酵の力と組み合わせることで、冷えやすい季節の朝にもぴったりの心強い一杯になります。
梨と白きくらげのデザート(潤い補給)
梨や白きくらげは乾燥に弱い「肺」をサポートするとされる食材。やさしい甘さで食後のデザートにもなり、秋から冬にかけての乾燥対策にぴったりです。
かぼちゃの黒ごま煮(血を養う)
かぼちゃは気力を養い、黒ごまは血を補うと考えられる組み合わせ。ほんのり甘いかぼちゃに黒ごまの香ばしさが加わり、栄養も満足感も得られるおかずになります。
季節ごとの生理ケアの違い


陰陽五行の考え方では、季節ごとに自然界のエネルギーが変化し、それが私たちの体や心にも影響するとされています。
春は「木」、夏は「火」、秋は「金」、冬は「水」と結びつき、それぞれの季節に特有の不調やケアのポイントが表れるのです。特に女性の体は季節の移ろいに敏感で、生理周期の揺らぎもこの自然のリズムと深く関係しています。
つまり季節に応じて生理ケアの工夫をすることは、自然の流れに寄り添い、自分の心身をやさしく整えることにつながるのです。
春 → 肝が乱れやすい、酸味を取り入れる
春は気温や環境の変化で「肝」の働きが乱れやすく、気持ちのアップダウンが強く出る時期です。酸味のある食材(梅干し、いちご、柑橘類)を食事に少し加えると、気の巡りを整えるサポートになります。
夏 → 汗で気血を消耗、梅干しやきゅうりで補う
暑さでたくさん汗をかく夏は、体のエネルギーである「気」と「血」が不足しやすくなります。梅干しやきゅうりなど、水分とミネラルを補える食材を取り入れると、体の内側からしっかり潤いを保ちやすくなります。
秋 → 肺を潤す、梨や白きくらげを食べる
乾燥しやすい秋は「肺」に影響が出やすく、喉や肌の乾燥、生理周期の乱れが気になる人もいます。梨や白きくらげ、はちみつなど潤いを与える食材を日々の食事に取り入れることで、からだをやさしくいたわることができます。
冬 → 腎を守る、黒ごま・黒豆を意識
寒さの厳しい冬は「腎」に負担がかかりやすく、冷えや腰のだるさ、生理痛を感じやすい時期です。黒ごまや黒豆、ひじきなど黒い食材を意識して取り入れると、腎の働きを支え、冷えにくい体づくりに役立ちます。
まとめ


生理前から生理期間の過ごし方は、女性の身体と心の調子を大きく左右します。
つい「生理だから仕方ない」と我慢してしまいがちですが、実はちょっとした工夫や意識の切り替えで、驚くほど快適に過ごすことができるのです。
西洋医学的にはホルモンの変動によって起こる不調も、東洋医学や陰陽五行の視点で見れば「気・血・水の巡りの滞り」「陰と陽のバランスの崩れ」として捉えることができます。つまり、自分の体のリズムに合った過ごし方を選ぶことで自然と整いやすくなるのです。
また、生理前や生理中は「休むこと」も大切なケアの一部です。
現代社会では、どうしても頑張り続けることが美徳とされがちですが、陰陽の流れで言えば「陰」を補う時期にはしっかり休むことが必要不可欠です。無理をしてしまうと、気血の巡りが滞り、次の周期にも影響してしまいます。
そして何より、「自分の体を知り、受け入れること」が最大の養生です。
「こうあるべき」と思い込むのではなく、自分自身の体の声に耳を傾けてあげましょう。
今日は疲れているから早く寝よう、今日は温かいスープを飲もう、今日は深呼吸をして気持ちを落ち着けよう。そんな小さな自己ケアが、長い目で見て女性の健康を守り、人生をより豊かにしてくれます。
つまり、生理前から生理期間の過ごし方は「毎月訪れる体からのリセットタイム」と捉えることもできます。
体調の波を受け入れながら、自分に合ったケアを積み重ねていくことで、PMSの症状が和らぎ、生理そのものが「つらい時間」から「自分を労わる時間」へと変化していくのです。
ぜひ、今回ご紹介した陰陽五行の視点や日々の工夫をヒントに、あなた自身の心と体に合った“心地よい生理ライフ”を見つけてみてください。


生理の不調なく過ごしたいという方に、
上図の5大登録プレゼント「体質改善&美肌作り完全攻略 有料講座教材5点」と
✅美肌&体質改善攻略合計「175枚」スライド
✅24年のノウハウ公開!限定動画3本60分
の計7点をメルマガより無料でプレゼントしています。
20秒で完了の簡単な登録ですので、ぜひ受け取ってみてくださいね!
\ メルマガ登録 /




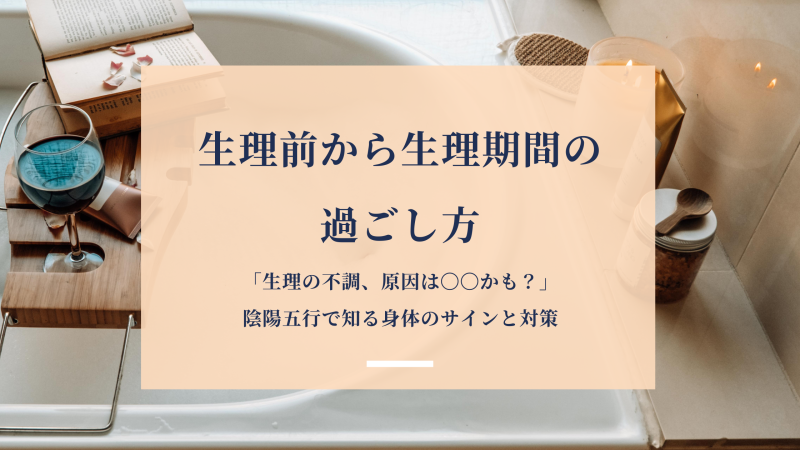

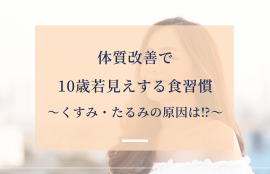
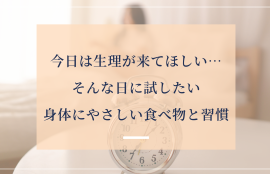
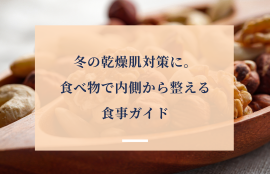
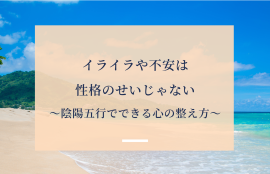
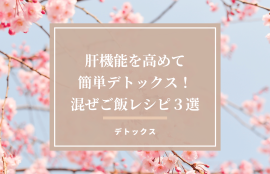
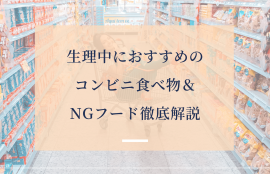
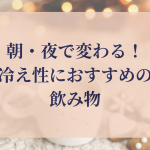
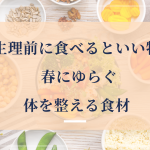

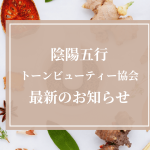

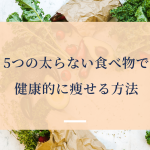
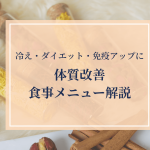
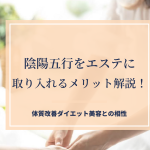
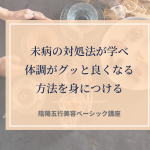
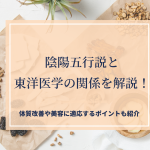

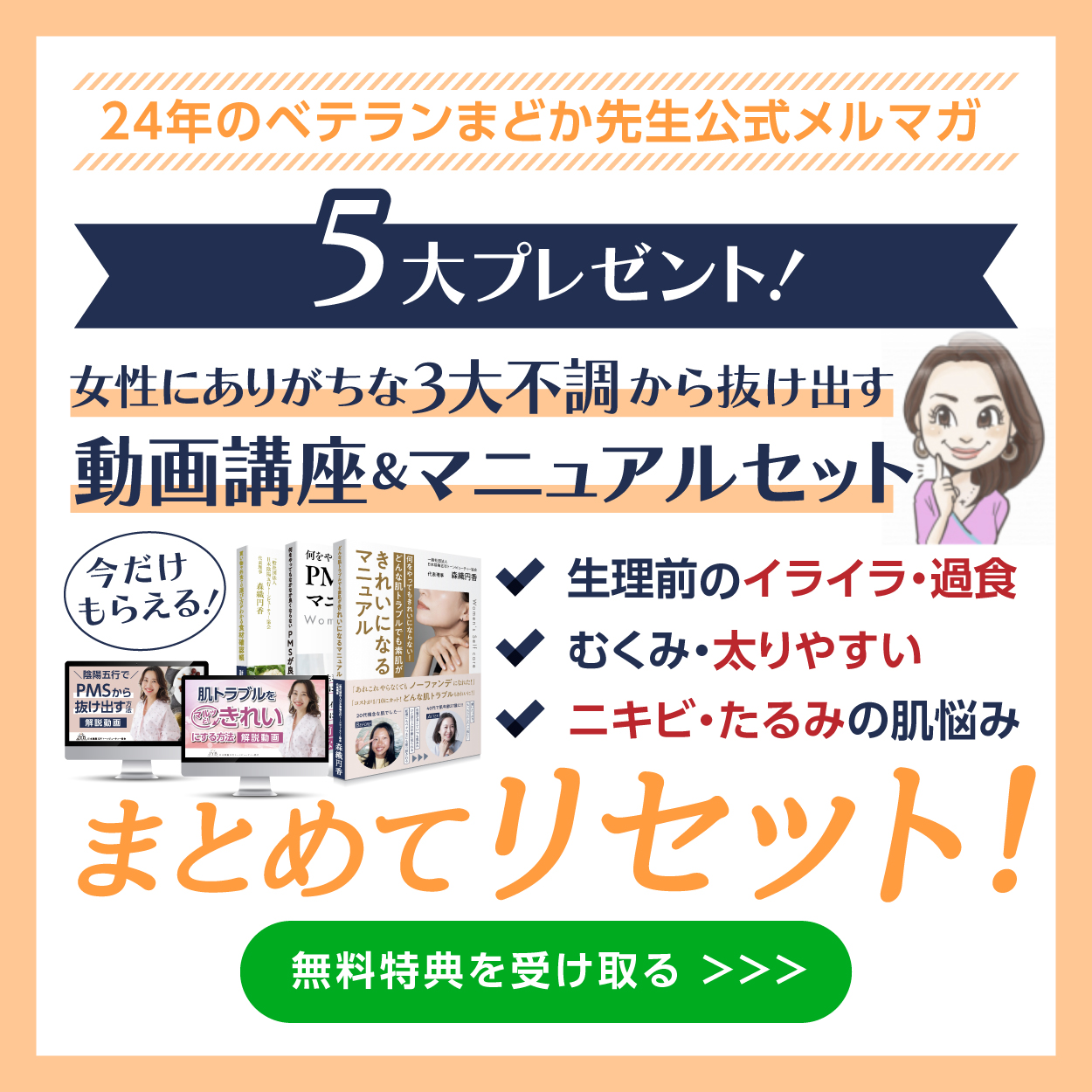
この記事へのコメントはありません。