冷え性改善のために取り入れたい冬の食材5選とそのレシピ
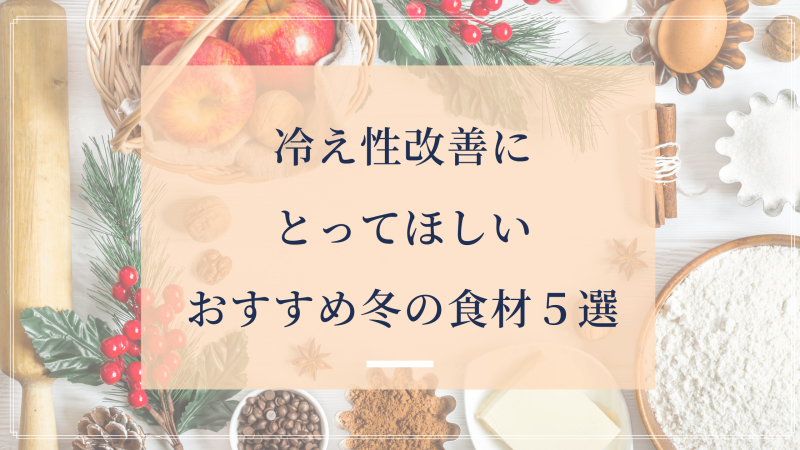
こんにちは! JYB協会代表理事 森織円香です。
寒い季節になると、特に気になるのが冷えの問題ですよね。
カイロや重ね着などで冷え対策をしている方もいらっしゃると思います。
もちろんそのような「外側から」の対策も必要ですが、「内側から」同時にケアできると、気になる冷えが根本から解決しやすくなります。
今回は食べ物で簡単に「内側から」のケアができる、「冬に食べたい温かな食材とレシピ」をお伝えします。
冷え性の基礎知識

冷え性放置の危険性
デスクワークの増加や運動不足、不規則な生活リズムにより、特に女性の約7割が冷えを感じているというデータがあります。
冷えが続くと、血の巡りが悪くなることによる肩こり・頭痛だけでなく、自律神経の乱れや肌荒れなどを引き起こします。
また冷えを放置し続けると、生理痛など婦人科系のトラブルにも繋がってしまうのです。
陰陽五行における「冷え」の考え方
陰陽五行では、体を温める「陽」のエネルギーと冷やす「陰」のエネルギーのバランスが大切です。
前述のように現代女性は生活も食事も乱れによって、「陰」にエネルギーが傾きすぎてしまい、身体を温めにくい身体になり冷え性が起こっています。
ですが、陰陽五行には「食養生」という言葉があります。
これは食べ物の力で、身体のバランスを整えることができるという考え方です。
それでは、冷え性のお悩みを解消する、冬におすすめの食材をご紹介します。
温める食材代表「生姜」

生姜の薬膳効果と栄養成分
生姜には、「ジンゲロール」という成分の体の末端部分の血行をサポートする働きや「ショウガオール」という成分の体の代謝をサポートする作用があります。
また生姜は陰陽五行において、身体を温める「温」の性質を持つ食材として知られています。
しかし、生の生姜と乾燥生姜では体への働きかけが異なります。
生の生姜:発汗を促すことで、体の熱を冷ます作用があります。
乾燥生姜:体を温める作用が強い。
効果的な食べ方
生か乾燥かによって効果の異なる生姜。
生の生姜は、熱を冷ます作用があるので夏バテ予防やかぜをひいて熱が高いときに向いています。
反対に、乾燥生姜は冬の温活に最適です。
冷え性さんは、乾燥タイプの生姜を選びましょう。
生姜パウダーなら、スーパーなどで手に入りやすく、温かいスープや飲み物に手軽に使うことができます。
おすすめレシピ:手作り生姜シロップ
手軽に生姜をとれるシロップを常備しておくと、シロップをお湯で薄めて飲んだり、料理の味付けに使ったりできます。
量が多く感じる方は、それぞれ半分の分量で作るなど、量を調節して作ってみてください。
【材料】
生姜パウダー20g
はちみつ200g
黒砂糖50g
水50mL
- 生姜パウダー 20g
- はちみつ 200g
- 黒砂糖 50g
- 水 50ml
【作り方】
- 鍋に水と黒砂糖を入れ、弱火で溶かす
- 乾燥生姜粉末を加え、かき混ぜる
- 火を止め、はちみつを加えて混ぜ合わせる
- 冷めたら清潔な瓶に移し替える
体を内側から温める「くり」

くりに含まれる栄養素
くりには、体温維持に欠かせないビタミンB1がたっぷり含まれています。
このビタミンB1は、私たちが食べた物をエネルギーに変えるときに重要な役割をします。
さらに、くりには食物繊維もたっぷり。
これが腸内環境を整えてくれるので、エネルギーをつくりだすための栄養をしっかり吸収しやすくなります。
陰陽五行におけるくりの温活効果
くりは、「温」の食材として特に脾胃(消化器系)を整える働きがあるとされています。
胃腸を温めることで冷えの緩和をサポートしてくれます。
また、くりが持つ「エネルギーを補う性質」もポイント。
くりを食べることで効率的に身体を温めるために必要なエネルギーを補給することができます。
おすすめレシピ:くりと小豆の温か甘味
寒くなるとついつい食べたくなる甘いもの。
せっかく食べるなら、身体を温め整えてくれる、身体に優しい甘味はいかがですか。
【材料】
- くり(むき身)
- 200gゆで小豆(砂糖不使用) 100g
- 黒砂糖 50g
- 水 適量
- シナモンパウダー 少々(お好みで)
【作り方】
- くりは皮をむき、一口大に切る(※むき甘栗も可)
- 鍋に茹でた小豆、くり、黒砂糖を入れる
- ひと煮立ちさせたら弱火で15分煮る
- お好みでシナモンパウダーをふりかける
滋養強壮に「山芋」

身体にやさしい山芋
陰陽五行では、食材にはそれぞれ「体を温める」「体を冷やす」などの性質があるとされています。
一方、山芋はどちらにも属さない「平」の性質の食材なので冷え性の方にも使いやすい食材です。
山芋は特に胃腸の調子を整えるのが得意!
胃腸を整えることで消化吸収がスムーズになり、身体を温めるエネルギーをつくりやすくなります。
滋養強壮に適した理由
山芋の中には、体に嬉しい成分がたくさん!
特に「ムチン」という、あのネバネバの正体となる成分が胃腸の粘膜を保護する働きをしてくれます。
さらに、ビタミンB1とB2も豊富に含まれており、糖質の代謝を助けてくれるので、食べ物からエネルギーを作るのに適しています。
おすすめレシピ:山芋の温か養生スープ
このスープは、冷えを感じる日の朝食や、夜遅い食事のときにおすすめ。
山芋のとろみが胃腸を優しく包み込み、体を内側から温めてくれます。
【材料】
- 山芋(すりおろし) 200g
- 鶏ささみ 100g
- 干し椎茸 3個
- 青ねぎ 2本
- 生姜(すりおろし) 小さじ1
- だし汁 600ml
- 塩 適量
【作り方】
- 干し椎茸は水で戻し、薄切りにする
- ささみは細切りにする
- だし汁を温め、ささみと椎茸を入れる
- 火が通ったら山芋のすりおろしを加える
- 最後に青ねぎの小口切りと生姜を加え、塩で味を調える
体を温める発酵食品「味噌」

味噌は体を温める!昔からの知恵
味噌は、体の巡りを良くして、胃腸の働きを助けてくれる、「温」の性質を持つ発酵食品です。
原料の大豆自体がエネルギーを補ったり水巡りをよくしてくれるのに加え、麹菌による発酵過程で、体を温める成分が増えています。
朝ごはんに味噌汁を飲む日本の習慣、実は理にかなった知恵が詰まっているのです。
夜の間に下がった体温を、朝の味噌汁で優しく上げてくれて、一日を元気に過ごす準備を整えてくれます。
発酵の力で栄養価アップ!
発酵すると、大豆に含まれるタンパク質が、体が吸収しやすい形(アミノ酸)に変わります。
発酵で生まれる酵素には、一緒に食べる他の食材の消化も助けてくれる働きがあります。
また、お腹の中で善玉菌のエサになる成分がたくさん含まれているので、味噌は腸活にも効果的です。
おすすめレシピ:具だくさん味噌汁
味噌を摂るならやっぱり味噌汁!
自分の好みや季節に合わせて具材を変えられるのも魅力的なお料理。
今回は、不足しがちな潤い(血と水)を補える根菜の味噌汁のご紹介です。
【材料】(2人分)
- 合わせ味噌 大さじ2
- 大根 100g
- にんじん 50g
- 油揚げ 1枚
- 乾燥わかめ 5g
- 青ねぎ 1本
- だし汁 600ml
【作り方】
- 大根とにんじんは厚さ5mm程度の半月切りにする
- 油揚げは熱湯をくぐらせて油抜きし、細切りにする
- だし汁を温め、根菜類を加えて火が通るまで煮る
- 油揚げとわかめを加え、一煮立ちさせる
- 火を弱め、味噌を溶き入れる
- 最後に青ねぎの小口切りを散らす
アンチエイジングに「黒ごま」

黒ごまは体の中からパワーをくれる!
陰陽五行では、黒ごまは「血液をつくる」「体の潤いを保つ」のを助けてくれる食材と考えます。
そもそも、熱を運ぶための血が不十分だと、せっかく作られた熱を身体中に運ぶことができません。
質のよい血がたっぷりと巡る身体にすることは、冷え性の方にとって必要不可欠です。
また、冬は「腎」という生殖やアンチエイジングに関わる臓腑が、寒さによって弱りやすいと言われています。
黒ごまのように「黒い食材」は、「腎」を元気にしてくれる作用もあるので、まさに冬にぴったりの食材です。
黒ごまの栄養学的特徴
黒ごまには、良質な油脂が豊富!
特にリノール酸やオレイン酸などの必須脂肪酸は、体温を上手にコントロールするのを助ける働きがあります。
さらに、黒ごまにしか含まれない「セサミン」や「セサモリン」という成分も!これらは体の巡りを良くしてくれることが、最新の研究でわかってきています。
黒ごまの皮はかたくて消化吸収しにくいので、すりごまやペーストがおすすめです。
おすすめレシピ:黒ごまペースト
市販の黒ごまペーストもいいですが、手作りすることもできます。
和え物などの料理や、ホットココアに混ぜて飲むのもおいしいですよ。
【材料】
【作り方】
- 黒ごまをフライパンで香ばしい香りがするまで煎る
- 粗熱が取れたら、すり鉢でしっかりとすりつぶす
- はちみつと塩を加えて混ぜ合わせる
- 清潔な瓶に移し、冷蔵庫で保存
まとめ: 継続しやすい冷え対策のポイント

忙しい毎日でも続けられる温活の秘訣は、無理のない取り組み方にあります。
いくつか取り組み例をご紹介します。
自分のライフスタイルに合わせて工夫してみてください。
・作り置きをしておく(今回ご紹介の生姜シロップ、黒ゴマペーストなど)
・野菜は事前に切っておく。
・冷凍できる野菜は、少量ずつ保存袋に入れて冷凍し、必要な時に解凍。
・スープやドリンクを保温ポットに入れて、職場や外出先に持っていく。
また、食事以外でも簡単にできる温活もあります。
食事とあわせて取り組みたい方はこちらもご覧ください。
ご自身のライフスタイルに合わせて、少しずつできることから始めていきましょう。
体を温める食材を日々の食事に取り入れることで、徐々に体の内側から変化を感じられるはずです。
食事で内側から温められる冷え知らずの身体をつくりましょう。
少しずつでも日常の食事に取り入れていくのが、体質改善の一番の近道です。さらに詳しい情報を無料公開していますので、良かったら下記から受け取ってくださいね。
冬の冷え性をなくした!という方はまずは無料でお試しを!

内側から温めたい!冷えの悩みを解消したい!という方に、
上図の5大登録プレゼント「体質改善&美肌作り完全攻略 有料講座教材5点」と
✅美肌&体質改善攻略合計「175枚」スライド
✅24年のノウハウ公開!限定動画3本60分
の計7点をメルマガより無料でプレゼントしています。
20秒で完了の簡単な登録ですので、ぜひ受け取ってみてくださいね!
\ メルマガ登録 /
プレゼント受け取り






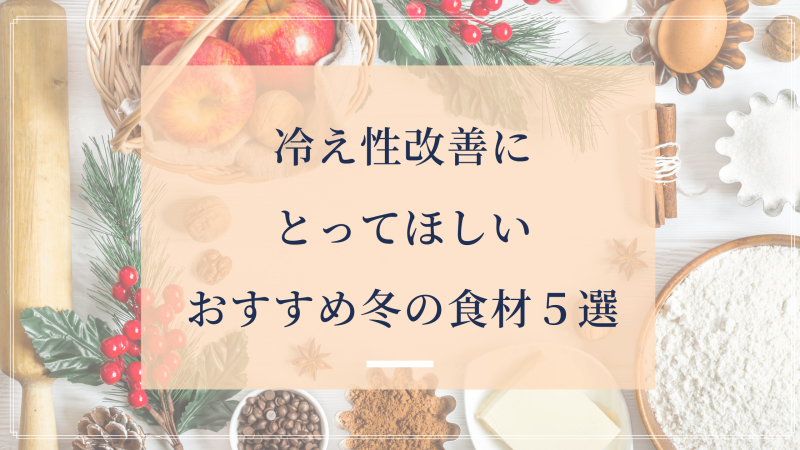
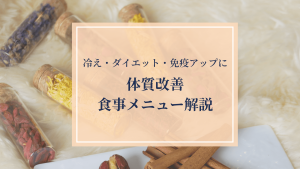









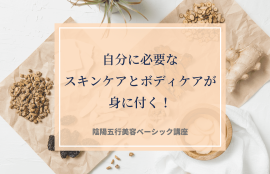
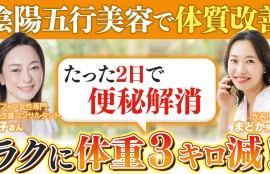
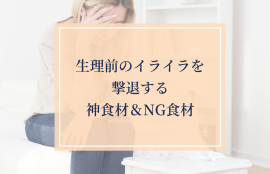
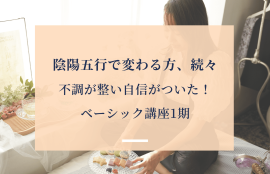
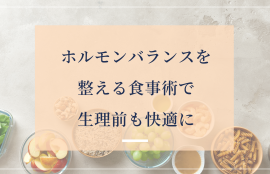
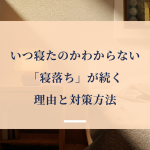
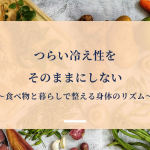
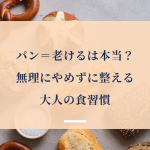
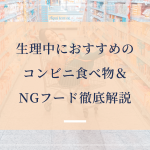
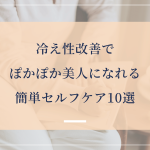
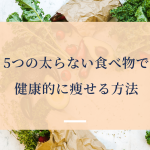
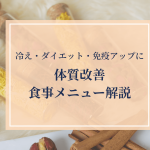
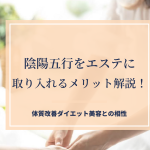
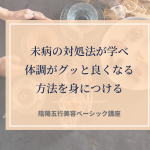
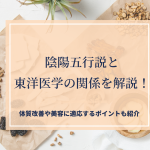

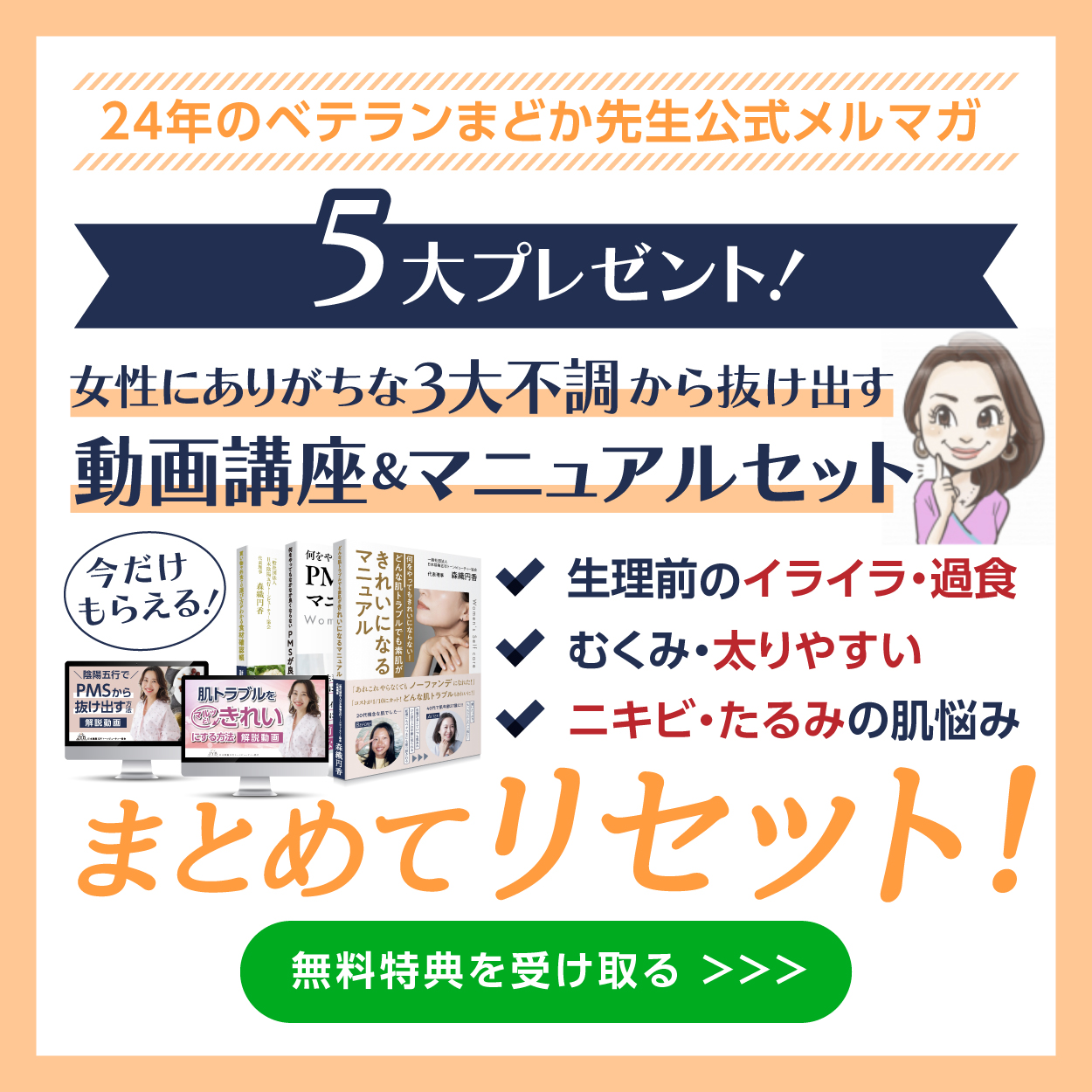
この記事へのコメントはありません。