こんにちは! JYB協会代表理事 森織円香です。
季節を問わず「手足が冷たい」「なかなか温まらない」そんな悩みを抱えていませんか?
冷え性の対策は季節に関係なく必要です。夏場でもエアコンの効いた室内や、朝晩の温度差で冷え性の症状が出ることがあります。そんな冷えの悩みを解決してくれる重要な栄養素「ビタミンE」をご存知でしょうか?
「ビタミンE」には身体を芯から温め、冷えを改善する驚きのパワーが隠されているのです。
今回は私たちの身体に大切な「ビタミンE」と「冷え」の関係について掘り下げていきたいと思います。
冷え性は単なる不快感だけでなく、血行不良による様々な健康問題(肩こり、頭痛、むくみなど)につながる可能性があるため、年間を通じたケアが大切です。
毎日のちょっとした選択で、指先の温もりから内側の輝きまで手に入れる方法をご紹介します。
冷え性の原因と体温の重要性


冷え性が引き起こす不調と症状
冷えの問題は単なる温度感覚の不快さだけでなく、身体の深い部分での不調のサインです。東洋医学では、この状態を「気滞血瘀(きたいけつお)」と考えます。
東洋医学における「気」とは、体内を巡るエネルギーの流れを意味します。生命活動を支える原動力であり、体温調節にも関わります。「血」は栄養を運ぶ血液だけでなく、身体を潤し、滋養する働きを持ちます。
- 気滞(きたい): 「気」の流れが停滞した状態です。気の流れが悪くなると、エネルギーがスムーズに行き渡らず、体内の様々な機能が低下します。
- 血瘀(けつお): 「血」の巡りが悪くなり、滞った状態を指します。血の流れが滞ると、栄養や酸素が体の末端まで届きにくくなります。
気血水についてはこちらで詳しく解説していますので併せてぜひお読みください。
体温1度上昇でもたらされる健康効果
体温が1度上がるだけで免疫力は約30%アップすると言われています。これは、体内の代謝が活性化し自然治癒力が高まるためです。
身体を温めることは私たち女性にとって特に重要で、ホルモンバランスの安定にも深く関わっています。
冷え性の原因は人それぞれ異なります。東洋医学の視点からより詳しく各タイプの特徴をご紹介しましょう。ご自身の症状と照らし合わせてみてください。
エネルギー不足による冷え
気虚(ききょ)タイプ
- 疲れやすく少し動いただけで息切れする
- 汗をかきやすいが、かいた後に冷える
- 声が小さく話すのも疲れる
- 食欲がなく消化不良を起こしやすい
- 午後になると特に疲労感が強まる
- 精神的なストレスで症状が悪化する
- 顔色が青白くつやがない
- 力が入りにくく筋力低下を感じる
対策のポイント: エネルギーを補う食材(薬膳では「補気」する食材)を積極的に。山芋、かぼちゃ、人参などの根菜類、適量の良質なタンパク質が効果的です。休息と睡眠の質も重視しましょう。
血液の質や量の問題による冷え
血虚(けっきょ)タイプ
- 肌が乾燥してかさつきやすい
- 髪にコシがなく抜け毛や白髪が目立つ
- 爪が割れやすく縦筋が入りやすい
- めまいや立ちくらみがある
- 唇や歯茎、まぶたの内側が青白い
- 手足のしびれを感じることがある
- 月経トラブル(生理痛、経血量の異常)がある
- 皮膚の色つやが悪くくすみやすい
対策のポイント: 血を補う食材(「補血」する食材)を中心に。黒豆、黒ごま、レバー、ほうれん草、ビーツなど赤紫色の食材、鉄分豊富な食材がおすすめです。十分な水分摂取も大切です。
身体を温める力の低下による冷え
陽虚(ようきょ)タイプ
- 手足が常に冷たく、特に指先や足先が氷のよう
- 温かい飲み物や食べ物を好み冷たいものが苦手
- 顔色が青白く血色が悪い
- 寒さに極端に弱く夏でも冷房が苦手
- 尿量が多く色が薄い
- お腹や腰回りが冷えやすい
- 朝起きるのがつらく、起床時の体調が特に悪い
- むくみやすく、特に下半身にむくみが出やすい
対策のポイント: 身体を温める食材を積極的に摂りましょう。生姜、ねぎ、にんにく、シナモン、クローブなどの香辛料、黒胡椒、羊肉などが効果的です。温活習慣(半身浴、蒸しタオル、温かい飲み物)も重要です。
エネルギーの流れが滞ることによる冷え
気虚(ききょ)タイプ
- ストレスを感じると冷えが悪化する
- 胸やみぞおちが張った感じがする
- ため息が多く出る
- イライラしやすく、気分の浮き沈みがある
- 生理前に症状が悪化する傾向がある
- 肩こりや首のこりが強い
- 消化不良や便秘と下痢を繰り返す
- 特定の部位だけが冷える(局所的な冷え)
対策のポイント: 気の流れを良くする食材を摂りましょう。
柑橘類、ハーブ類(ローズマリー、バジルなど)適度な運動も効果的です。ストレス管理と深い呼吸法も取り入れましょう。
ビタミンEと冷え性の関係


ビタミンEの基本的な役割と効果
ビタミンEは脂溶性ビタミンの一種で、強い抗酸化作用を持っています。東洋医学では「気血」を整える栄養素と位置づけられ、体内の「陽気」を高める効果が期待できます。
年齢を重ねるとともに減少しやすい栄養素ですので、意識的に摂取することが大切です。
血行促進メカニズムとビタミンEの働き
ビタミンEは血管の柔軟性を保ち、血液の流れをスムーズにする働きがあります。また抗酸化作用により細胞の若々しさを保ち、身体の内側から温かさを支えます。
さらに、ビタミンEは代謝をサポートする役割も担っています。代謝が活発になると体内で熱が生み出され、体温維持に役立ちます。
冷え性改善におけるビタミンEがオススメな理由
ビタミンEの摂取は末梢血管の拡張を促し、血流を改善する効果が確認されています。特に手足の冷えに悩む方には、ビタミンEを含む食品の摂取が推奨されています。
冷え性の方は特に、このような血行促進と代謝活性化の作用を持つビタミンEが不足しがちです。年齢を重ねるとビタミンEの吸収率や体内保有量も減少するため、意識的に摂取することが体温管理には重要なのです。
ビタミンEは単体で働くのではなく、他の栄養素(例えばビタミンC、セレン、オメガ3脂肪酸など)と協力して体内環境を整えます。これは東洋医学の「陰陽バランス」の考え方にも通じるところがあります。
陰陽五行の観点からは、ビタミンEは「陽」のエネルギーを高め「陰」の過剰状態(冷え)を緩和すると考えられます。
ビタミンE豊富な食材とその活用法

植物油で手軽に摂取!ビタミンE源となる油脂類

ビタミンEは油に多く含まれるため、良質な植物油を選ぶことが大切です。特に以下の油がおすすめです
- グレープシードオイル:軽い風味で料理を選ばない
- オリーブオイル:「陽」の性質を持ち、身体を温める効果が期待できる
- アーモンドオイル:肌にも良い万能オイル
これらを日々の調理に取り入れるだけで、効率よくビタミンEを摂取できます。
ナッツ類に含まれるビタミンEとミネラルの相乗効果
アーモンド、ヘーゼルナッツ、ひまわりの種などのナッツ類は、ビタミンEの宝庫です。
しかも亜鉛やマグネシウムといったミネラルも豊富に含まれているため、冷え対策に相乗効果が期待できます。
東洋医学ではナッツ類は「腎」を強化する食材とされ、身体の基礎エネルギーを高めるとされています。
緑黄色野菜から摂るビタミンEと他の栄養素
ほうれん草、モロヘイヤ、かぼちゃなどの緑黄色野菜にはビタミンEだけでなく、身体を温める効果のあるカロテンも含まれています。
五行説では、緑は「木」、黄色は「土」の気を持ち、体内のバランスを整える効果があります。
五行説について詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください
身体を温める食事の基本原則


東洋医学に基づく「温」食材の活用
東洋医学では、食材には「温・熱・涼・寒」の性質があると考えます。
冷え性改善には「温」「熱」性の食材を取り入れることが効果的です。
- 温性食材:生姜、ねぎ、にんにく、くるみ、黒ごま
- 熱性食材:羊肉、唐辛子、シナモン、クローブ
これらの食材を日々の食事に取り入れることで、身体の芯から温まります。
ビタミンEと相性の良い栄養素の組み合わせ
ビタミンEは、他の栄養素と組み合わせることでその効果を高めることができます。
- ビタミンC:抗酸化作用を強化し、血行促進効果を高める。
- オメガ3脂肪酸:血液をサラサラにし、ビタミンEの吸収を助ける。
- セレン:ビタミンEの働きをサポートし、代謝を活性化する。
これらの栄養素を含む食材を組み合わせた食事を心がけましょう。
食べ方・調理法で変わる体温上昇効果
同じ食材でも、調理法によって身体への影響が変わります。
- 温かい食事を中心に:生野菜サラダよりも温野菜や温スープにしましょう。
- よく噛んで食べる:消化酵素の活性化と代謝アップにつながります。
- スパイスを活用:シナモン、ジンジャー、クローブなどで内側から温める。
炒める、煮る、蒸すなど火を使った調理方法が効果的です。
ビタミンEで冷え性改善!毎日の食事プラン


朝食で代謝アップ!ビタミンE摂取の朝食レシピ
朝は身体の「陽気」が高まる時間帯。この時間にビタミンEを摂ることで一日の代謝を高められます。
- かぼちゃと黒ゴマの簡単お粥:レトルトのお粥に冷凍のかぼちゃと黒ゴマをトッピング、醤油を少しかけて完成
- アボカドトースト:オリーブオイルとアボカドで良質な油を摂取できます
- 温スムージー:バナナ、アーモンド、生姜を温かい豆乳でブレンドして
ランチタイムの効果的なビタミンE補給法
昼は活動のピーク時。エネルギーとなる食事を心がけましょう。
- 玄米と温野菜のボウル:かぼちゃ、ほうれん草、アーモンドスライスをトッピング
- ブロッコリーとナッツのビタミンEサラダ:茹でたブロッコリーにナッツ、オリーブオイルドレッシングをかけて
- 生姜入り根菜スープと全粒粉パン:身体を内側から温める組み合わせで冷え性対策
夕食で身体を芯から温める食事提案
夜は「陰」が強まる時間。しっかり身体を温める食事を。
- スパイス香る根菜シチュー:ターメリック、クミン、シナモンで風味づけ
- サーモンのオリーブオイル焼き:オメガ3脂肪酸とビタミンEの相乗効果
- ごま油で炒めた野菜と豆腐の炒め物:良質なタンパク質と油を一緒に
効果を高める!ビタミンEと冷え対策の生活習慣


食事のタイミングとビタミンE吸収率の関係
ビタミンEは脂溶性ビタミンなので、少量の油と一緒に摂ることで吸収率が高まります。
また陰陽五行の考えでは朝は「陽」が上昇する時間なので、この時間帯の摂取が特に効果的です。夜21時以降の食事は避け、身体の回復に集中させましょう。
効果的な運動とビタミンEの関連性
適度な運動は血行を促進し、ビタミンEの働きを助けます。特におすすめなのは
- ヨガ:「気」の流れを整え、血行促進
- 太極拳:緩やかな動きで内側から温まる
- ウォーキング:20分程度の軽い運動でもOK
運動後に温かい飲み物と一緒にナッツ類を摂ると、より効果的です。
入浴・半身浴でビタミンEの効果を高める方法
入浴は血行促進の強い味方です。38〜40℃のお湯に20分程度浸かり、血行を促進しましょう。生姜やシナモンのバスソルトを加えるとより効果的。
入浴前にビタミンEを含む食品を摂ることで栄養素の巡りも良くなります。
ビタミンEを補う簡単レシピ集


温活グリーンスムージー
朝のスムージーで手軽にビタミンE補給
【材料】
- ほうれん草
- バナナ
- アーモンドミルク
- アーモンドバター小さじ1
- すりおろし生姜少々
【作り方】
- すべての材料をブレンダーで混ぜ、軽く温める
アボカドディップと野菜スティック
ランチに取り入れたいビタミンEレシピ
【材料】
- アボカド:1個
- レモン汁:小さじ1
- 塩:少々
- にんじん、きゅうり、パプリカ:適量(スティック状に切る)
【作り方】
種と皮を取ったアボカドをフォークでつぶしレモン汁と塩を加えて混ぜるだけ。野菜スティックにつけて食べる
生姜とナッツの温芯スープ
夜の温活にオススメな体温上昇レシピ
【材料】
- 根菜類(人参、ごぼう、玉ねぎ)
- 生姜
- くるみ
- オリーブオイル
- 香辛料(クローブ、シナモン)
【作り方】
- 根菜と生姜をオリーブオイルで炒め、水を加えて煮込み、最後にくるみと香辛料を加える
ビタミンEを味方につけた冷え性改善の総合アプローチ


冷え性改善は単に身体を温めるだけでなく、体内のバランスを整えることが大切です。
ビタミンEはその強力な抗酸化作用と血行促進効果で、私たちの身体を内側から支えてくれます。
陰陽五行の考えと現代の栄養の知識を組み合わせることで、より効果的なアプローチが可能になります。
「陽」のエネルギーを高め「気血」の流れを良くするビタミンEを意識的に摂取しながら、食事・運動・入浴のバランスを整えていきましょう。
皆さんも今日からできることから始めて、温かな身体と心を手に入れてください。健やかで美しい毎日のために、ビタミンEのパワーを味方につけましょう!

冷え性対策を始めたい!という方はまずは無料でお試しを!


私も自分の体質を理解して冷え性を手放したい!という方に、
上図の5大登録プレゼント「体質改善&美肌作り完全攻略 有料講座教材5点」と
✅美肌&体質改善攻略合計「175枚」スライド
✅24年のノウハウ公開!限定動画3本60分
の計7点をメルマガより無料でプレゼントしています。
20秒で完了の簡単な登録ですので、ぜひ受け取ってみてくださいね!
\ メルマガ登録 /




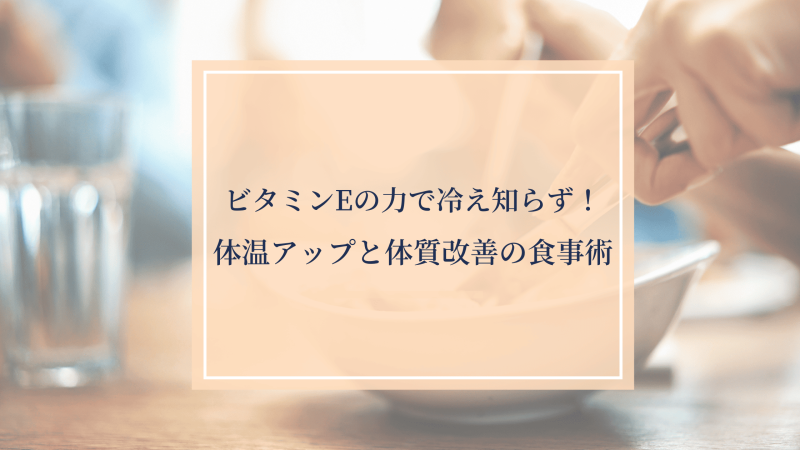
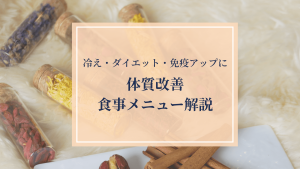

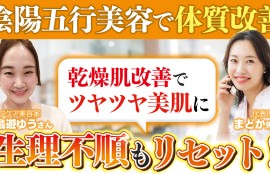
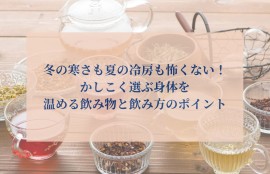
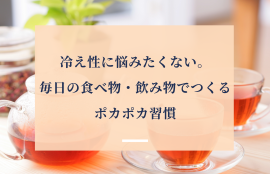
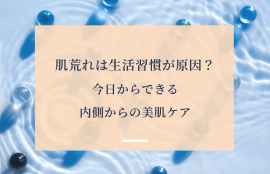
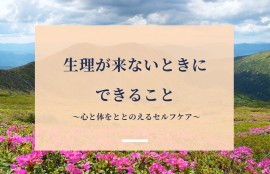
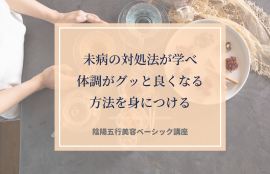
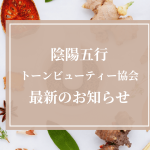

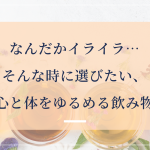

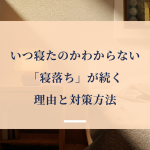
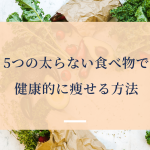
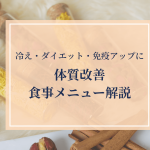
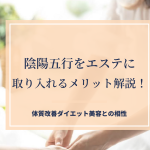
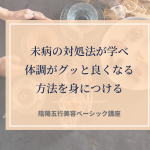
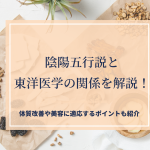
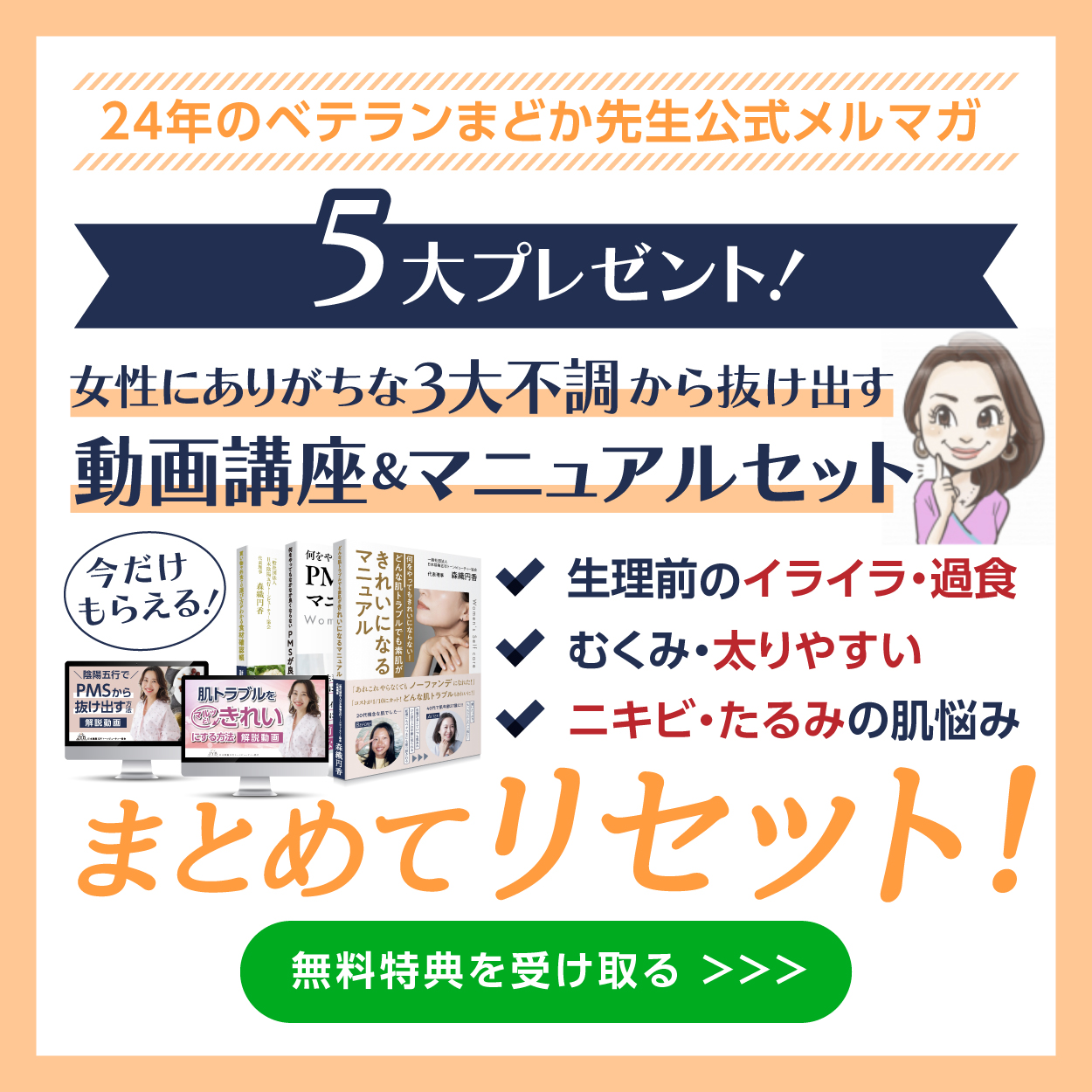
この記事へのコメントはありません。