朝晩の空気がひんやりと感じられる季節。
気づけば手足が冷たくなり、身体の芯まで冷えを感じやすくなる頃です。
「冷え性だから仕方ない」とあきらめていませんか?
実は、毎日の食事の選び方や調理法を少し意識するだけで、
身体の“めぐり”を整え、内側からあたためることができます。
本記事では、東洋の知恵「陰陽五行」の考え方をもとに、
秋から冬への移り変わりにぴったりの“温活ごはん”をご紹介します。
身体をやさしく包み込むような旬の食材と、日常に取り入れやすい食べ方の工夫で、
冷え知らずの心地よい季節を過ごしましょう。
秋から冬にかけて“冷え”が強まる理由


秋が深まり、冬へと向かっていくこの季節。
「最近なんだか冷える…」と感じる人が増えるのには、きちんと理由があります。
特に女性は季節の影響を受けやすく、身体のバランスが乱れやすい時期でもあります。
寒暖差と自律神経の乱れが冷えを招く
秋〜冬は、一日の気温差が大きくなります。朝晩は冷え込み、日中はぽかぽか…。
実はこの 急激な温度変化こそが、自律神経に負担をかけ、冷えにつながる大きな原因 です。
自律神経は、体温調節を行う“司令塔”。
寒暖差が大きいと、体温調整がうまくいかず、身体の末端まで温かい血が巡りにくくなります。
特にこんな人は影響を受けやすい傾向も
- ストレスを溜め込みやすい
- 生活リズムが乱れがち
- 夜更かし気味
- 運動不足
こうした状態だと、自律神経がさらに乱れ、冷えやすくなってしまいます。
女性に多い“隠れ冷え”とは?
「手足は温かいのに冷えている気がする」
「お腹だけ冷たい」「夕方になると足が重い」
それは “隠れ冷え(内臓冷え)” の可能性があります。
秋〜冬は身体が冷えやすいため、血流が内側から滞り、
・お腹
・腰
・太もも
など、外側から触れにくいところが冷えやすくなることがあります。
さらに、
・冷たい飲み物
・生野菜のサラダ
・シャワーだけで済ませる
こうした習慣が続くと、内側からじんわり冷えてしまい、気づきにくい「隠れ冷え」として現れます。
これは季節的なものだけでなく、体質的な傾向ともつながるため、
次章では “食べ物でできる温活” について、東洋医学の視点からお話ししていきます。
体を内側から温める「温活ごはん」の基本


冷えやすい季節こそ、意識したいのが “食べ方” と “食材選び” です。
身体は食べたものでつくられるため、毎日の食事は温活の大きな味方。
ここでは、東洋医学の視点も取り入れながら、身体をじんわり温める食の基本をまとめます。
陰陽五行で見る「温める食材」と「冷やす食材」
陰陽五行では、食材にも「冷やす(陰)」「温める(陽)」という性質があります。
ここで大事なのは、“めぐり”=身体の中の流れ を整えてあげること。
めぐりとは…
- 血の流れ(手足が冷える=血が届きにくい)
- 水分の流れ(むくみ=水の停滞)
- エネルギーの流れ(ストレスで肩がガチッと固まる=気の滞り)
の総称だと考えるとイメージしやすいです。
温める(陽)食材
→ 体が温かさを保ちやすい状態をサポートし、体内の流れがスムーズになりやすい と言われるもの
例:
- 根菜類(にんじん、れんこん、ごぼう)
- 冬の葉物(長ねぎ、白菜)
- 発酵食品(味噌、しょうゆ)
- 香味野菜(生姜、にんにく)
冷やす(陰)食材
→ 体の熱が逃がしやすい性質 を持つため、寒い季節は量を少なめにするとバランスがとりやすい
例:
- 生野菜サラダ
- 南国の果物
- 夏野菜(きゅうり・トマト)
冷えをやさしくサポートする食材の選び方
冷えやすい季節は、体があたたかさを保ちやすいようにサポートしてくれる食材 を選ぶことが大切です。
例えば──
- しょうが、ねぎ、にんにく(体を内側から温める働きがあると言われる)
- かぼちゃ、さつまいも、にんじん(エネルギーを蓄えやすい食材)
- 黒ごま、黒豆(めぐりを整える方向に働きやすいと言われる)
- 鶏肉、羊肉(温かさを保ちやすい体づくりをサポート)
一方で、
- 生野菜や南国フルーツ
- 冷たい飲み物
- 白砂糖が多いお菓子
これらの食材は、身体を冷やしやすいとされるため秋冬は控えめにするのがおすすめです。
日常に取り入れやすい調理法の工夫
温活ごはんは、“調理法” を変えるだけでも効果的です。
ポイントは 「火を通す」「温かくして食べる」 の2つ。
温活に向いている調理法
- 煮る(スープ・味噌汁・煮物)
→ 体をじっくり温め、胃腸にやさしい - 蒸す(温野菜、蒸し鶏)
→ 栄養が残りやすく、温かいまま食べられる - 炒める(生姜炒め、野菜炒め)
→ 手軽に火が入り、体を冷やしにくい
特におすすめなのが、“具だくさん味噌汁”や“根菜スープ”。
温活の基本である 「温め × 巡り × 胃腸にやさしい」 が一度に叶います。
冷えやすい人におすすめの旬の食材リスト


温活ごはんの良いところは、季節に合う食材を選ぶだけで、自然と体が温まりやすい状態をサポートできるというところです。
ここでは、秋〜冬にかけて特に取り入れやすい旬の食材を、「どう体に嬉しいのか」もセットで分かりやすくまとめていきます。
秋の旬食材(9〜11月):じんわり温め、エネルギーを蓄える
秋は、徐々に寒さに備える時期。
“体のベースを整える”食材を意識するのがポイント。
・さつまいも
やさしい甘みで胃腸に負担が少なく、身体のエネルギー源を補いやすい食材。
体が冷えにくい土台づくりをサポートします。
・れんこん
シャキシャキ食感で満足感がありながら、身体にうるおいを与えやすい。
乾燥する秋には特に相性が良い食材です。
・生姜
言わずと知れた温活の定番。
身体の内側からじんわり温かさを感じやすく、スープやお茶にも◎。
・きのこ類(しいたけ・まいたけ・しめじなど)
身体の余分な重だるさ(むくみ)が気になる時期に。
巡りがスムーズになりやすい状態へ自然と整えてくれます。
冬の旬食材(12〜2月):芯から温め、冷えを溜め込まない
冬は、“冷えを深めない”ことが大切。
身体の内側まで温まりやすい食材を中心にとり入れましょう。
・長ねぎ
寒い季節に嬉しい温め食材の代表格。
香り成分がじんわり広がり、温かさが全身に届きやすいと言われます。
・にら
少しスタミナをプラスしたい時に。
冷えによるだるさや、朝起きた時の重さが気になる方にもおすすめ。
・黒ごま
黒い食材は、冬の養生にぴったり。
内側の力を補い、温かさを保ちやすい身体づくりをサポート。
・ごぼう
土の中で育つ根菜は、冬の味方。
身体の内側にしっかり力を蓄え、冷えに負けにくい状態をそっと支えてくれます。
飲み物でやさしく温めるプラス一品
食べ物と同じくらい、飲み物の選び方も大事。
・ 生姜湯
体の中心からじんわり温まりやすい。
砂糖を控えめにすれば毎日でも飲みやすい。
・黒豆茶
香ばしく、クセが少なく飲みやすい“冬の常備茶”。
黒い食材は冬の温活としてもおすすめ。
・甘酒(ノンアル)
天然のやさしい甘さで、胃腸にも負担が少ない。
朝の体を起こす一杯にもぴったり。
旬の食材は自然のサポーター
旬の食材は、
「その季節に必要な力を自然と与えてくれる」 のが魅力。
秋はエネルギーを蓄え、冬は温かさを保ちやすい状態へ導いてくれる──。
そんな、季節に寄り添った食材選びが、“冷え知らずの身体づくり”の第一歩になります。
食べ方で変わる!温活を続けるコツ


温活ごはんは、「何を食べるか」だけでなく、「どう食べるか」も同じくらい大切です。
毎日の習慣を少し見直すだけで、体が温まりやすい状態が続きやすくなります。
ここでは、今日から取り入れられる食べ方の工夫を紹介します。
朝食で体温を上げるポイント
人の身体は、朝が一番体温が低い時間帯です。
そのため、朝食は身体を温め、活動モードへ切り替えるための大事なスイッチになります。
特に意識したいのは次の3つです。
・温かい汁物をつける
味噌汁やスープなど、具だくさんで温かい料理は胃腸が働きやすくなり、体温が上がりやすくなります。
・冷たい飲み物は避ける
起き抜けの冷たい水は体を急激に冷やします。
白湯や常温の水に変えるだけでも、朝の負担が減ります。
・根菜やたんぱく質を少し入れる
にんじん、かぼちゃ、卵、鶏肉など、身体を温める方向に働きやすい食材を朝に取り入れると、一日を通して温かさが保ちやすくなります。
“冷えない習慣”を身につける小さな工夫
冷えは、食べ物だけでなく生活習慣とも深く関わっています。
身体が温まりやすい状態をキープするために、次の工夫を意識してみましょう。
・食事はよく噛んで、ゆっくり食べる
噛む動作は胃腸の働きを助け、消化を穏やかにスタートさせます。
急いで食べると内臓が冷えやすくなるため、少しゆっくり目を心がけると良いでしょう。
・シャワーだけで済ませず、湯船に浸かる
身体の表面だけ温めるシャワーでは、深部が温まりにくいまま。
短い時間でも湯船につかることで、身体の中心からじんわり温まりやすくなります。
・冷たい食材は、火を通すひと工夫
サラダばかりに偏ると身体の内側が冷えやすくなります。
温野菜、蒸し野菜、炒め物にするだけで、身体への負担が変わります。
ストレスケアも温活の一部
「冷え」は身体だけの問題ではなく、心の状態とも関係があります。
緊張やストレスが続くと、肩や背中がこわばり、身体の中の流れが滞りやすくなります。
意識したいポイントは次の通りです。
・深呼吸を数回して、緊張をほどく
呼吸が浅くなると、身体が冷えやすくなります。
ゆっくり息を吐く時間をつくるだけでも、体はゆるみやすくなります。
・温かい飲み物で一息つく時間をとる
白湯やハーブティーなど、穏やかに温めてくれる飲み物は、心にも身体にもやさしい効果があります。
・無理をしすぎない
忙しさや無理の連続は、冷えの大きな要因のひとつです。
身体のサインに耳を傾け、休むことも温活の一部として意識しましょう。
温活は「無理なく続ける工夫」が大切
温活は、特別なことをしなくても、日々の食事と暮らしを少し見直すことから始められます。
「温かいものを選ぶ」「火を通す」「朝に温かいものを飲む」など、続けやすい習慣から取り入れてみてください。
冷え性についてもっと対策したい方は、こちらのブログもぜひ参考にしてみてくださいね!
まとめ|“冷え知らず”は毎日の食事から


冷えを感じやすい季節は、特別なことをしなくても、
毎日の食事や暮らし方を少し整えるだけで、身体はゆっくりと変化していきます。
秋はエネルギーを蓄え、冬は温かさを保つ。
自然のリズムに寄り添いながら、旬の食材を選ぶことは、無理なく続けられる温活の大きな味方です。
- 温かい料理を中心にする
- 旬の根菜や香りのある食材を取り入れる
- 朝に温かい飲み物を飲む
- 生活習慣やストレスケアも同時に整える
こうした小さな積み重ねが、季節の冷えに負けない身体づくりにつながります。
変化は一歩ずつで大丈夫。今日から始められる温活を、できることから取り入れてみてください。

私に合う食事をもっと知りたい!という方はまずは無料でお試しを!


体質別の冷え性対策って何があるの?という方に、
上図の5大登録プレゼント「体質改善&美肌作り完全攻略 有料講座教材5点」と
✅美肌&体質改善攻略合計「175枚」スライド
✅24年のノウハウ公開!限定動画3本60分
の計7点をメルマガより無料でプレゼントしています。
20秒で完了の簡単な登録ですので、ぜひ受け取ってみてくださいね!
\ メルマガ登録 /




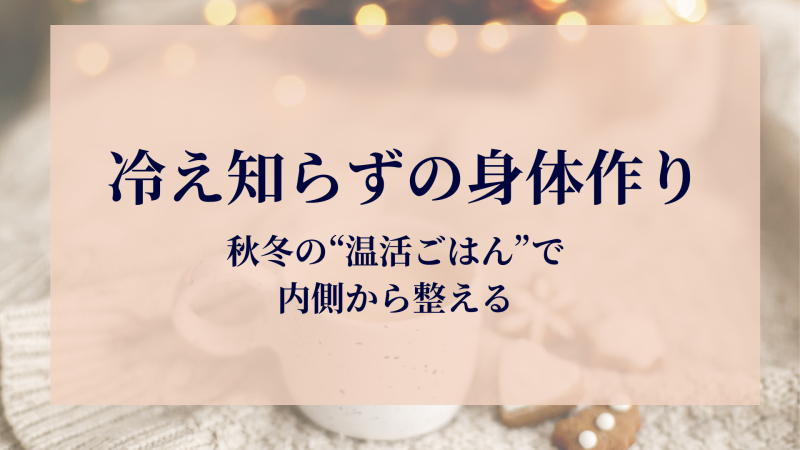

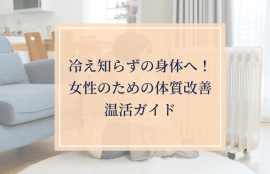
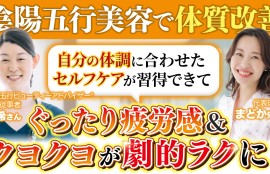
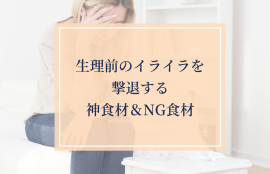


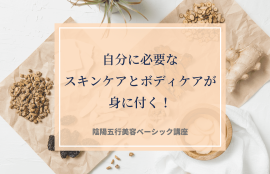
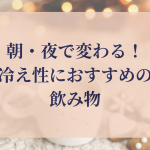
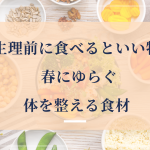

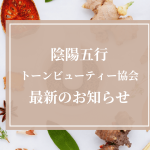

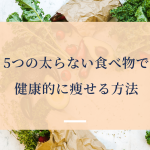
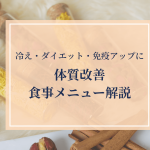
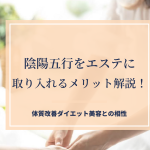
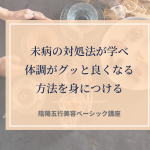
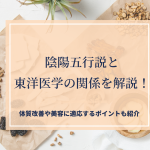

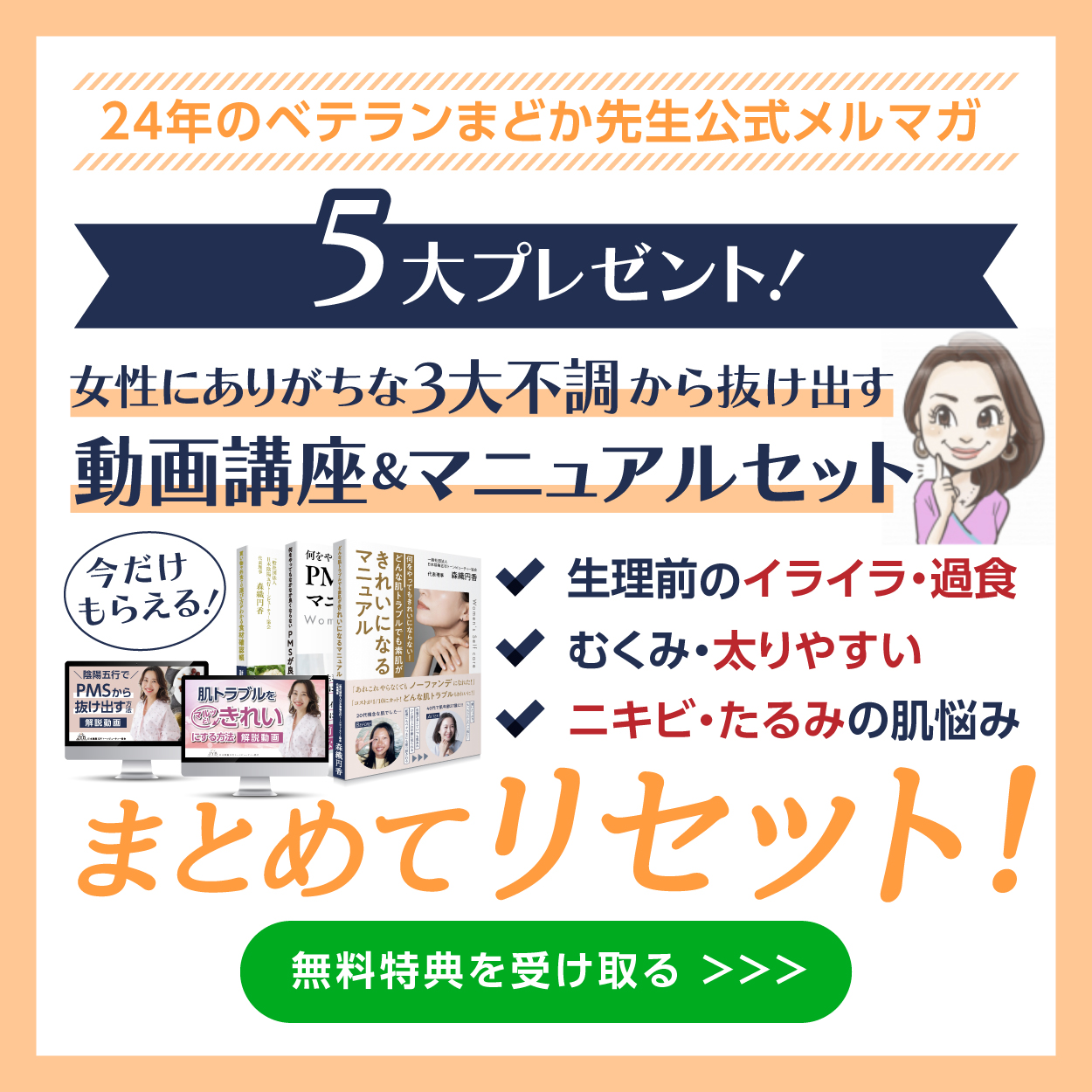
この記事へのコメントはありません。