こんにちは! JYB協会代表理事 森織円香です。
「ベッドに入ったのに頭が冴えて眠れない」「スマホを見ているうちに気づいたら寝落ち」「朝起きても疲れが残っている」そんな経験はありませんか?
現代人の多くが抱えている悩みのひとつが「睡眠」にまつわるもの。仕事や人間関係のストレス、スマホやPCから受ける光や情報の刺激などが、眠りを妨げてしまうこともあります。
陰陽五行の視点から見ると、眠りは「心(しん)」や「腎(じん)」の働きと深い関わりがあります。心がざわついていると寝付きにくくなり、腎のエネルギーが不足すると深い休息が得にくくなる、といったように、心と体のバランスが睡眠に影響するのです。
この記事では、寝落ちや睡眠不足、寝付きにくさといった悩みをテーマに、暮らしに取り入れやすい工夫を「心」「体」「環境」の3つの視点からご紹介します。
陰陽五行のエッセンスも交えながら、無理なく実践できるヒントを集めましたので、リラックスした気持ちで読んでみてくださいね。
睡眠不足のサインに気づこう


眠れていないとき、体や心は小さなサインを出しています。
- 朝起きても頭がすっきりしない
- ぼーっとして集中力が続かない
- 肌の乾燥やくすみが気になる
- ちょっとしたことでイライラする
- 夕方になると強い眠気に襲われる
陰陽五行の考え方では、眠れないときに出てくるサインを「体の中のめぐりの乱れ」としてとらえることがあります。
例えば、心が落ち着かず頭が冴えてしまうのは燃えるような“火のエネルギー“というものが強すぎる時。逆に、体を休ませるために落ち着かせる“水のエネルギー“というものが不足すると、眠りが浅くなりやすいとされています。
つまり、火と水のちょうどよいバランスが取れていることが、すこやかな眠りに繋がるのです。
「私は眠れていないかもしれない」と自覚することは、バランスを整える第一歩になります。
なぜ眠れないの? 睡眠不足の背景

心の影響

考えごとが頭から離れず、布団に入っても心が落ち着かないことがあります。陰陽五行でいう「心(火)」が働きすぎている状態です。火が強まると落ち着きにくく、夢を多く見ることもあります。
体の影響
運動不足や飲食の乱れは「脾胃(土)」を弱め、エネルギー不足につながります。また、腎(水)の力が不足すると、深い眠りを支える力が弱まり、途中で目が覚めやすくなります。
環境の影響
部屋が明るい、スマホのブルーライト、騒音などは「肺(金)」に負担をかけ、呼吸が浅くなりやすいもの。呼吸が整わないと、副交感神経への切り替えもスムーズにいかず、眠りが浅くなります。
自分の睡眠タイプをセルフチェック


眠れないにもいくつかタイプがあります。当てはまるものをチェックしてみましょう。
- 寝付きに時間がかかるタイプ → 心の火が強まりやすい
- 夜中に何度も目が覚めるタイプ → 腎の水が不足しやすい
- 朝早く目が覚めてしまうタイプ → 肺の働きや気の巡りが乱れやすい
- 睡眠時間は長いのに疲れが取れにくいタイプ → 脾胃が弱ってエネルギーが不足している
こうしてタイプを知ると、自分に合ったケアの方向性が見えてきます。
心を整える工夫


眠れない夜の背景には、体の疲れだけでなく「心のざわつき」も大きく関わっています。
特に夜は静かで、自分の思考に意識が向きやすく、日中よりも不安や考えごとが膨らみがちです。
陰陽五行では、心の落ち着きは「火」、呼吸は「金」とつながり、これらのバランスが整うことで安心して眠りに入りやすいと考えられています。
ここからは、そんな心をゆるめるためのシンプルな工夫をご紹介します。
夜の“考えごとメモ”
頭に浮かんだことを書き出すと「心の火」を落ち着けやすくなります。火を紙に移すイメージで、不安ややることを外に出してみましょう。
呼吸でリラックス
「肺(金)」は呼吸をつかさどり、心の安定ともつながります。深呼吸で気を巡らせることは、陰陽五行でいえば金の力を整えることにも。息を吐くことを意識するだけで、自然と体はゆるみます。
夜のルーティン
お茶や香り、日記など「これをしたら寝る」という合図を習慣にすると、「陰の時間」に切り替わりやすくなります。陰を補う小さな儀式が、心を落ち着ける助けになります。
体を整える工夫

適度な運動

日中の運動は「気」を巡らせ、「脾胃(土)」の働きを助けます。気が滞らず循環していると、夜は自然に「陰」に切り替わりやすくなります。
食事と飲み物
- 寝る前のカフェインは「心火」を高めるので控えめに
- 夜食やお酒は「脾胃」に負担をかけ、眠りの質を下げる要因に
- 温かいスープやハーブティーは「腎水」を補い、安心感を与えてくれます
入浴の工夫
熱すぎるお湯は火を強めてしまうので、ぬるめのお風呂で「陰」を養いましょう。体を温め、リラックスした後に自然に体温が下がる流れが、心地よい眠りを招きます。
環境を整える工夫

光をコントロールする

光は「陽」の象徴。夜は暗さ(陰)を意識して、少しずつ照明を落としましょう。陰陽のリズムが自然に体に刻まれます。
デジタルデトックス
ブルーライトは「陽」の刺激を強め、脳を冴えさせてしまいます。寝る前の1時間は「陰の時間」として、スマホから離れてみましょう。
香りや音の力
アロマや自然音は「心火」を和らげ、肺の働きを助けます。金(肺)のエネルギーが整うと呼吸が深まり、自然に眠りやすいモードに。
眠れない夜の過ごし方


どうしても眠れないときは、無理に眠ろうとするほど心が焦ってしまい、かえって目が冴えてしまうことがあります。
そんな時は「眠れない=悪いこと」と思うのではなく、「陰を養う静かな時間」と捉えてみましょう。
例えば、やわらかい灯りの下で本を読んだり、肩や首をほぐすように軽くストレッチをしたり、温かいハーブティーをゆっくり飲むのもおすすめです。
秋冬など乾燥や冷えが気になる季節には、白湯や生姜を少し加えた温かい飲み物で体を内側から温めるのも良いでしょう。呼吸が整い、自然と気持ちが落ち着いてきます。
「眠らなきゃ」と力を入れるのではなく、「今は自分をやさしく整える時間」と思うことで、心と体が休息モードに切り替わりやすくなります。
そして不思議なことに、そうやって力を抜いたときにこそ、ふっと眠りが訪れることも少なくありません。
季節や生活のリズムと睡眠


私たちの睡眠は、体調や心の状態だけでなく、季節の移ろいとも深く繋がっています。日が長くなる春、蒸し暑い夏、乾燥する秋、冷え込む冬。
自然のリズムは、私たちの心身のバランスに大きな影響を与えています。
陰陽五行では、春夏秋冬それぞれが五行(木・火・金・水)と対応し、臓腑や感情、体の働きと関わると考えられています。
その為、季節ごとに「眠りの質が変わる」と感じるのは自然なこと。春は気持ちがそわそわして眠りにくく、夏は暑さやのぼせで眠りが浅くなり、秋は乾燥で呼吸や眠りが乱れやすく、冬は冷えで深く休めない。
こうした変化は五行の視点からも説明できます。
- 春(木):新しい環境で心がざわつき、寝付きに影響することも
- 夏(火):暑さで「心火」が強まり、眠りが浅くなりやすい
- 秋(金):乾燥で呼吸が浅くなり、夜中に目が覚めやすい
- 冬(水):冷えで「腎水」が弱まり、眠りが不安定に
その季節に合ったケアを少し取り入れるだけで、リズムが整いやすくなります。
まとめ 〜眠りは“がんばらない”ケア〜


睡眠は、私たちの心と体をやさしくリセットしてくれる大切な時間です。
けれど「早く寝なきゃ」「ぐっすり眠らなきゃ」と意識しすぎると、かえって緊張して眠れなくなってしまうこともあります。
眠りは“頑張ってつかむもの”ではなく、“自然と訪れるもの”なのかもしれません。
そこで大切なのは、次のような小さな視点です。
- 自分の睡眠タイプを知ること
「寝付きにくいのか」「夜中に目が覚めやすいのか」など、自分の傾向を知ると、工夫の方向性が見えてきます。 - 陰陽五行で心・体・環境のバランスを意識すること
不眠や寝付きの悪さは、心(火)、肺や呼吸(金)、腎やエネルギー(水)などのバランスの乱れが関係していることも。東洋医学の知恵をヒントにすると、自分の状態をやさしく見つめ直すきっかけになります。 - 季節に合わせて小さな工夫を続けること
春は心を落ち着ける習慣、夏は熱を冷ます工夫、秋は潤いを補うケア、冬は体を温める暮らし。自然のリズムに合わせることで、睡眠も調和しやすくなります。
眠りは「整えなきゃ」と肩に力を入れるよりも、「楽しみながら工夫する」ほうが、ずっとやさしく寄り添ってくれます。
寝る前の小さな儀式や、季節を感じるセルフケアを取り入れながら、あなたに合った眠りの形を見つけてみてください。
今日の夜が、少しでも心地よく、明日への活力につながりますように。

ぐっすり眠りたい!という方はまずは無料でお試しを!


睡眠不足を解消したいという方に、
上図の5大登録プレゼント「体質改善&美肌作り完全攻略 有料講座教材5点」と
✅美肌&体質改善攻略合計「175枚」スライド
✅24年のノウハウ公開!限定動画3本60分
の計7点をメルマガより無料でプレゼントしています。
20秒で完了の簡単な登録ですので、ぜひ受け取ってみてくださいね!
\ メルマガ登録 /




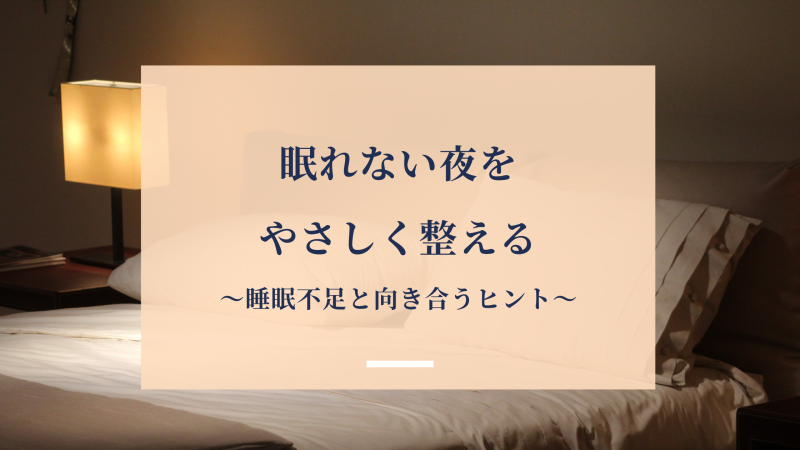

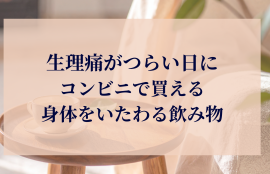
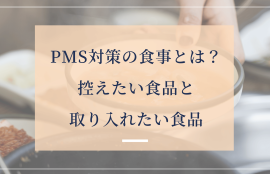
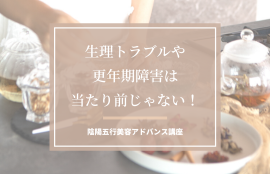
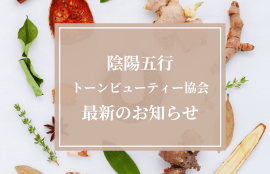
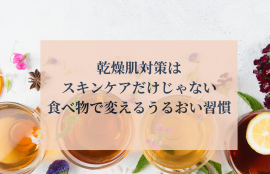
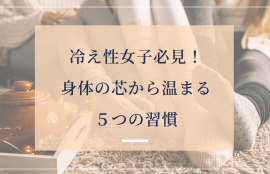
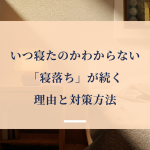
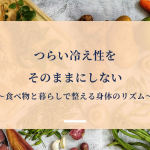
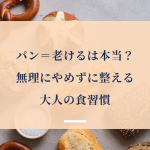
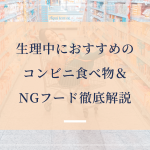
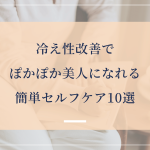
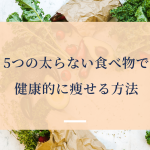
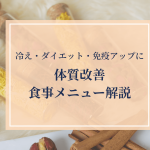
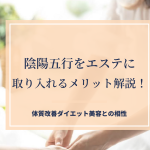
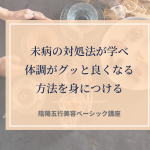
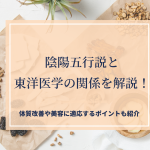

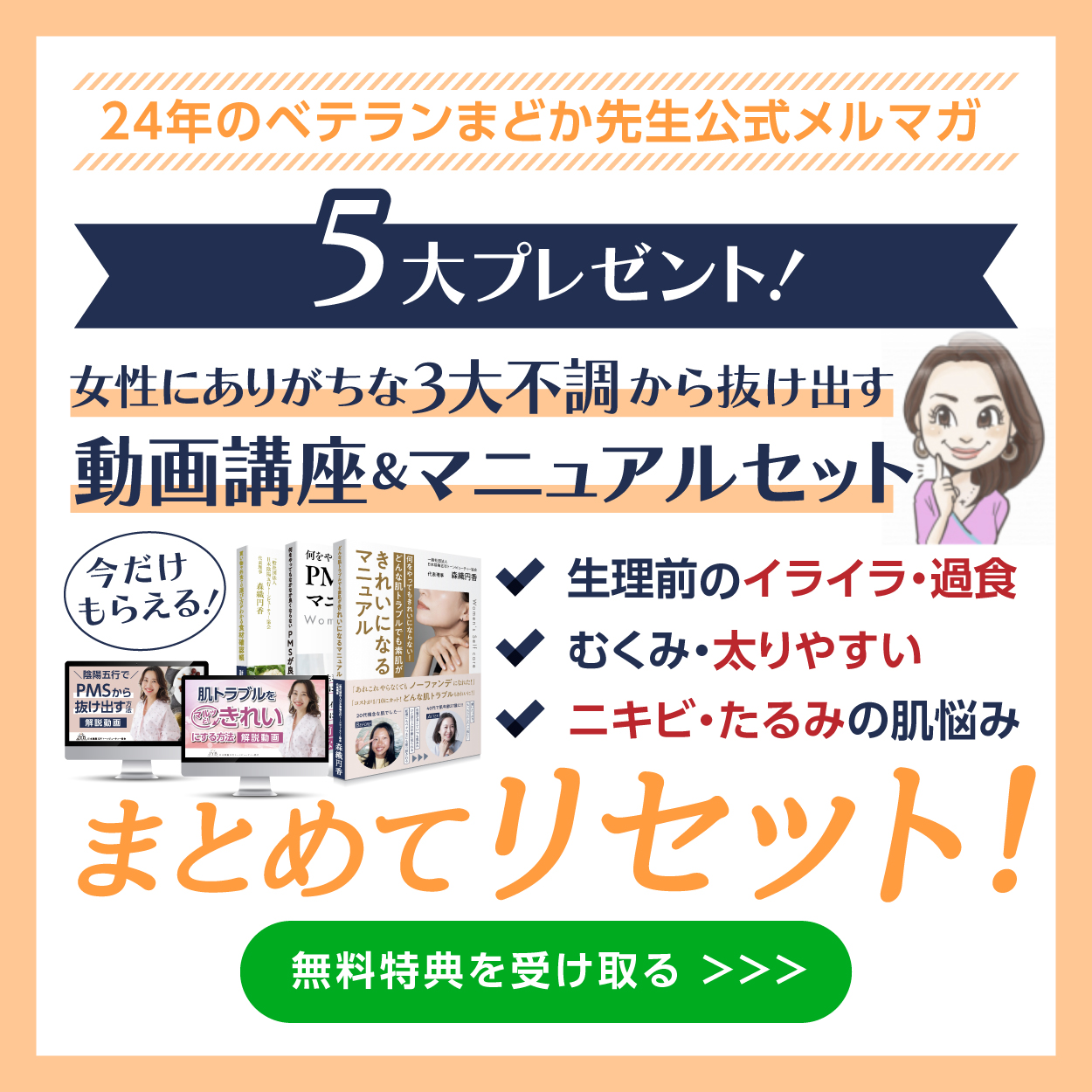
この記事へのコメントはありません。