忙しい日の朝ごはんやお昼ごはん、外出時の軽食としても便利なおにぎり。
手軽で親しみやすいメニューだからこそ、選ぶ具材によって「身体へのやさしさ」が大きく変わります。
ここでいう“身体にやさしい”とは、胃腸に負担をかけず、身体を冷やしにくく、食後も重くなりにくいという意味。
とはいえ、健康的と言われる具が多くて迷ってしまう、何を選ぶのが自分に合っているのか分からない、という声もよく聞きます。
そこで本記事では、毎日の食事に無理なく取り入れられる「体をいたわるおにぎりの具」について、栄養的な視点だけでなく、身体に負担をかけにくくするための具材の選び方や、日々の体調に合わせた工夫も交えながら紹介します。
いつものおにぎりをほんの少し工夫するだけで、負担が少なく、食後の満足感も続きやすい“身体にやさしいおにぎり”に。
今日から試しやすい具材選びのヒントをお届けします。
おにぎりの具で健康を左右する理由


おにぎりは、炊いたご飯と具材、そして塩だけで作られる、とてもシンプルな食事です。
だからこそ、使う具材によって体への負担や満足感、食後の軽さが大きく変わります。
市販のおにぎりを見ると、油分や濃い味付けが特徴の具が多いため、
「毎日食べるなら、どんな具を選べば体にやさしいのか?」という視点が大切になります。
シンプルだからこそ差が出るポイント
おにぎりの健康度を左右する主なポイントは次の通りです。
- 塩分量
- 脂質の多さ
- 消化しやすさ
- 温度や食べ方による体の冷え
- 食後の満足感の持続
具材の選び方によって、これらのポイントは大きく変わります。
例えば、脂っこい揚げ物系の具は満足度が高い反面、胃腸に負担がかかりやすい傾向があります。
一方で、梅干しや昆布などの伝統的な具は、塩味と旨みで食べやすく、食後も軽さが続きやすい特徴があります。
ご飯より“具材”で健康差が生まれやすい理由
白ご飯は基本的にどの家庭も大きく差はありませんが、具材は人によって選ぶものが大きく違います。
例えば、
- 塩鮭なのか、鮭フレークなのか
- 昆布なのか、佃煮昆布なのか
- 卵そぼろなのか、マヨ系の具材なのか
同じ名前の具材でも、調理方法や味付けによって健康への影響は変わります。
そのため、健康を意識するなら、
「どの具材を選ぶか」
「どんな味付けにするか」
という視点がとても大切です。
体をいたわる“やさしい具”の選び方


おにぎりは日常的に食べる機会が多いからこそ、体に負担をかけにくい具材を選ぶことがポイントになります。
ここでは、初心者でも迷わずに選べる「体をいたわる具材の基準」を整理します。
消化にやさしいこと
胃腸が疲れている時や、朝食におにぎりを食べる場合は、消化のしやすさが大切です。
脂っこい、濃い味、硬い食材は、朝の体には負担になることがあります。
選ぶと安心な具材の目安
- シンプルな塩味(梅、昆布、鰹)
- あらかじめ火が通っているもの(鮭、卵)
- やわらかい食材(おかか、そぼろ)
逆に、揚げ物やマヨネーズたっぷりの具は満足度は高いものの、消化には時間がかかりやすい傾向があります。
味が濃すぎないこと
おにぎりは「塩」と「具材」で味が決まるため、具の味が濃いと塩分過多につながりやすくなります。
健康を意識するなら、素材の旨みで食べられる具材を選ぶと安心です。
例:
- 昆布は佃煮よりも素朴なタイプの方が塩味控えめ
- 鮭はフレークよりもほぐし身の方が味がシンプル
- 梅干しは“はちみつ漬け”よりも伝統的な塩梅の方がバランスがよい
「旨みがあるのに強すぎない」という具材は、飽きにくく毎日でも取り入れやすいのが特徴です。
体を冷やしにくいこと
気温が低い日や冷えを感じやすい人には、身体が冷えにくい具材・調理方法を選ぶのがポイントです。
温かい性質の具材
- 鮭
- 梅干し
- 生姜を使ったそぼろ
- かつお節
冷えやすい具材の例
- 冷たいままのツナマヨ
- 生のままの具材
- 夏野菜を大量に混ぜるもの(きゅうりなど)
体を冷やしにくい具材は、食後も体が温まりやすく、満足感も続きやすくなります。
食後の軽さと満足感の両立
「軽いけれど、満足できる」
このバランスが取れている具材が、日常的に食べるおにぎりには適しています。
例:
- 梅おかか
- 昆布とごま
- 鮭と大葉
- 卵そぼろ(甘さ控えめ)
シンプルな組み合わせは食べ飽きしにくく、体調にも合わせやすい点が魅力です。
健康的で取り入れやすい定番の具材


ここでは、日常的に取り入れやすく、体への負担が少ない具材を中心に紹介します。
どれもスーパーで手に入りやすく、作りやすいものばかりです。
鮭(塩鮭・焼き鮭)
おにぎりの定番でありながら、体を冷やしにくい具材のひとつ。
焼いてほぐした鮭は、油分も少なく食べやすいのが特徴です。
市販の鮭フレークは味が濃く油分が多いものがあるため、自宅で焼いた鮭をほぐすのがおすすめです。
ポイント
・味付けを薄めにすると毎日でも食べやすい
・温かいご飯との相性がよく、冷えを招きにくい
梅干し
昔ながらの「塩だけで漬けた梅干し」は、おにぎり具材の中でも特に飽きにくい一品。
酸味と塩味が食欲を自然に引き出し、食後も軽い満足感が続きます。
ポイント
・はちみつ漬けより伝統製法の方が味がシンプル
・ご飯と合わせることで疲れにくい軽さがある
昆布(塩昆布、昆布の旨煮)
旨みが強いため、少量でも満足感を得やすい具材。
特に素朴な昆布の旨煮や塩昆布は、脂質が少なく、体への負担が控えめです。
ポイント
・佃煮は甘味が強いものが多いため、選ぶ際は味の濃さに注意
・ごまを少し混ぜると風味が増して食べやすくなる
おかか(かつお節)
かつお節はシンプルで身体を冷やしにくい食材のひとつ。
しょうゆをほんの少しだけ加えると、旨みが立って満足感が出ます。
ポイント
・塩分の摂りすぎを防ぐために、しょうゆは控えめに
・ごまや少量の海苔と組み合わせても相性が良い
卵そぼろ(甘さ控えめ)
優しい甘さとやわらかさで、子どもから大人まで人気の具材。
卵は消化にやさしく、忙しい朝にも食べやすい存在です。
ポイント
・甘すぎない方が毎日でも食べやすい
・温かいご飯ともよくなじむ
野菜混ぜご飯の具(にんじん、ごぼう、ひじきなど)
野菜を刻んで炒めたものや、ひじきの煮物などを少量混ぜるおにぎりは、食物繊維が取りやすく、満足度が高まります。
色々な具材を少しずつ取り入れられるため、飽きにくいのが特徴です。
ポイント
・根菜類は体を冷やしにくい
・醤油や砂糖の入れすぎに注意し、薄味にすると続けやすい
体を冷やしにくいおにぎりの工夫(作り方・温度の工夫)


おにぎりは具材だけでなく、作り方や温度の工夫によっても、体の冷え方が大きく変わります。
特に気温が低い季節や、冷えを感じやすい人にとっては重要なポイントです。
温かいご飯で握る
炊き立て、または温めたご飯で握ると、おにぎり全体がふんわり温かく保たれます。
冷たいご飯は体を冷やしやすくなるため、できるだけ温度のある状態で仕上げることが大切です。
ポイント
・温かいご飯は具材の風味が引き立つ
・手早く握ることで余計な水分を含みにくい
冷たい具材は“ひと工夫”して使う
冷蔵庫から出してすぐの具材は、おにぎり全体を冷やしやすくします。
ツナや卵、鮭などは、常温に少し置くか、ほんのり温めるだけで食べ心地が変わります。
工夫例
・ツナは油を切って軽く混ぜて常温に戻す
・冷蔵の卵そぼろは短時間レンジで温める
・梅干しや昆布はそのままでも温かいご飯によくなじむ
海苔の使い方で温かさが変わる
海苔は風味だけでなく、温かさを閉じ込める“カバー”の役割もあります。
巻くタイミングを工夫すると、好みの食感と温度が両立できます。
おすすめの巻き方
・握った直後に巻けばしっとり&温かさが残りやすい
・食感を重視する場合は直前に巻く
塩加減を見直すと食後が軽くなる
塩分が多いと体内の水分バランスが乱れ、むくみやすくなります。
冷えやすい人は、むくみが冷えにつながることもあるため、控えめの味付けが安心です。
工夫例
・塩は表面に薄くつける
・具材が塩味強めの場合は追加の塩を控える
・昆布やおかかなど旨みの強い具材で満足度を補う
体にやさしい具材の選び方(避けたいもの・注意したいポイント)


おにぎりを毎日の食事に取り入れるなら、どんな具材を選ぶかが大切です。
体への負担を減らし、食後の軽さを保つためのポイントを整理します。
冷たい状態で使う具材は避ける
冷蔵庫から出したばかりの具材は体を冷やしやすく、消化にも負担がかかります。
常温に戻すだけでも食べやすさが変わります。
例
・冷えたツナ缶
・冷たい卵サラダ
・冷たい蒸し鶏や野菜
油分の多い具材は負担になりやすい
油分は冷えると固まり、体を重く感じやすくなります。
揚げ物やマヨ系は量を減らすだけでも負担が軽くなります。
例
・ツナマヨ、卵マヨ
・天むす、唐揚げおにぎり
・油で炒めた具材
味が濃い具材は控えめにする
塩分や糖分の強い具材は、体内の水分バランスを崩しやすく、結果的にめぐりが乱れやすい原因に。
例
・濃い鮭フレーク
・甘辛いそぼろ
・味が濃い佃煮類
具材を詰め込みすぎない
具材が多いほど豪華に見えますが、消化の負担が大きくなります。
少量で十分満足できる具材は控えめに使うのがコツです。
適量の目安
・具材は中央に軽く乗る程度
・1種類に絞ると負担が少ない
・混ぜ込みは“軽く広がる程度”に
季節や体調に合わない具材は避ける
体は季節や体調の影響を受けやすいため、その日の自分に合った具材を選ぶことが大切です。
例
・冬:冷たいサラダ系は避ける
・夏:濃い味より軽い具材を選ぶ
・胃腸が弱い時:刺激の強い具材は控える
自分の体質に合わせた具材選び


同じ「おにぎり」でも、人によって心地よい具材や、負担を感じにくい具材は異なります。
ここでは東洋医学の考え方をヒントに、体質に合わせて選びやすい具材を紹介します。
難しい専門用語を使わず、“どんな人にどの具材が合いやすいか” をわかりやすく整理しています。
冷えやすいタイプ
体が冷えやすく、朝や冬の寒さが特につらい人は、温かさを保ちやすい具材が向いています。
おすすめの具材
- 焼き鮭
- 梅おかか
- 生姜入りそぼろ
- 昆布とごま
- ひじきの煮物(薄味)
ポイント
- 温かいご飯で握る
- 冷蔵の具材は常温に戻す
- 脂質の多い具材は避ける
体を温める方向に働きやすい具材が、食後の軽い温かさをサポートします。
疲れやすいタイプ
少し活動すると疲れやすい、午前中にエネルギー切れしやすい人は、消化しやすい具材が合っています。
おすすめの具材
- 卵そぼろ(甘さ控えめ)
- おかか
- 炊いた根菜(にんじん、ごぼう)
- 鮭のほぐし身
- やわらかい野菜混ぜご飯
ポイント
- 具材の味を濃くしすぎない
- 油を使わず、蒸す・煮るなどの調理が合う
- 温かいスープと組み合わせると食べやすい
負担が少なく、すぐにエネルギーとして使いやすい具材が適しています。
むくみやすいタイプ
夕方になると手足が重い、体の水分が滞りやすい感覚がある人は、軽さのある具材が向いています。
おすすめの具材
- 昆布
- 梅干し
- かつお節
- ごま
- 大葉や少量の薬味
ポイント
- 水分が多く冷たい具材は控えめに
- さっぱりした味付けの方が合いやすい
- 海藻類や香りのある具材が食べやすい
軽さと満足感のバランスが取りやすい具材が合うタイプです。
ストレスがたまりやすいタイプ
肩や首がこわばりやすい、気分が張りやすい、つい食べすぎてしまう……
そんな人には、香りのある具材や“ほっとする味”が向いています。
おすすめの具材
- 梅しそ
- 昆布とごま
- おかかに大葉を少し
- 焼き鮭
- 野菜の混ぜ込みご飯(根菜中心)
ポイント
- さわやかな香りは体のこわばりがゆるみやすい
- ぬるめの味噌汁と合わせると食べすぎも防げる
- 重い具材は反対に疲れが増しやすい
心身の緊張がほどける具材が合いやすいタイプです。
自分に合ったおにぎりの具でアンチエイジングも!こちらも、一緒に読まれていますよ!
まとめ:無理なく続ける“体をいたわるおにぎり習慣”


おにぎりは身近で手軽な食べ物だからこそ、具材や作り方を少し工夫するだけで、
体にやさしい食事へと変えることができます。
素材に近い味を選ぶ、温かい状態で握る、脂質の多い具材を控える。
こうした小さな積み重ねが、毎日の食事の心地よさにつながります。
また、自分の体質や季節に合わせて具材を選ぶことで、
「今日の自分に合う食事」が分かりやすくなり、食後の軽さも変わります。
健康的な食事は、完璧である必要はありません。
続けられる形に整えながら、負担の少ない具材を取り入れるだけでも、身体は少しずつ心地よい方向へ向かっていきます。
いつものおにぎりを、少しだけ今の自分に合うものに。
無理なく続けられる、あなたらしい食の習慣づくりに役立ててください。

自分に合ったおにぎりを知りたい!という方はまずは無料でお試しを!


私も食事で楽しく、活き活きと過ごしたい!自分に合った食材についてもっと知りたい!という方に、
上図の5大登録プレゼント「体質改善&美肌作り完全攻略 有料講座教材5点」と
✅美肌&体質改善攻略合計「175枚」スライド
✅24年のノウハウ公開!限定動画3本60分
の計7点をメルマガより無料でプレゼントしています。
20秒で完了の簡単な登録ですので、ぜひ受け取ってみてくださいね!
\ メルマガ登録 /




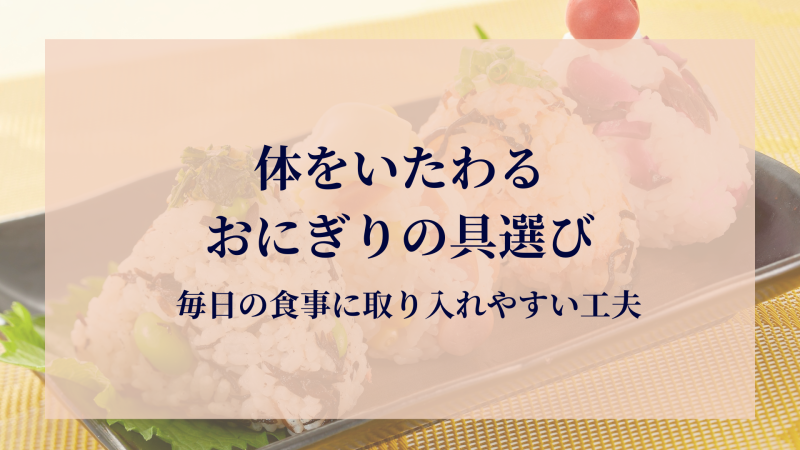



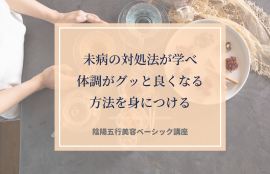

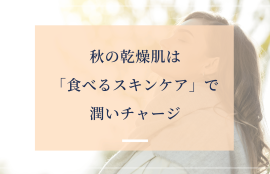

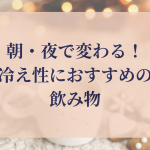
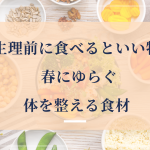

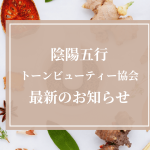

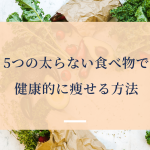
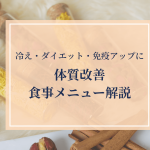
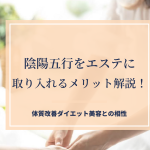
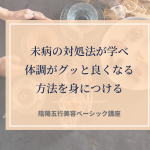
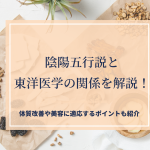
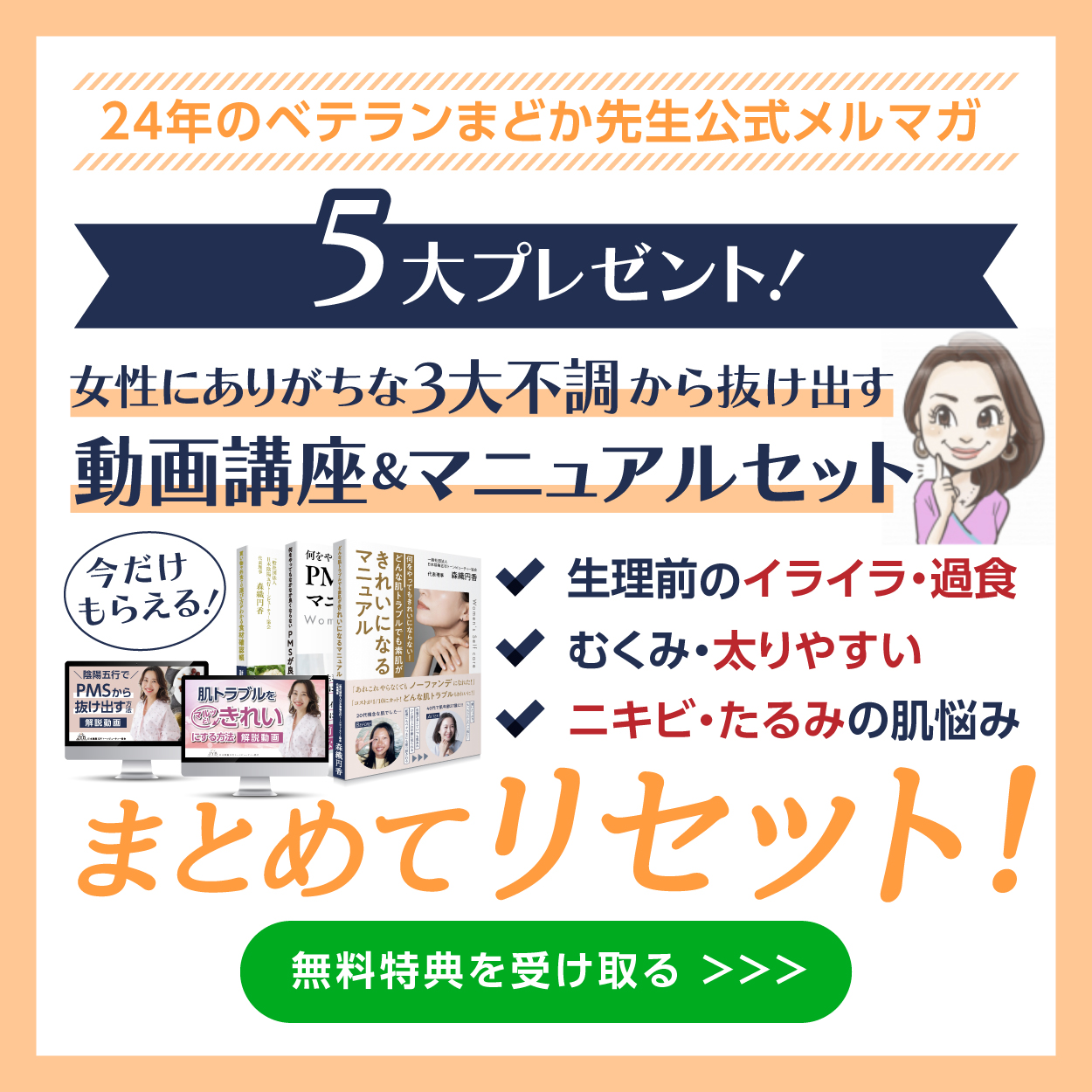
この記事へのコメントはありません。